これまで、人物、花、家族、標本、屋久島の原生林など、幅広い被写体を膨大に撮影してきた上田義彦。2015年には、35年間の写真家活動の集大成として、仕事と作品を写真集『A Life with Camera』という形で、その世界観をひとつにまとめあげたのも記憶に新しい。一貫して、世界に向かって真摯に対峙しながら、被写体のまとう目には見えない気配や、被写体を取り巻く全体性を印画紙に写し取ろうと試みてきたが、彼が今回心奪われたのは、北関東の村で出会った素朴な林檎の木だった。
インタヴュー・構成=小林英治
写真=高橋宗正
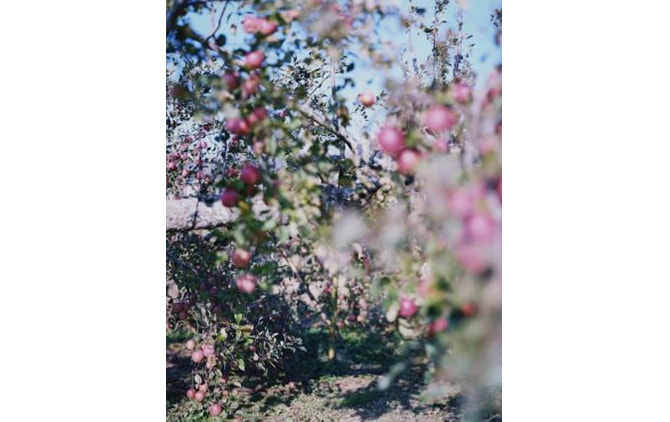
林檎の木 6(部分)2017 © Yoshihiko Ueda, Courtesy of Tomio Koyama Gallery
記憶を頼りに歩いて探した林檎の木
―今回の作品「林檎の木」は、2013年に群馬県川場村で開催された「川場町ネイチャーフォトフェスティバル」に審査員として訪れたことがきっかけということですね。
はい。川場村の駅からタクシーで会場に向かう途中、ぼんやりと外を見ていたら、林檎の赤い色が目に入ってきて、瞬間的に撮りたいと思いました。ちょうどいい光が当たっていて、ワクワクするような嬉しい色でした。カメラを持っていなかったので、記憶にだけ残ったのですが、その記憶が、東京に戻ってからもことあるごとに出てくる。これは撮らないといけない、という気持ちがどんどん膨らんでいきました。
―そういうことは過去にもあったんでしょうか?
たびたびありますね。それは撮り逃したときにものすごく強く残る。まあ、病気のようなものだと思います。今回も毎年林檎の時期になると、例えばスーパーで林檎を見て綺麗だなと思った瞬間にも思い出す。あ、そうだと。それで一昨年に、来年(2016年)は必ず撮ろうと決めて、最初に訪れた時期と同じ11月に川場村へ行きました。
―タクシーで通り過ぎた場所は覚えていたんですか?
それが川場村のどの場所なのか、全くわからなかった。林檎の印象はすごく強いのですが、場所については曖昧な記憶しかなくて、古い蔵が見えてから次の瞬間に林檎が見えたことだけ、覚えていました。それで、役場の方にお会いしてそう伝えたら、「このあたりは林檎畑が多いから、そういう風景はよくあります」と(笑)。それで役場の方に良さそうなところに連れていってもらいました。ただ、連れて行かれたところは、いわゆる生産農家で、林檎の実はたくさんついているものの、木も若くて、僕としては感じるものがありませんでした。
―川場村の林檎畑ならどこでもいいわけじゃなかったんですね。
はい。生産農家の林檎園を撮ることになると、すごく難しいなと、瞬間的に思いました。喜びのようなものが湧いてこないし、これでは撮る理由がないなと。日光もちゃんと当たって赤い林檎が実っているのに何も感じないというのは、場所の問題でもあると思いました。それで、役場の方とはそこで別れて、助手と3人で8×10のカメラを担いで歩いて探すことにしました。

―上田さんの記憶の中には確かにある場所、ですね。
かなり歩きまわったと思います。そうすると、だんだん勘のようなものが働き始めて、ある道を歩いていたら、何の根拠もないのですが、この道じゃないかなと思い始めた。さらに歩いていくと、蔵が見えてきて、まさにタクシーから見た場所にたどり着きました。嬉しかったですね。そこは、いわゆる生産農家ではあるのですが、整然と木が並べて植えてあるのではなく、ランダムに大きい木が植わっていました。
―そのとき見た林檎の木にも、数年前にタクシーから見たときと同じ感動がありましたか?
ありましたね。それは木の生命力だと思うのです。農家の方に挨拶に行ったとき、このあたりで一番古い木だという話をしていましたから、栽培のために育てられたのではなくて、昔からあった木なのだと思います。そういう古い自然な木がもつ生命力であったり、時間であったり、姿というものを、見た瞬間に、意識しないレベルで受け止めている。
―撮影には何度か行かれたんでしょうか。
3回くらい続けて行きました。その日は泊まって、翌日も撮影。戻って現像、プリントしてから、改めてもう一度行きました。

暗室作業で見つけた親密さを感じるサイズ
―実際の撮影の方法は、上田さんの中で最初からイメージされていたのでしょうか。例えば屋久島の原生林を撮るのと同じ態度であったりとか。
そうですね、森を撮るように。ある意味同じテーマだと思いますので、何か全く別の入口から、新たなこととして撮るというものではなかったです。
―屋久島の原生林の作品はとても大きなサイズでしたが、今回展示されている林檎の写真はとても小さなサイズになっています。そこにはどのような違いとプロセスがあったのでしょうか。

林檎の木 6 2017 c-print, acrylic frame © Yoshihiko Ueda, Courtesy of Tomio Koyama Gallery
まずは森で撮るのと同じように、120×170~80cmくらいの大きなプリントをしました。最初は良いなと思ってしばらく眺めていましたが、見ているうちに何か違うと感じるようになりました。大きさによる迫力はあるのですが、実際の木を撮りながら湧いてくるような親密な喜びがないというか、こういう迫力がほしいわけじゃないのだな、と。それで、最適なサイズを探すために、いきなり8×10のフィルムの原寸サイズに戻しました。ここから始めよう。そこに戻れば、僕が8×10のカメラを覗いて感じたことに戻れるかもしれない、と考えました。

―暗室での試行錯誤が始まったわけですね。
暗室は、僕にとって一番好きな場所ですが、乱闘場所のようなものでもあります。8×10に戻したら、いきなり良くなりました。でも、ちょっと火がついたので、もう少し小さい4×5にしたらどうなるのだろうと思ってやってみたら、さらに良かった。これはどういうことだろう?と。もっと小さく今度は6×7にしてみたら、急に良く見えなくなりました。そのあたりに何かあると感じたので、そこからはちょっと自分でもわからないくらいにサイズを細かく刻んでプリントしていきました。そうすると、今回決めたサイズ(86×68mm)が一番しっくりきて、これだなと思ったのです。
―ここまでプリントのサイズを小さくしていくっていうのは初めてのことですか?
初めてですね。そもそもネガフィルムで撮るということは、プリントで拡大するというのが大前提ですから。でも、この写真は、6×7や35mmで撮って拡大するのではなく、8×10で撮ってこのサイズに小さくすることに意味があると、僕の中で必然性のようなものを感じました。それは、撮影しているときに感じた「親密さ」というのが、ここにたどり着く過程で大事な言葉になっていたからです。小さい写真をよく見るためには、写真に身体を近づける行為をしないといけないですし、近づいていろんな情報が入ってきたときに、もし喜びを感じてくれる人がいれば、それは親密感というのが一番強い状態で見ていることになると思います。それからまた離れて見たり、もう一回近づいて見たり。
―この作品を見るには一定の最適な距離があるのではなく、近づいたり離れたりする運動こそが重要だと。
そうですね。この写真がそのような運動を引き起こすのだと思いますし、最初に大きくプリントしたときに親密さが足りないと思ったことの答え、つまり、実際に林檎の木を見て感じた喜びに近い親密な感覚が一番再現できるサイズがこれだったのだなと、いまは思います。

8×10という不自由なカメラが生み出した身体
―写真を見ると、被写界深度も浅く、焦点が合っていないところはぼやけています。
こういう風に、自分の目で見たままに撮りたいという気持ちは、ある時期から現れてきたものです。昔はパンフォーカスで絞りきって手前から奥まで焦点を合わせていましたが、最近は自分が立ったそこが「写真の場所」なのです。カメラを担いで立つと、その前にスッとカメラが来て、そこが写真の場所になる。要するに、身体が自然に止まってしまったところが、ということです。カメラを構えてからああだ、こうだとは僕は一切やりません。自分が見ている場所があって、それを写せばいい。たぶんそれをはっきりさせるために、パンフォーカスではなくなったのです。
―上田さんが使っている8×10というカメラとも関係してると思いますか?
8×10で30年くらいやってきたものですから、そういう見方や構え方になってきたと思います。実は、僕は35mmでも立ったところでそのまま撮るのですが、そういう身体にもうなってしまっているのです。重要なことは、身体と写真はすごく関係しているということです。僕の場合は、やはり8×10という非常に不自由なカメラのおかげで、身体を先に先にという感覚になっていったと思います。身体はドキドキしたり、動けなくなったりするわけですから、そこにカメラさえあれば、その感覚は写るだろうし、そのまま写ってほしいと思います。カメラで撮ってるというよりは、目とどこか、ある人に言わせれば魂の場所で撮るといいますか、そういうことだと思います。
―カメラを持っているときと、持ってないときの見方は違いますか?
変わります。多分「魂の場所」というところに届かせるには、カメラがないといけないのだと思います。言葉にできない、ある状態だと思うのですが、喜びであったりとか、そういうものを感じる場所。それは必ずあるだろうと思って、そことの交信がないと、自分自身も納得する写真にはならない。そう感じるのも、いろいろ思うと、やっぱり8×10というカメラでずっとやってきたからかな、と。不自由なカメラに身体でつながろうとすることが必要になってくるので、そういう力を使っている間に、いまのようなスタイルになっていったのだと思います。

白い印画紙の余白部分も含めた全体が作品
―今回の作品の大きな特徴として、林檎の木の画像のサイズは小さいのですが、その周りの印画紙には、余白のような白いスペースが大きくとられています。つまりプリント全体のサイズとしては大きいわけですが、これも上田さんとしては必然性があってのことですよね。
この小さい写真だけでいいじゃないかと思われるかもしれません。ここが、言葉で説明ができない部分ではあるのですが、それでは僕が思っているものと全然違うものになってしまうということは、すごくはっきりしていました。例えば、ある大きさから縮小していったというプロセスも、理由のひとつかもしれません。この印画紙の余白がないと、画像がこのサイズである根拠がなくなってしまう。
―この白い部分に暗室でのプロセスが残っているということですね。
そうです。実は全部を含めてこの作品だと思っているので、「余白」と呼ぶのが相応しいのかわからないですが。
―林檎の木のイメージ自体は小さくなっていますが、写真全体のイメージとしては余白部分を含んでいると。そうなると「余白」という言い方は違うかもしれないですね。
そうですね。あの広さの余白がないといけないのですが、デザインだと思われても違う。だから、いい言葉を見つけないといけませんね。
―1枚の大きな横長の印画紙に、小さなイメージが2~3点配されている作品もありますが。
そうですね。1本の林檎の木を3枚の写真で構成しているものは、それぞれ1点ずつでも独立した作品になり得るのですが、今回はあえて3連の作品として1枚の印画紙にプリントしました。
―複数のイメージを1枚の印画紙に現像するのは、技術的にはかなり難しいのではないかと思うのですが。
暗闇の中の手作業で、機械がやったかのように正確な位置にプリントしないといけないので、そもそも技術的に難しい。暗室内でライトはつけられませんから、1枚目の露光が終わったら、指先の感覚だけを頼りに紙だけ横に動かして、引き伸ばし機のフィルターの数値を変えてと、暗闇の中、手探りでやります。今回、作品のエディション数は3枚にしたのですが、カラーの現像はその日の温度や液の状態のわずかの違いに影響されてしまうので、同じ条件で一度にプリントしないといけないから、根を詰める大変な作業でした。何でこんなこと思いついてしまったのか、と(笑)。
フレームではなく透明な箱に印画紙を閉じ込める
―そうして完成した写真は、また特殊なアクリルのケースに入れられています。
今回、フレームもすごく難しかった。余白としかいいようがない印画紙の白い部分を含めての全体、その真ん中に画像がある。その意味というのが、普通の額装にすると消えてしまう。つまり、この余白はただの余白ではないということなのですが、そこにフレームをつけてしまうと、なんだか急にデザインしたような計算された見え方をし始める。フレームを付ける前に見ていた感覚と全然違ってしまって、要するに、誤解が生じてしまう。
―それまでの試行錯誤が水の泡になってしましますね。
まったくその通りで、ものすごくイライラしました(笑)。次にアルポリック貼り(アルミの合板をプリントの裏に張る手法)を試してみましたが、今度は裏打ちしたフラットなアルミの影響を受けていきなり金属的なサーフェイスを現しはじめ、表情が変わってしまった。やはり、僕は印画紙を感じ取りたい。それで思い浮かんだのが、以前、東京大学と一緒に取り組んだ「マニエリスム博物誌」シリーズの写真集で作ったアクリルの箱でした。印画紙そのものを、昆虫採集の標本のように中に閉じ込められないかと思ったのです。
―枠で囲むのではなく、透明な箱に閉じ込めるという発想ですね。
突然ひらめいたのですが、これはこれまでのプロセスと道理に合うので、うまくいくのではないかと思いました。ただ、プリントを挟むアクリルの隙間が1mm程度しかなく、作ってくれる工場も初めてのことで大変だったようです。実際できて印画紙を入れてみたら、まさに僕が思ったような見え方で、写真を閉じ込めることができていると感じました。最終的には、このアクリルのケースも一体でひとつの作品になったと思えた。昨年の秋に撮影してから展示まで、約1年間くらい作業しましたが、撮ることだけでなく、伝えることについてより考えるようになりました。
―上田さんにとって撮影と暗室作業というのは以前から重要だったと思いますが、それらと同じくらいの比重になったと。
そうですね。写真の展示の方法はいろいろありますが、それらを機械的に選ぶのではなくて、それが持つ意味を含めて伝わるようにするにはどうしたらいいのか、相当考えないといけない。あたりまえのことなのかもしれないですが、まさにそういうことを1年やっていたのかなと思います。

―今回の展示会場が、写真ギャラリーではなくて現代アートギャラリーであるのも納得しました。
こちらの意図がほとんど誤解なく伝わる場所だと思いますし、このギャラリーで展示ができたことは、僕にとっても作品にとっても、とても嬉しいことでした。
| タイトル | |
|---|---|
| 会期 | 2017年12月2日(土)〜2018年1月13日(土) |
| 会場 | 小山登美夫ギャラリー(東京都) |
| 時間 | 11:00~19:00 |
| 休廊日 | 日月曜・祝日、12月29日(金)〜1月8日(月) |
| URL | http://tomiokoyamagallery.com/exhibitions/yoshihikoueda2017/ |
上田義彦|Yoshihiko Ueda
1957年兵庫県生まれ。写真家福田匡伸氏、有田泰而氏に師事した後、1982年独立。エディトリアルワークをきっかけに、広告写真やコマーシャルフィルムなどを手がけ、東京ADC賞最高賞、ニューヨークADC賞等、国内外の代表的な国際デザイン賞を多数受賞。作家活動は独立当初から継続し、2014年に日本写真協会 作家賞を受賞。2017年までに33冊の写真集を刊行。2011年よりGallery 916を主宰し、写真展企画、展示、写真集の出版をトータルでプロデュースしているます。現在多摩美術大学グラフィックデザイン学科教授。
2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。















