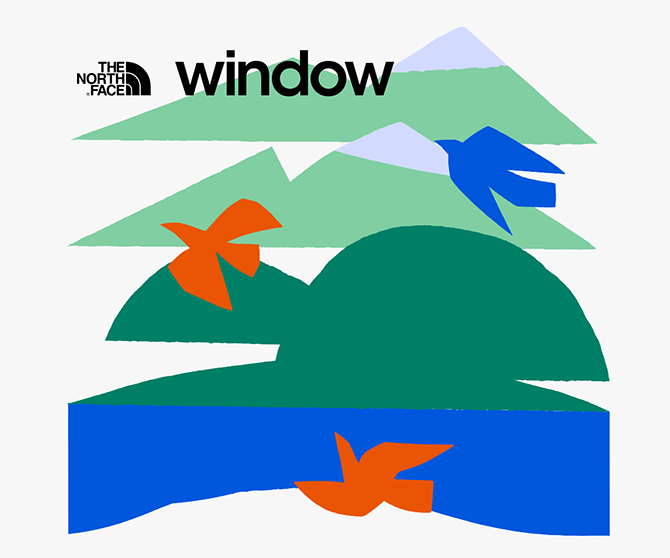人も企業も、“SDGs”を避けては通れない現代。ものをつくるアーティストも同様だ。アートとSDGsはいまどう響き合っているのか?オウンドメディア「THE NORTH FACE Window」でSDGsを発信するアウトドアブランド「ザ・ノース・フェイス(THE NORTH FACE)」と共に、環境や多様性を感じさせる作品を生み出す作家のクリエイティヴィティを考える。
最終回は、山を描く日本画家・春原直人さん。長野で生まれ、現在は山形を拠点に活動する彼は、山行という運動を通じて自らの身体感覚に刻まれた山の存在を大きなキャンバスに再現した作品で注目を集める。この3月にはザ・ノース・フェイスとコラボレーションし、展示が原宿の店舗で4月5日まで開催中だ。「絵を描くように山に登り、山に登るように絵を描く」と、自身の制作活動を表現する25歳の画家に、山を描く理由やコラボレーションについて聞いた。
撮影=竹澤航基
文=龍見ハナ
―春原さんの作品を一見するだけではそれが本当に山であるのか定かではないけれど、なぜか山であることを確信させる迫力があります。山を捉えたいという気迫とも呼べるかもしれませんが、それは長野出身ということも関係していますか?
大学から山形で、卒業後の今も山形を拠点にしていますが、実はここにくるまで山に興味はなく、自ら山登りに行くこともなかったんです。
それが在学中に出された「それぞれの山形」という課題を通じて初めて、長野の山と山形の山は違うということに気づき、興味を持ちました。そこから山に登りはじめ、山をテーマに絵を描くようになりました。
―長野の山と山形の山のどんな違いが、春原さんを魅了したのでしょう?
僕が住んでいた長野の地域は晴天率が高く、カラッと晴れているんです。そんな澄み渡った空気の中、どこにいても遠くにギザギザした山の稜線が見えるというような環境で育ちました。
一方、山形は曇が多くいつも霧がかっていて、雲に隠れて山頂が見えないんです。頂きが見えないからこそ想像が掻き立てられて、かえって山が大きく見えたりして。そうして初めて、見慣れていたはずの山という存在が相対化されたんです。
この経験を機に山にも登るようになると、同じ山でも登る度に異なる経験が待っていて、新しい発見があります。 登れば登るほど遠い存在のようにも感じられて、別世界のようだけれど繋がってもいる……。そういう山との不思議な距離感が絵を描く動機に繋がっている気がしています。
―絵を描くように山に登り、山に登るように絵を描く、というコンセプトについて教えてください。山に登ることも絵を描くことも「運動」であり、経験の記述という点でも共通していますね。
僕は山を登るとき、頂上を目指しているわけではないんです。それよりも過程を重視しています。たとえば、山の麓と中腹、頂上近くでは見える景色も違いますよね。まるで写真を撮るように、その一瞬一瞬で見える情景を切り取って自分の中に経験として落とし込んでいく。それが「絵を描くように山に登る」という表現に繋がっています。
一方、僕はキャンバスに岩絵の具を乗せて描きはじめることが多いのですが、描いているうちに、絵の具のシミや重なりが岩肌に見える瞬間があります。つまり、山に登ったからこそ描ける線や筆のタッチ、色があるんですね。
そうした瞬間を手がかりにかたちを探っていくわけですが、それが山を登っているときの「頂上が見えそうで見えない」「山頂を探しているけれど、もうちょっと登らないと見えないだろうな」という感覚と重なるんです。
―「もうちょっと登らないと見えない」という感覚は、春原さんの作品を観るときの感覚にもどこか似ている気がします。山なのかな、何なのかな、と、近づいたり離れたりして動きながら作品を捉えようとする感じです。
乱暴な言い方をすると、僕の作品は、砂(岩絵の具)の塊が和紙にくっついているだけのもの。それが誰かの目を通じて、何かの事象や風景に見えることに価値があると思っているんです。
だから山に見えなくてもいいし、僕の絵を見た経験をもとに、その人の世界を見るフィルターみたいなものがアップデートされたら嬉しい。見え方が変わる、違う景色が見えてくる、という現象が僕の作品にとって大切なんです。
世界は歩いてみないとわからない
―世界を見るフィルターという点では、環境問題という地球規模の社会課題に対するメッセージを、つい春原さんの制作活動に見出したくなってしまうのですが、ご自身はそうした意図をお持ちですか?

登る度に新しい発見があるというのは、すなわち山も少しずつ変化していると思うんです。山の美しい風景を見る度に、これがいつまでも変わらないで欲しいと願うとともに、自分の生き方がその変化に何らかの影響を与えているかもしれない、という意識はあります。
また、僕の作品はモノクロが多いのですが、それは解釈の余地を広げたいからなんです。いろんな見方をしてほしいんですね。本来、山にはいろんな側面や色があります。でも、それをあえてモノクロという限定的なメッセージにしぼり込むことで、むしろより多くの要素を包含できるんじゃないかという期待があるんです。
と考えると、そこには環境問題に対するメッセージを含めることもできると思います。
―最近では、ご自身が山を歩かれた際のGPSデータをもとに作品制作するなど、新しい試みも行っていますね。新しい試みという意味では、今アート界ではNFTアートが一大ブームを引き起こしていますが、そういう時代に生きる20代のアーティストとして、ご自分の作品の存在意義をどう捉えていますか?
僕はゲームも大好きだし、ヴァーチャルなものへの抵抗があるわけでは全くありません。でも最近思ったのは、結局、この世界は自分で実際に歩いてみないとわからないということです。僕の場合は山ですが、実際に動いてみないと景色だって見えてこない。そう考えると、結局、人間は歩くしかないんだなって。そういう主張をしたくて作品を制作しているところはあります。
―ザ・ノース・フェイスとのコラボでは、春原さんの作品がプロダクトにプリントされています。つまりは、作品を身に着けて、人が歩いたり動いたりするわけですね。
絵画って、音楽など気軽に共有できるメディアに比べて、全然身軽じゃないんです。だからなのか、身軽なものへの憧れがあって。僕の作品がプロダクトにプリントされ、別の新しいものになっていろんな人に行き渡ると考えると、すごくワクワクします。どんな反応が待っているのか、とても興味深いですね。

春原直人 Naoto Sunohara
1996年長野生まれ。2020年東北芸術工科大学大学院修士課程芸術文化専攻日本画領域修了。主に山をテーマとした作品を制作しており、作家自身が実際に登攀することで蓄積される身体的な動きを筆致に昇華し、抽象的な風景として表現する。炭や岩絵具といった伝統的な日本画材を用いながらも、外延性を持った平面作品の新たな可能性を模索。これまでの展示に、アートフロントギャラリー「Fragments from Scaling Mountain」や上野の森美術館「VOCA展」、 銀座蔦屋書店「エマージング・アーティスト展」など。