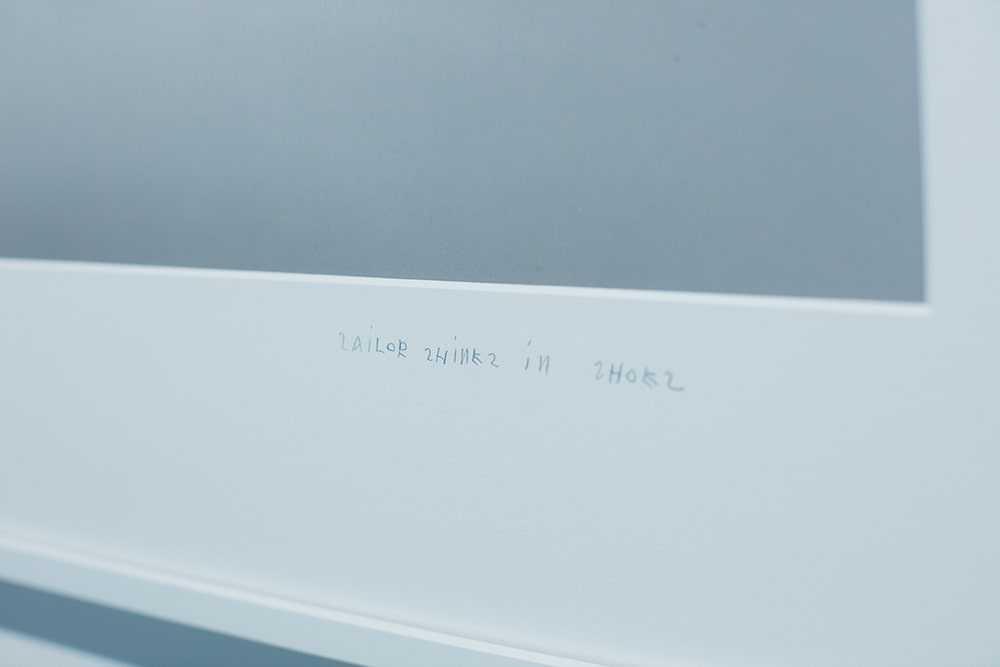現在、渋谷PARCOで開催中のココ・カピタンの個展「NAÏVY」。2020年にロンドン、2021年にアムステルダムを巡回した個展を踏襲した本展では、シリーズ完結版となる50点の写真作品とカピタン自身が制作したファウンドオブジェクトなどを公開している。カピタンは写真、詩、絵画、インスタレーションなど、多岐にわたる手法で表現を行い、コマーシャルとファインアートの分野を横断している。日本初個展に合わせて来日中のカピタンに話を聞き、その柔軟な姿勢と魅力を探る。
インタヴュー・文=原知慶
写真=髙橋直也
―日本初個展となる本展では、自身が手焼きされたプリント作品を中心に展示していますね。
今回は暗室に入って制作したCプリントをメインに展示しています。暗室にいるという経験は、いまではそれ自体とても貴重なことですが、自分について色々と考える楽しい時間にもなりました。
―手書きのステートメントからは「存在」に対する洞察が伺えました。周囲の存在との結びつきに強く思いを馳せることは、同時に自身の存在について確かめることでもあると思います。被写体のディティールに丁寧な視線を注いで撮影された写真からも、ステートメントに書かれた想いを深く感じました。
人と言葉を交わしコミュニケーションを取ることは、必ずしも簡単なことではありません。逆に私が扱っているテキストや写真という手法は、他者とつながることを助けてくれる表現であるともいえます。
―テキスト、写真、ファウンドオブジェクトなど、さまざまなメディアを複合的に扱った作品を展開していますが、写真を撮る際にはどのような意識で被写体と接しているのですか?
私にとって写真を撮るということは日記的な表現です。今回展示している作品がフレームの中で写真と共にテキストが入っているのも、日記的な側面を含んでいるからでしょう。撮影を行うときは基本的には準備をせず、自然な流れの中で起きたことを撮影するカジュアルな方法を用いています。自分自身の経験した時間から自然に派生して撮られたものが一番リアルであると思いますし、写真であることの意味も感じます。

―写真を撮るのが日記的な行為だとおっしゃいましたが、写真を撮り始めるきっかけとなったのは文章を書くように自然な仕草からなのでしょうか?
写真に触れるようになったのは本当に偶然というか、ほぼマジックのように感じています。生まれた家にはカメラが一台あっただけでしたが、1990年代生まれなのもあり、家族で写真を撮って現像に出す文化が自然に身についていました。いまでも現像をするときには、このプロセスが一体どういうもので、どうやって自分の記憶が収まった箱から実際に写真ができるのかをずっと想像しています。それくらい私にとってカメラは不思議な魔法の箱のようでした。自然と写真に取り憑かれるように撮影に夢中になっていましたが、家族はまさか私が写真を撮ることを職業にするとは思ってもいなかったでしょう。その分、家族からのプレッシャーがない中で育ったことも写真家としてよかったのでは思います。
―「Naïvy」 はセーラー服への関心を据えながらイメージが展開されていくシリーズですが、なぜ「セーラー服」というアイテムに惹かれたのでしょうか? 日本では学生服としてセーラー服に馴染みがあり、軍服という本来の意味から逸脱して受け入れられています。そういう意味で日本のオーディエンスがあなたの作品に、あなたの意図とは異なる意味を重ね合わせてくれることを期待しています。
そもそも私は海に対してとても興味があります。生まれ育ったスペインの街やこれまで住んだ場所にも海が深く関係してきました。制服は視覚的な表象として組織や団体、共同体に属していることを意味しますが、今回扱ったセーラー服というモチーフは、海というコミュニティに属していることを表しています。展示もしている実際のセーラー服に刺繍をした作品は、刺繍によって個性そのものを象徴しています。個性を尊重することとコミュニティや社会、団体に属することが共存できることを今回は表現したかったんです。
―日本でも学生服を加工したり刺繍を入れる文化がありますが、それらは若者がアイデンティを確立するための術であるともいえます。連帯感、記号性を伴いながら自分自身のものとしてカスタムすることに、馴染みと共感を覚えました。
私も日本の制服文化には関心があって以前調べたこともありました。ヨーロッパでは日本ほど制服を自分のものとしてカスタムする文化は薄いので、日本で学生たちが海軍の服を着ているという現象はとても興味深いです。いつかカメラで収めてみたいと思っています。
―こうしてあなたの写真を前にすると、表情が見えないポートレイトや体の一部分にフォーカスした写真など、フレーミングの面白さに目を引かれます。
例えば、ポートレイト作品でモデルがこちら側を向いていると、その目を見つめてしまってどうしてもほかのものが見えてこない。目線を外すことでもっと全体的に見えるようになります。全体で見せたいのか、ディティールで見せたいのかを選択することで、意図的に被写体が与える印象の違いを生んでいます。
―それぞれの意図が空間全体にも顕著に現れていることに、作家としての人柄を感じます。自身で現像されたプリントからも、色に対する並外れた意識の高さと誠実さが感じられました。
私は色に対するこだわりが強い方だと思います。ほかのカメラマンと比べてもここまで強く色へのこだわりを持っている人はいないかもしれません。暗室に入ってプリントすることに関心がある理由はまさに、色調をコントロールすることですべてのディティールを集約できると思えるからです。
いまだに私にとってプリント作業とはとても魅力的で、何か不思議な魔法をかけている行為のようです。プリントするまでどのような像が表れるかわからない時間があることがすごく大事で、毎回出来上がるたびに少しの驚きを与えてくれます。自分がデジタルプロセスを嫌っているのは、撮ってからイメージを見るまでの時間が全て省かれるからです。手焼きというプロセスの中で、理想とするイメージに手間と技術をかけられるからこそ、撮影自体にも大きな魅力を感じます。
―プリントを見ていると澄み渡った青色がとても印象的です。
今回の作品のコンセプトの中にも、ブルーを狙って出したところがありました。人生にはわからないことが色々ありますが、私にとってブルーという色は言葉にならないほど好きで心地がよいと感じられる色です。自分が今回長時間暗室に入って取り組んでいたのは、このパーフェクトなブルーを求めていたからでもありました。
―この展示に合わせて写真集も制作されているそうですね。
そうですね。今回の写真集はスクエアサイズの装丁で作っています。四角い画面をフレームに見立てて、実際の写真作品に近づけるようなアイデアを盛り込んでいます。展示されている作品のように、写真の余白とテキストを楽しんでもらえるように仕上げる予定です。
―最後に、これからの展望を聞かせてください。
次はもう少し絵画に比重を置いた制作をしたいと思っています。絵画を制作する中でも写真を用いることが多いので、日常的に写真を撮ることには変わりはありません。これから先の写真展のアイデアもいくつか思い浮かんでいるのですが、コンセプトに対して真剣に向き合う時間ができてから、また考えたいと思っています。

| タイトル | 「NAÏVY」 |
|---|---|
| 会期 | 2022年4月15日(金)~5月9日(月) |
| 会場 | PARCO MUSEUM TOKYO(東京都) |
| 時間 | 11:00~20:00(入場は閉場時間の30分前まで/最終日は18:00閉場) |
| 入場料 | 800円*未就学児無料 |
| URL |
ココ・カピタン|Coco Capitán
1992年、スペイン生まれ。ロンドンとマヨルカ島を拠点に活動している。ロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートで写真領域の修士課程を取得後、作家として活動を開始。コマーシャルフォトグラフィーとファインアートの分野を横断しながら写真、テキスト、絵画、インスタレーションなどさまざまな手法で表現を行なっている。GUCCI、A.P.C.、DIOR、COS、BENETTON、NIKEなどのブランドとのクライアントワークを行う。2022年、Louis Vuittonのフォトブックシリーズ「FASHION EYE」から写真集『TRAINS SIBERIAN』を刊行。また、ケンブリッジ大学、ロイヤル・カレッジ・オブ・アート、オックスフォード大学、マンチェスター芸術学校、などのゲストスピーカーとしても活動する。