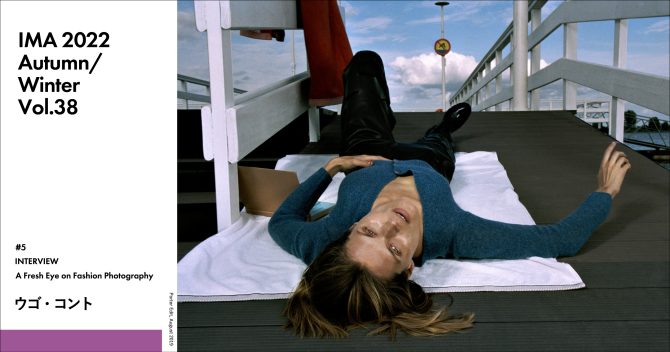2024年9月に千葉市美術館で個展『Nerhol 水平線を捲る』展を成功させた田中義久と飯田竜太によるアーティスト デュオ・Nerhol。グラフィックデザイナーである田中は、紙にも並々ならぬこだわりを持ち、10000種類の紙を手触りで判別できるほどだという。今回はそんな田中をも魅了した和紙を制作するファクトリーを訪ねて徳島へ向かった。
『IMA Vol.42』から転載。
テキスト=IMA編集部
写真=高木康之
折る、畳む、切る、破る、捲る、剥ぐなど紙にまつわるアクションに加えて、通常はあまりされない「彫る」という行為を通して、ネルホルは紙の新しい可能性を私たちに教えてくれた。そのルーツを辿ると、「子どもの頃によく一人で山に登って風景画を描いていたんですが、その時のスケッチブックの紙の質感が今でも記憶に残っている」という田中義久。すでに幼少期から紙への関心を持っていたが、やがてグラフィックデザイナーになってからは、その興味が増大していく。
対談でも「まるで盲牌のように手で触るだけで何の紙かを当てていた」と飯田が証言したが、「紙の表面には質感があって、練り込まれた内容によって持った時の重さや匂い、しなやかさも違う。そういった繊細な機微を理解して、日本中にある紙を知りたかったから」と、絶えず貪欲に紙と向き合ってきた。その後も、デザインの仕事ではさまざまな紙を扱って、数えきれない書籍や印刷物を制作してきた。特に紙と土地の深い関係性を知ることになったのが、自費出版していた『疾駆』という本のシリーズだ。毎号テーマとなる地域を選び、その土地の文化を捉えるコンテンツに合わせて、装丁や本文用紙にその土地の紙を使うことを実践しながら、水に恵まれた日本は紙が生活に根ざしていて、その種類も桁外れに多い国であることを実感する。

そこまで魅了される日本の紙の魅力を問うと「無駄がないこと。自然と人との関係がとても良いバランスで存在していて、究極のサスティナブルが1000年以上前に出来上がっていたんです。和紙は雑草が原料ですから、その地域に生えていた一年草を刈り取って、繊維状にほぐし平らに漉いただけ。紙漉きに必要な水は川から引く。つまり自ずとその土地と強く結びついているんです。昔は農家さんがやっていたぐらいですから」と語るように、この数年、田中はヴァナキュラーな紙のルーツを掘り起こすことに興味を寄せている。
過去には、紙の専門商社である竹尾との協業で、ユニークな紙の開発を行ってきたが、中でも大きな成果となったのは、土地の土を練り込んだ「土紙」を作ったことだ。ここから石を練り込んだ紙の彫刻なども生まれるが、田中の関心は、紙を扱うことから見たことのない紙を新たに創作することに向いていく。「デザインする上での紙は、紙媒体としての機能を持っています。何か伝えなければならない事柄を媒介する支持体のような役割を取り除くことはできません。ネルホルとして扱う際には、紙は作品を制作するための素材であり、その素材は作品に対するコンセプトに付随します」

阿波和紙との出会い
その過程で出会ったのが、徳島県にあるアワガミファクトリーだ。徳島県の山間、吉野川市で 1300年という長い歴史を持つ阿波和紙の製法を継承しつつ、和紙の新たな可能性の研究・開発を行っている、いわば和紙のラボ。手漉抄紙(てすきしょうし)、機械抄紙(きかいしょうし)から染紙、和紙の加工まで、和紙にまつわる製造の一方で、国内外からのアーティストを受け入れて作品制作のサポートや阿波和紙の技法を教える手漉きのワークショップなども積極的に展開してきた。
既製の紙を重ねて彫って作品を制作してきたネルホルだが、次第に紙そのものを作品化することにも展開していく中で、田中はこれまでもアワガミファクトリーの工房をたびたび訪れて、新しい紙をともに開発してきた。「阿波和紙の起源は古いんです。900年頃に朝鮮半島から渡来した忌部氏という宮祭祀を担っていた人たちが、麻や楮(こうぞ)を植えて紙や布を作り始めたのがはじまりです。江戸時代には藍染めの和紙が全国に広まり、この土地は麻、楮、そして藍の産地でもあったので、明治・大正には農閑期の副業から専業となった和紙の工房が200軒もあったんです」
こう教えてくれたアワガミファクトリーの藤森洋一氏は、たった一軒だけ残った和紙の工房を父から継いで40年余りにわたって、多彩な素材で和紙の可能性を拡げながら、この場所を今では国内外のアーティストに知られる和紙の聖地に育てた人物だ。

和紙といえば薄くて丈夫であることがその特徴であると言われてきたが、藤森氏はその反対を行く、分厚くて巨大な和紙を作ることを始めた。それがアーティストたちを魅了する。「アメリカの版画家の巨匠ケネス・タイラーがきっかけでアートが和紙と近づいたんです。1992年にうちに来て、しばらく滞在制作をしました」
戦後のアメリカ現代美術における版画芸術をリードしてきた版画工房タイラー・グラフィックスを率いるタイラーが知ることで、アワガミファクトリーの名は海外の現代アーティストの間でも浸透していく。これまでフランク・ステラ、リチャード・セラ、サム・フランシスといった綺羅星のごとき巨匠たちが阿波和紙で作品制作してきたと言う。

田中もこれまでさまざまな和紙の制作を依頼してきたが、今回の千葉市美術館でのネルホルの展示のためにも、千葉市の蓮の葉を練り込んだ和紙を制作したばかり。アワガミファクトリーであっても経験のないほどの量だったというが、また一つ新しい紙が生まれ、その経験を通して互いの知見が拡大した。「今まで存在しなかった紙をたくさん作ることができました。アワガミさんはやったことのないことでも率先して協力してくださるので、これからもどんどん面白いものが生まれていくと思っています。和紙というと、どうしても伝統工芸といった言葉がまとわりついてしまい、新しく挑戦することよりも守ることに焦点がいきがちです。本当は伝統という言葉には更新する意味も含まれているのですが、アワガミさんにはそう言った意味で大変感謝しています」
障子、襖、壁紙など、長く和紙は日本人の暮らしに欠かせない素材であったが、生活の変化に伴い需要が減り、斜陽で一時期は消えかかった阿波和紙の伝統を繋ぎ、復興させ、さらには新しいフェーズに押し上げたアワガミファクトリーは、アーティストの発想を取り込むことでさらに進化してきた。

紙、そして麻へ
ネルホルの作品は、被写体が本来持っていた時間や空間や行為を彫ることで表出させてきたが、何もプリントされていない、彫られてもいない紙を展示するインスタレーションは、紙そのものにも時間や空間が積層しているということを物語っている。
「土地の特性を知ることは、自身の背景を知ることになると思います。例えば日本には全国的に黒ボク土という土壌が多く見られるのですが、通説では火山噴火により火山灰が積もるとされていました。しかし最新の研究結果では、縄文時代と弥生時代の途中くらいまで全国的な規模で人々が山焼き、野焼きを行っていた時期があって、火山由来粘土鉱物、火山非由来粘土鉱物などの鉱物と関係なく、長年の火入れによって土壌中で生まれた微粒が炭化した黒色物質を土壌中に留まらせたという話になっています。とすると、この黒ボクを作ったのは日本に住んでいた縄文人。先祖の暮らしの中で生まれた営みを土から捉え、それらを背景に紙作りをすることによって、作品を制作する上での振る舞いは大きく変わっていくと思います」
このように土地の記憶を紙へと写しとり、それを表出させる作品を生み出してきたネルホルだが、その活動は今、紙から麻へと拡張している。

今年5月に太宰府天満宮で開催された個展「Tenjin, Mume, Nusa」では、太宰府に何度か滞在制作し、太宰府の「天神」である菅原道真、道真が愛した「梅」、さらには紙の起源としての「麻(ぬさ)」をテーマに、太宰府の物語を掘り起こすことになる。麻は古くから、清浄で穢れを祓うものとして、神事においては祓串(はらえぐし)という細い木に細かく切った紙垂(しで)や苧麻(ちょま)をつけた神具や麻布を括り付けた罪を祓い除けするための神具などに使われ、欠かせないものとなっている。
こうした制作のプロセスで麻との関わりが深まり、千葉市美術館での新作にも、和紙の素材に麻を混ぜてから漉き、2,200メートルの和紙ロールを同じ大きさに切って積層させたものが登場した。積層させた紙の一番上の層には、ドローイングしたプランを元にした紙をグラインダーで削って、手で裂きながら、本体の和紙の積層からは分離させる。何もイメージのない中で、和紙が持っている記憶を彫り当てていくような行為を繰り返して、現れた像はまるで砂漠の表面を捉えたような、どこかの星の地表の写真のような体をなしている。グラインダーで削り割かれた断面からは麻の質感が現れ、紙だけでは出せない独特の風合いが表現される。紙から麻へ、麻から土へとつながる連鎖の中に潜む土地の個性と記憶は、これからネルホルの作品がより一層深まっていく予感がある。

この作品のように作品が麻まで拡張していることを問うと、「拡張したというよりは」と前置きして、田中はこう語ってくれた。
「和紙を遡っていくと麻という素材に向き合わざるを得なくなったという感じです。和紙の素材は現在、楮(こうぞ)、三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)が主要なものですが、それらは大陸からの技術が混ざり合って生まれています。しかし1000年単位で遡ると、日本と麻という素材の関係は切っても切り離せません。それは神社仏閣だけではなく、日常生活においてとても身近な素材であり、多くの日用品としても使われてきました。紙は現代の日本の生活において必需品であり、それらを紐解く上で麻は重要な意味を持っていると思います」
縄文時代の出土品にも見られるように、麻の歴史は古いが、庶民の間では長い間、圧倒的に絹や綿より麻が衣服としても、紙としても生活の中で活用されてきた。日本は紙の文化と言われると同様に、麻の文化とも言い換えることができるのだが、麻もまた大陸から渡来した帰化植物だ。ネルホルがたびたびモチーフにしてきた帰化植物の、もっとも古いルーツとも言える。
田中は紙の現在と未来をこう考えている。
「情報を伝達するために紙が使われた時代から解放されて、紙自体の本来の特性を活かす時代に変わったと考えています。それは紙という素材の価値に対し、今の時代に最も適したあり方を再考できる大きな転機になると思っています」
デジタル化、AI化が加速する社会の中で、物質感を伴うものの役割はさまざまに変化しているが、紙もまた然り。その価値は時代の中でこれからも変容していくだろう。
最後に、ネルホルと紙の関係を問うと、こんな答えが返ってきた。
「私と飯田は紙によって出会ったと言えます。ですので、紙を素材にすることからは離れることはないだろうと思います」
ネルホル | Nerhol
田中義久と飯田竜太により2007年に結成されたアーティストデュオ。紙と平面的構成によるグラフィックデザインを行う田中と、紙や文字を素材とする彫刻家の飯田からなる。田中は、1980年静岡県生まれ。武蔵野美術大学造形学部空間演出デザイン学科を卒業後、慶應義塾大学大学院政策・ メディア研究科在学中。飯田は、1981年静岡県生まれ。日本大学芸術学 部美術学科彫刻コースを卒業、東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修了。写真と彫刻を往還する独自の表現を通じ、現代的な視点から人間社会と自然環境、時間と空間に深く関わる多層的な探究を続けている。主な個展に、「 Tenjin,Mume,Nusa」(太宰府天満宮宝物殿、福岡、2024年)「Beyond the Way」(レオノーラ・キャリントン美術館、メキシコ、2024年)、「Affect」(第一生命ギャラリー /M5 GALLERY、東京、2023年)「Interview, Portrait, House and Room」(Youngeun Museum of Contemporary Art、韓国、2017年) 、「Promenade」(金沢21世紀美術館、石川、2016年)など 。
AWAGAMI FACTORY | アワガミファクトリー
和紙の展示のほか、ワークショップや制作の相談も受け付けている。
徳島県吉野川市山川町川東 141 番地
0883-42-6120
https://www.awagami.or.jp/