前作『日常らしさ』から、約12年ぶりに新作写真集『1/1』を刊行した安村崇。本作では北海道から九州まで、1980年代以降に建設された地方の公共施設を被写体としながらも、イメージは極端なまでに抽象化されている。牛腸茂雄の『SELF AND OTHERS』に「背景」を強く意識したという作家にとって、「背景をなくす」とは一体どのような試みだったのか。『1/1』というタイトルの裏側や写真家としての姿勢に、『日常らしさ』から安村作品を見続けてきた、倉石信乃が向き合った。
構成・文=IMA
写真=高橋マナミ
倉石信乃(以下、倉石):今作『1/1』は何年間くらいかけて撮ってこられたんですか?
安村崇(以下、安村):2008年から8年間、継続して撮影してきました。はじめの頃は特に意識していませんでしたが、だんだんと地方の公共施設や港などを巡りながら制作するようになりました。床や壁が作る構成に興味があって撮影しているように見えるかもしれませんが、僕自身はそういう意識はあまりなくて、あくまで背景になりそうなものを、できるだけ作らないようにしようと。
倉石:背景をなくしたらどうなるかという発想がまずあって、それの上で色々撮影してみたら結果的に地方の公共施設が一番適しているとなったわけですね。あらかじめ調べてから撮影に行ったのですか?
安村:例えば撮影で熊本に行く場合は、熊本県の県別地図を見て、行けそうなところには全部行くつもりで出かけます。事前に得られる情報は限られていますから、特に計画は立てないんです。
倉石:これを見ると、色面によって構成されている抽象絵画を連想するのですが、絵画に対する関心は持っていますか?
安村:色面への関心はありますが、絵画が直接作品制作に関わるようなことはあまりないですね。でも写真の背景と絵画の背景を比べて考えたとき、絵画の背景は絶対に筆を走らせなければ描けないけれど、写真の場合は作家自身が意識していなくてもカメラが写してしまう。そこは大きく違うと思っています。
倉石:いろんな夾雑物が入っている現実の風景から、ある距離と角度でフレーミングをすると、こういう複雑だけど単純な色面と場所ができるのだと思いますが、どのようにフレーミングしていくのでしょうか?
安村:まずは色や表面の質感に興味が向かいます。それをカメラのファインダーで見ながら、背景になりそうなものをなくしていく。ひたすらそれですね(笑)。そうすると自ずとフレーミングが決まっていき、形が生まれてくる。背景になるものを排除していくことで、想像もつかなかった像がファインダーに現れるという感覚です。

『1/1』(2017年、Osiris)より
倉石:一見フラットだとしても、実はフラットな面なんて存在しなくて、写真はその微妙な凹凸を正確に拾うことができます。そういうモノとしての様相の一方で、「公共空間」や「地方」といった記号や意味が重ね合わせられています。どのようにしてそれらの場所に行き着いたのでしょうか?
安村:モノの表面の質感は常に重要ですね。この撮影をしばらくして気付いたのは、県の人口がおよそ200万人以下のところばかりを撮影場所に選んでいたことでした。そういう地域には大きな都市の公共施設にはない、無駄なようにも見える凡庸な空間の広がりがあり地方らしいゆとりを感じます。物理的にも引きがあって撮りやすいこともあり、各地でロケーションを探しました。撮影中は意識してませんでしたが、被写体となっているのは80年代以降に建設された建造物も多く、つまり歴史の厚みのない構造物の表面の色彩に興味を惹かれたのかもしれません。
倉石:色とかたちと素材を、普通はこのように切り取らないですよね。しかし安村さんの写真から、自然より人工物に囲まれている、現代人の生活環境を知ることができる面もあります。
安村:そういう見方もあるんですね。いまのお話を聞いていると、確かにこれらの場所は市役所など街の中心からの距離などの立地条件によるのか、近隣の街並みがどこもよく似ていることを思い出します。
倉石:例えばここでは植物が、たとえ生きた自然物にせよほとんど人工化されたものとして写っている。人工物が自然を圧倒しているいまの現代社会に対する見定めが一貫して感じられます。単に元気のない今日の地方都市を引いてルポルタージュするよりも、文明の現在地がより明らかにされているんじゃないか。

『1/1』(2017年、Osiris)より
安村:面白いですね。撮影中は意図していなくてもそういうところにつながるとは。
倉石:だからこの写真集が重要だと思ったのは、物質性と記号性の両方が厳密に重ね描きされているからです。具体的なモノそれ自体の露わになることと、地方の建築的な環境が醸し出す人工的なものの優位性、そのふたつがあることで複雑な意味や批評の作動につながっていく。そういう視点は初期から安村さんの世界にあります。この「1/1」というタイトルも面白いですね。写真は自由にサイズを変えられるので、等倍という考え方は反写真的なところがある。ただ等倍に気づくことで逆に写真の条件を明らかにすることもできる。
安村:タイトルについていうと、僕はファインダーに映っているものと、カメラの前の現実を見比べたとき、どうしてもその現実にファインダーに映る像の嘘っぽさを同時にみてしまう。そんな中で「1/1」という言葉が浮かんできたのです。
倉石:嘘というのは?
安村:ファインダーに見える背景をなくした像が想像を超えていて嘘っぽい。それを見たがために現実にもそれが反映してしまう。「1/1」という言葉は、スケールが同じであることを表してはいますが、その前提として、これは実物ではないですよと伝える記号だとも思うんです。
倉石:それは複雑な思考ですね。つまりピントグラスに映ったこの嘘の方が、現実を写像して、それが等倍になるということだよね。
安村:三脚で固定した4×5カメラを黒い布で覆って、明るいピントグラスを使っているから、ファインダーがすごくよく見えるんです。まるで写真を見ながら写真を撮っているような感覚があって。背景をなくすという考え方も、ファインダーの視認性の良さが大きく影響していると思います。

倉石:この写真の中で奥行き感が消されているのは、背景をなくしていることに関係があると思いますが、浅い奥行きがあるともいい換えることができます。この浅い奥行きに惹かれているのでしょうか?
安村:惹かれているというよりむしろ、少し戸惑いがあります。写真を見ていると、視線が吸い込まれずに跳ね返されるような感じがあって。
倉石:教会の入り口などにあるバス・レリーフ(浅浮彫)を見ると、二次元と三次元の中間性が文字通り浮き彫りになってきます。だからそれは逆に立体や平面についての問題を考えさせられるのですが、同じようなことが安村さんの作品にはいえる思います。印画紙は二次元の平面ですが、写真の場合はそこに三次元的なイリュージョンを表現することができる。平面と立体についてはどのように考えていますか?
安村:三次元を二次元で見せることは写真にとっては当たり前で、ほとんど意識してこなかったんですね。ただこの奥行きの浅さが印画紙の表面との近さを感じさせるからか、写されたものを見ているのに、いつの間にか視線は印画紙の表面に戻ってきてしまう感じがあります。画面の中の奥行きと印画紙の表面、三次元と二次元を視線が往復することに戸惑いながらも面白さを感じています。

倉石:でもなぜ背景をなくす必要があったのでしょうか?
安村:たとえば牛腸茂雄さんの『SELF AND OTHERS』は、人物がほぼ画面の真ん中で、引き気味に撮影されている。それは背景を見せるためではないかとすらと感じます。自分は背景を気にするあまり、「日常らしさ」では対象に合う背景を求めて対象を動かすことから始まったのですが、今回はそれができない。背景が大切だと思うのは、まずモノの輪郭を伝えるから。そして、背景には“本当らしさ”が写っているように感じられ、手付かずの場所に見えるからです。
倉石:野性ですね。
安村:本当はすごく意識していても、主題があることによって背景は意識されずに撮影されたかのように見える。それは意識しようとしまいと写真は必ず何かを写し撮ってしまうという性質によるものではないでしょうか。主題への意識は感じられても、背景には意識が及んでいないように感じられる。「日常らしさ」の頃からずっとそういう思いがありました。「1/1」では背景は大事なのに、何もできない、建物は動かせませんから。ならばなくそうと(笑)。
倉石:そこが直感的だよね(笑)。モノによって埋め尽くすことによって、背景がいつ間にかなくなる。ただ実際には埋め尽くすというよりは、そういう場所を選んで切り出しているってことですよね。
安村:そうですね。
倉石:ということは、無意識をとにかくなくそうってことだともいえる。
安村:そうですね、それとともに、写真らしさに関する大事な部分がなくなったとき、その写真はどう見えるだろうかという興味がありました。
倉石:キュビスム以後の画家たちの一部は、自分が描くべき画面の四隅にコントロールできない曖昧な部分が出てきたとき、それをなくすことを考えた。絵画のフレームを楕円形にしてみたり、現実の事物をコラージュによって等倍で貼り付けることで、現実の場所(ここ)と現在のとき(いま)をイコールにしようとしました。もうひとつ、たとえば、ピート・モンドリアンが考えたのは、カンヴァスを45度回転させるということ。そうすることによって絵画の全部が図になる。面白い解決方法だけど、45度回転させると今度は展示空間の壁面が明確に背景になってしまう。モンドリアンの場合はそれによって世界とつながるという発想があったと思いますが、展示すると壁がまた背景になるということについて、安村さんはどう考えていますか?
安村:それは考えなかったですね。
倉石:背景によってニュアンスや情緒も生まれます。それ自体はどう機能しているかわからないけど、主題が置かれるためには不可欠な場所ですよね。

安村:そうですよね、ときには主題の性格にも影響を与えますね。でも背景がなくなると、主題だと思っていたものも主題ではなくなってしまい、全部が背景になってしまったともいえる。というのも、以前展示の際に120×150cmまでプリントを引き伸ばしたんですが、引き伸ばしたことで写真の何もなさが赤裸々になって、逆に全部背景になってしまったように見えたんです。
倉石:私は背景のことを考えるとき、いつもエドワード・ウェストンが思い浮かぶのですが、彼の代表作は静物が多いですし、背景がないと成り立たないんだよね。
安村:そうですよね。主題の輪郭を見せるための背景。
倉石:フォルムをしっかりと写すためには絶対に背景が必要になるけど、ウェストンの写真にも背景がないものがある。それは玉ねぎの断片など極端にクローズアップした写真と、砂漠のように単一のフォルムのみによってすべて構成されているような風景。ふたつの写真の共通点はオールオーバーということなのですが、背景をなくす手段としてオールオーバーに写すというやり方を安村さんは考えませんでしたか?
安村:写真集の中にも数点はありますが、ものに近づいていけば成立してしまうので、撮っているときにあまり驚きがないんです。この作品は作為的でわざとらしくみえますが、束になったものを見てみると、逆にすごく「写真の自然」があるように思います。それは写真の性質とも言えますが、人が介入してどうこうできるものではない、光学的、化学的な現象として生成された像ということです。意識的な作業の結果ではあれ、現象として現れる画像に自然を感じる。とても写真的というか。
倉石:アルフレッド・スティーグリッツの雲を撮った「Equivalent」(等価物)のシリーズはオールオーバーというか、少なくとも不定形と無対象を目指しています。彼は見る人に「雲を雲として見ないでほしい」と言うわけです。しかし清水穣さんが写真集『1/1』の解説の中で指摘されているように、実際のスティーグリッツ作品には自然と人工の二項対立を前提とする、「人間的な憧憬」が残されている。その分だけ雲も雲として残り、純粋な自然との「等価」な交歓もやや損なわれてしまう。また雲という具体的なモノを通じて対象のない世界を見てほしいということは、超越的な次元に属するし論証できません。安村さんの写真はそういう主観的な思考とは逆に、つまり対象がないように見える色面から対象が出現して、そこに驚きがある。スティーグリッツの超越とは逆ベクトルで見出される自然、人工物をも含んだ「自然」の側に立つ写真だといえるのではないでしょうか。
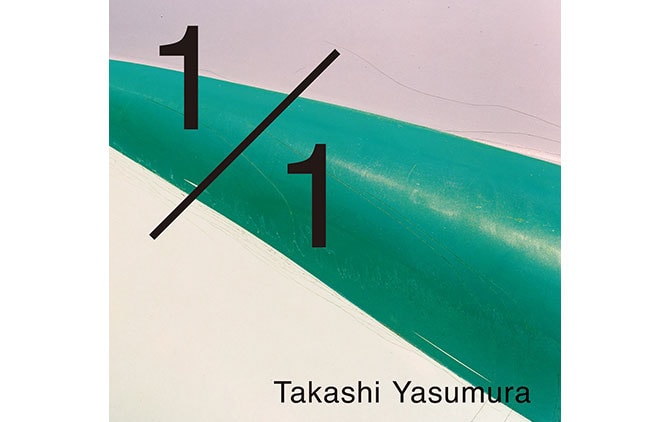
安村崇写真集『1/1』
| タイトル | |
|---|---|
| 出版社 | |
| 価格 | 9,000円+tax |
| 発行年 | 2017年 |
| 仕様 | ハードカバー/280mm×297mm/132ページ |
| URL |
安村崇|Takashi Yasumura
1972年、滋賀県生まれ。1995年日本大学芸術学部写真学科卒業。1999年に「第8回写真新世紀」年間グランプリ受賞。2005年に写真集『日常らしさ/Domestic Scandals』(Osiris)を発表。同年、パルコミュージアムで「安村崇写真展」を開催。2006年にはマドリードでグループ展「Photo Espana」参加。2017年に写真集『1/1』(Osiris)を刊行した。
倉石信乃|Shino Kuraishi
1963年生まれ。明治大学教授。1988〜2007年、横浜美術館学芸員としてマン・レイ展、ロバート・フランク展、中平卓馬展などを担当。1998年重森弘淹写真評論賞、2011年日本写真協会賞学芸賞を受賞。主な著書に『スナップショット—写真の輝き』(2010年)、『反写真論』(1999年)、『失楽園 風景表現の近代 1870-1945』(共著、2004年)などがある。『沖縄写真家シリーズ[琉球烈像]』(全9巻、2010-12年)を仲里効と監修。2001年、シアターカンパニーARICA創立に参加、コンセプト・テクストを担当。
2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。















