現在、ユカ・ツルノ・ギャラリーで開催中の個展「Doors」で、10代の頃から続けているドラムを使ったパフォーマンス作品を発表した山谷佑介。ギャラリーの中央に置かれたドラムセットにはカメラが複数台設置され、山谷が叩いた振動を感知するとシャッターが下り、山谷に向けられたカメラによって像が写される。写真はパソコンを経由して、会場の壁面に設置された旧型のモノクロプリンターから絶えず出力される。ギャラリー壁面の抽象的なモノクロプリントは、叩き続け表面が薄くなったドラムヘッドをフィルム代わりに大判の引き伸ばし機にセットし、暗室でプリントをしたものが飾られている。自らの身体的な行為をなぜ写真というフィールドで表現しようとしたのか、哲学や他ジャンルの視点で吉田幸司が解析する。
構成=IMA
写真=宇田川直寛
山谷佑介(以下、山谷):自分のキャリアはスナップ写真が始まりだったのですが、写真を始めたときは、シュルレアリスムとか夢の世界、無意識を表現するアートが好きだったので、最初はセットアップで撮ろうとしていました。でも長崎で東松照明さんに毎週写真を見てもらったときに、彼は間違ってシャッターを切ってしまった瞬間とかを面白いといって選ぶんです。そこから、スナップ写真は自分が世界をこう見たいから撮るんじゃなくて、世界に飛び込んでいったとき、障害がたくさんある中で、自分が知らなかった世界を撮れることが面白いことだと気づきました。それがきっかけで、写真を撮る時に「こう撮ろう」という決められたイメージを持ちたくないと思うようになりました。
今回の作品はシュルレアリスムのアート集団が用いていたオートマティスムという、自動記録装置に近いと思っているんですが、叩いた瞬間とシャッターが下りる間にズレが生じるし、旧式のモノクロプリンターにはノイズのような線が入る。そして見たことのない自分がそこに写っている。自分の変な顔を展示するのは本当は嫌ですが、写真家が自分をさらけ出す行為自体は、この時代にやる必要があると思っています。
吉田幸司(以下、吉田):「こう撮ろう」と意図して撮りたくなくなったとのことですが、今回、ドラムを叩くときも、写真を撮ることを意識していないんですか?
山谷:叩いている間は写真を撮ることはまったく考えないですね。だから自分でシャッターを押すタイミングから離れるために、この装置を用いたのは確かです。
吉田:普段、人間が何かを見ているときには、何を見ようか意図しなくても知覚風景が立ち現れていますよね。それに対して写真の場合は、写真家が意図的にカメラのシャッターを切って作品を制作する。ただ、今回の作品の場合、シャッターが自動で切られることによって撮影されているので、本人の意図が介在せず機械的な仕組みで撮られているのが特徴ということですね。

山谷佑介「Doors」インスタレーションビュー。会場内には京都でのパフォーマンス時に撮影された77枚の写真が飾られている。
山谷:僕のドラムパフォーマンスを見た友人が、フラッシュの一瞬の閃光によって、動いているのに止まっているように見えて、その強い光に晒された僕の姿が瞼の中に焼きついたと話していて。そういった経験自体がとても写真っぽいと言っていました。でも実際にはそれとは違うイメージがプリンターから出力される。そういった見る側の意識と世界とのズレも、この作品のノイズの一部だと感じています。
パフォーマンス自体、写真がとても苦手なことではあるんです。それ故、今回の場合は鑑賞者との共犯関係が成り立つ面白さもあるなと思って。写真を撮る行為自体がとてもポップになったいま、暗闇の中で強烈なフラッシュや視覚体験によって、写真が持っている暴力的な側面をみんなが感じてくれているのかもしれないと。
吉田:今回の作品以外では、写真家として写真を撮る立場、フラッシュを浴びせる立場にあると思うのですが、自分で意図して写真を撮るのではなく、写真を撮らされているっていう感覚はありますか?
山谷:シャッターを押す瞬間に対して、明確に立ち上がってくる何かはないのかもしれません。それはただの感覚とも違うし、言葉にはできない。昨年に発表した「Into the Light」では、深夜の住宅街で、人の家の中を覗きたいと思って赤外線カメラでフラッシュを焚いて撮っていたんですが、自分自身が見たいと思いながら撮っていたと同時に、何かから見られている視線をすごく感じたんです。深夜の静かな住宅街で、この世界に自分しかいないんじゃないかという感覚の隔たりが妙に居心地良く感じたのは、そういった相互の視線だったのかもしれません。スナップ写真から始めた僕としては、被写体にいつも見させられている側面があるのかもしれないということは、その時と今回の展示で考えたことです。
吉田:晩年のメルロ=ポンティや、イギリスの哲学者ホワイトヘッドがいっていることにも通じるところがあるように思いますが、例えば湿度の高く暑いときに森に入ると、そこに存在するものたちのざわつきが何か押しつけてくる感じがあったり、暗闇で何かの気配に気づいて、得体の知れない恐ろしさが迫ってくる感じがあったりするように、写真家も何かに迫られて写真を撮ってしまうことがあるんじゃないかと思います。撮る人だけのまなざしではなくて、昆虫や木に見られている感じとか、様々な存在者たちのパースペクティブというものがあるように思います。
山谷:何か向こうから来るものに対して撮るとか描くことは、受動的なことなんだろうなと改めて思いました。インスピレーションって”息を吹きかけられる”っていうラテン語の語源があって、すごく受動的な言葉なんですよね。
吉田:写真家が完全にコントロールするよりも、むしろ偶然が重なったり、被写体と写真家の関係がうまく一致したりしたときに、いい写真が撮れることはよくあると思います。しかも、写真家と被写体っていう二項関係ではなく、いろいろな要素が絡み合った多項関係の中でひとつの写真が成立することを考えると、写真を撮ることは一方向的な行為ではなくて、むしろいろいろな要素が入り混じる中で撮らされているっていう部分もあるんじゃないかと。その意味では受動的な方がシャッターチャンスが訪れる時があるのかなと思うのですが、山谷さんの場合はどうでしょうか?

山谷:それはあると思います。被写体を撮ろうとしたときに、僕のまなざしだけではなく、いろいろなものを通過している分「歪み」が出てくる。吉田さんは歪みについて本で書かれていましたが、僕はその歪みやノイズを撮りたい。
吉田:いろいろな要素が複雑に絡み合う中で、そのひとつの結節点として像が立ち上がる。そのときに歪みも含まれていく。今回プリンターから出力される時に、線が入ってしまったり、エラーが起きて顔が潰れてしまったりするのも一種の歪みですよね。
セルフポートレイトを撮っているように見えて、実際には、自分の身体的行為としてドラムを叩き、センサー、写真機、パソコン、プリンターなどを介して自分が写っている写真が出力されている。だからここで写っているのは実は自分自身ではなくて、「歪み」を含んだ一連の流れや全体の構造を写し取っているのかなと。その点では写真の工程をもっと細分化して、写真を撮るときの、意識以前のレベルで起きていることがどういうものなのか、写真を撮るということがどういうことなのかを、問いかけているのではないかと思います。

山谷佑介「Doors」インスタレーションビュー
山谷:その通りです。今回の写真に写った自分自身は肉体、肉片みたいなものでいいと思っているんです。被写体の立ち上がってくる個性やナラティブなストーリーはいらない。もっと機械から立ち上がる写真を今回は試みたいなと思って、それができたら面白いかもしれないと思いました。
吉田:肉片というのは、自分自身に余計な意味づけをせず、中立的なものとして考えるということですね。
山谷:ドラムを叩いている段階ではすごく生々しい動きをやっているけど、それがカメラを通して出力される時に削ぎ落とされていくような感覚です。
吉田:でも、意識的に作られた自分らしさではなく、衣を纏った自分よりも、より自分らしさが撮られているということはないですかね。
山谷:自分らしさなのかは分からないのですが、嘘と真実が同時に内在しているっていうのが写真の面白さでもある。そのままを持ってきたからといってリアリティではないし、写真のそういう面に興味があります。
吉田:プリントされた写真はリアルになってしまったモノだけれども、そこには、背景にあるようなシュールレアリスティックなものが表現として内包されている。今回の作品やパフォーマンスは、自分の意識を介在させずに、自分ではコントロールできないような環境や状況の要素がある中で、表層的なリアルの奥にあるもの、ポートレイト、自画像の深みや奥にあるものを顕現させているのかなと。

山谷:画家や写真家が昔から鏡を使ってセルフポートレイトを描いたりしていますが、その理由について考えたとき、対象を見ることと見られることが対立しているわけではなく、一緒のことだということに気付きました。だからすべてが監視されている現代社会の中で、人々の意識の中では、自分が見ていることと見られることが同一であるということが果たしてどこまで自覚的なのかと感じて、セルフポートレイトをいまやるべきだと感じたんです。
吉田:写真家が何を社会に訴えられるか、写真で撮った人、撮られた人以外の要素がどのように覆い隠されているか、その覆いを取って背景となっているものを表そうとしている作品であり、パフォーマンスだといえるでしょうか。
山谷:そうですね、覆い隠されているものを見たい、その裏に何があるかに強く興味があります。
吉田:人によっては今回のパフォーマンスを、これは写真家の仕事なのか写真作品なのかという人もいるのかもしれません。今回の作品は、カメラやセンサーなどの機械をこのドラムと接続させることによって、写真の概念やフレームを拡張しようとしているのかなとも感じました。
山谷:そうしたいと思っています。そのために過去にも赤外線を使ってみたりモノクロの古い手法を使ってみたりしてきました。今回、壁面に飾っている抽象的な作品(写真下)では、ドラムの跡=シャッターを可視化しました。結果として抽象的な作品にはなりましたが、肉体の痕跡は僕の中で重要なワードで、そういった些細な痕跡に焦点を当てたい。宇宙の爆発のようにも見えますし。いろいろなものに見えてより大きな世界を表現しているような感覚を覚えますね。
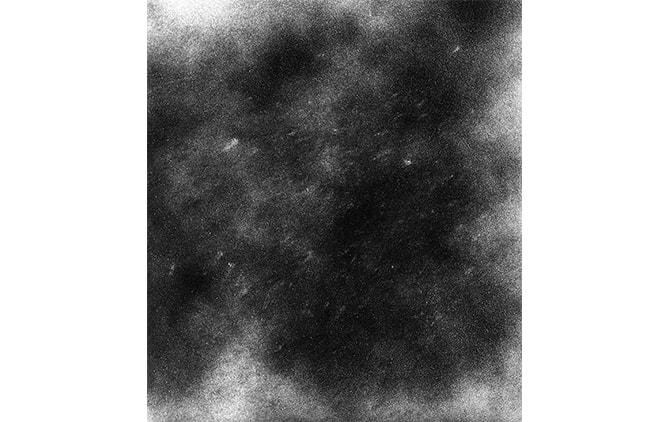
SD_0415, gelatin silver print, 2018
吉田:最後に今後の展望をお伺いしたいのですが、ドラムを叩いているときに、自分が撮られるだけじゃなくて同時にお客さんが撮られること、観客を撮ることは考えていないですか?
山谷:最初の京都では、たまたま写ってくる人たちも撮りたいなと思ったんですけどね、お客さんが少なくて写らなかったですね。
吉田:実際、もっとインタラクティブで観客自身がコミットできるような、参加型の作品へ展開できる可能性はあると思いました。一つのカメラだと身構えてしまいますが、たくさんカメラがあると、観客も、どこから、いつ撮られているかわからなくなる。そのような多項的なパースペクティブがあるような拡張もあるのかなと思います。
山谷:そういったいろいろな関係の中で、写真を通してこの時代に何を人々の感覚に訴えるべきなのか、そこを問いかけるものをこれからも作りたいなと思います。

| タイトル | |
|---|---|
| 会期 | 2018年6月9日(土)〜7月14日(土) |
| 会場 | ユカ・ツルノ・ギャラリー(東京都) |
| 時間 | 11:00〜18:00(金曜は11:00〜20:00) |
| 休廊日 | 日月曜 |
| イベント | パフォーマンス:2018年7月7日(土)15:00~ |
| URL |
山谷佑介|Yusuke Yamatani
1985年新潟県生まれ。立正大学文学部哲学科卒業後、外苑スタジオに勤務。その後、移住した長崎で出会った東松照明や無名の写真家との交流を通して写真を学ぶ。近年の展示に「Into the Light」(BOOKMARC、2017年)、「Lianzhou Foto 2016」(連州、中国)、「KYOTOGRAPHIE」(2015年、無名舎、京都)、「Yusuke Yamatani: Recent Works」(2015年、アリソン・ブラッドリー・プロジェクツ、ニューヨーク)、「Four From Japan」(2015年、コンデナスト、ニューヨーク)、「東京国際写真祭」(2015年)など。写真集・モノグラフに『Tsugi no yoru e(2nd ver.)』(ユカ・ツルノ・ギャラリー)、 『ground』(lemon books)、『RAMA LAMA DING DONG』(self published)、『Use Before』(a0)、『Into the Light』(T&M Projects)などがある。
吉田幸司|Koji Yoshida
博士(哲学)。上智大学哲学研究科博士後期課程を修了後、日本学術振興会特別研究員PD(東京大学)を経て、現在、哲学を事業内容としたクロス・フィロソフィーズ(株)代表取締役社長。上智大学客員研究員・非常勤講師などを兼任。共著書にBeyond Superlatives(Cambridge Scholars Publishing)、『理想―特集:ホワイトヘッド』(理想社)などがある。近年は、「写真×哲学」のワークショップを、ガーディアン・ガーデン、平間写真館TOKYO、PGI、東京工芸大学など各地で開催している。
2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。

















