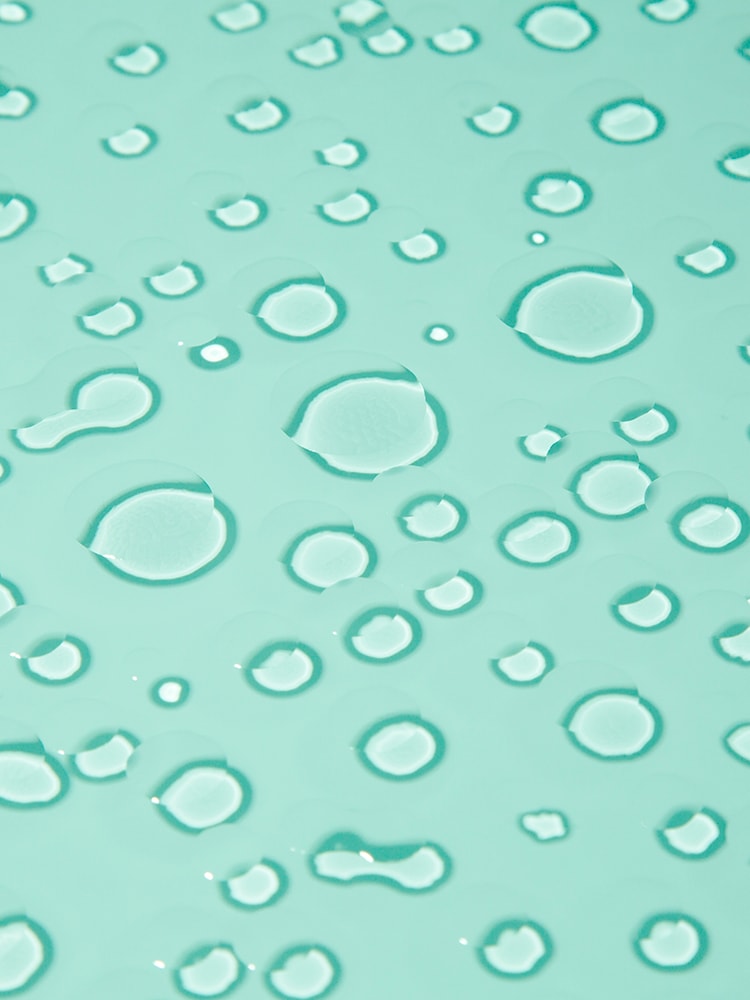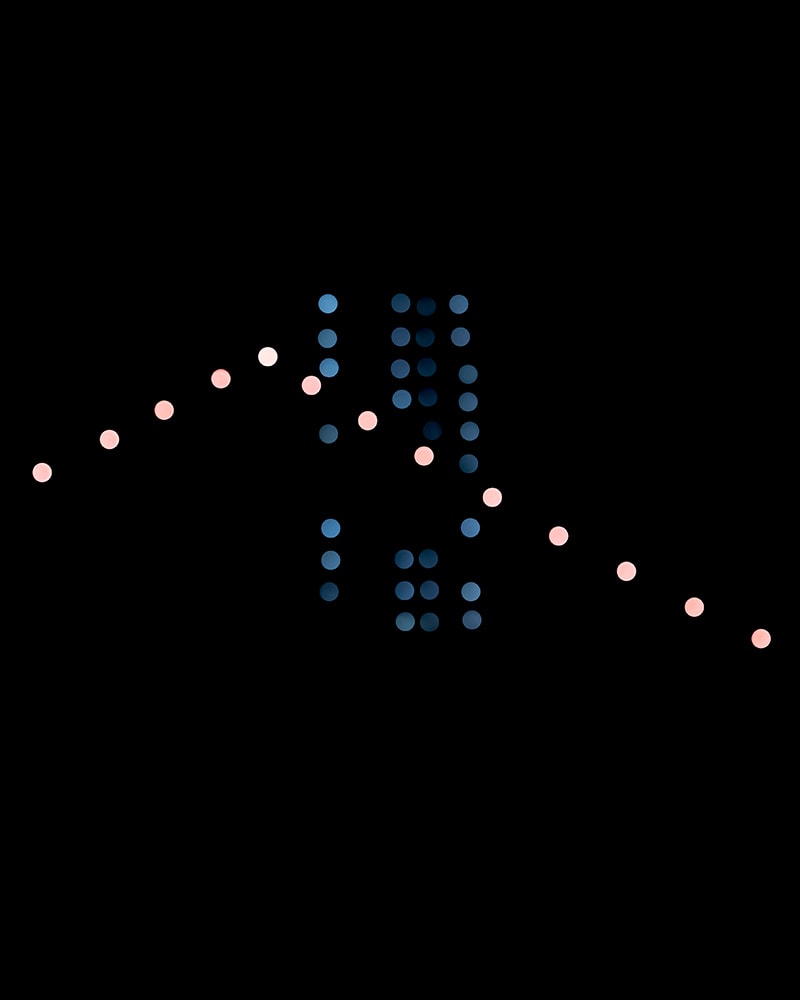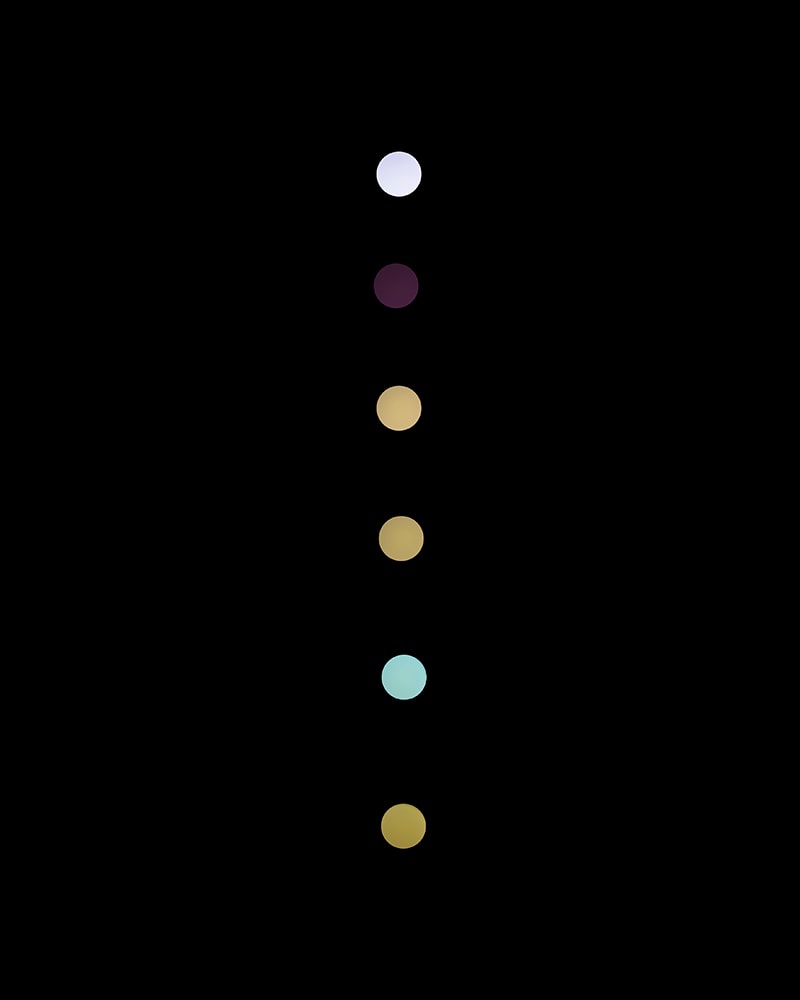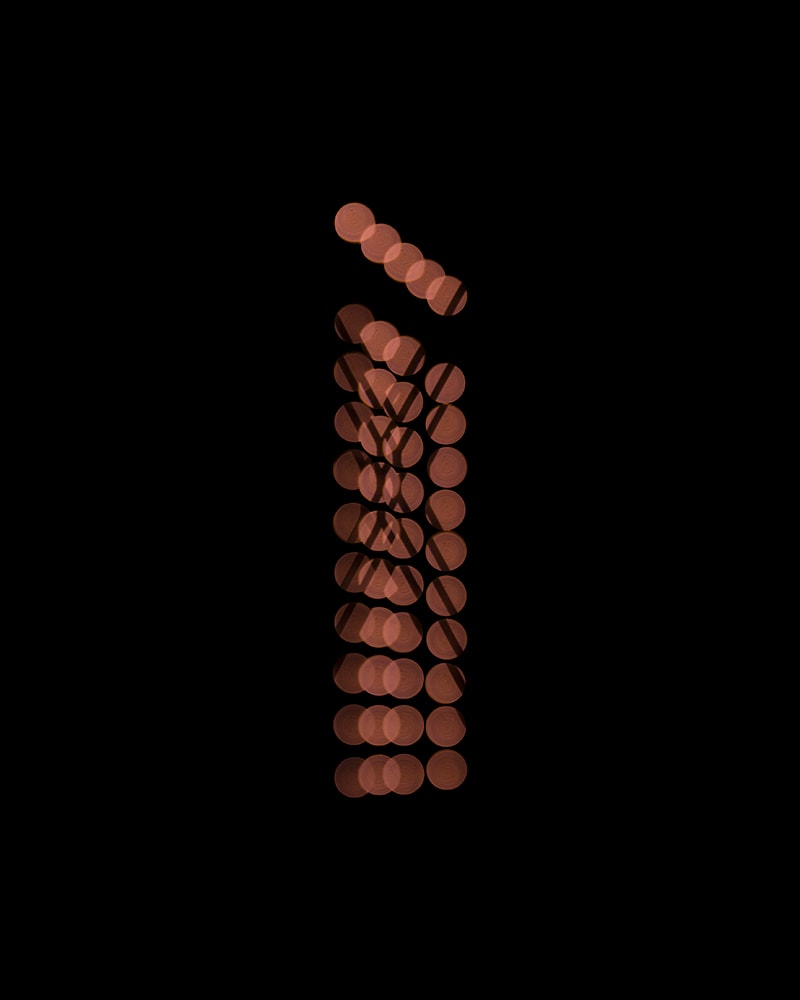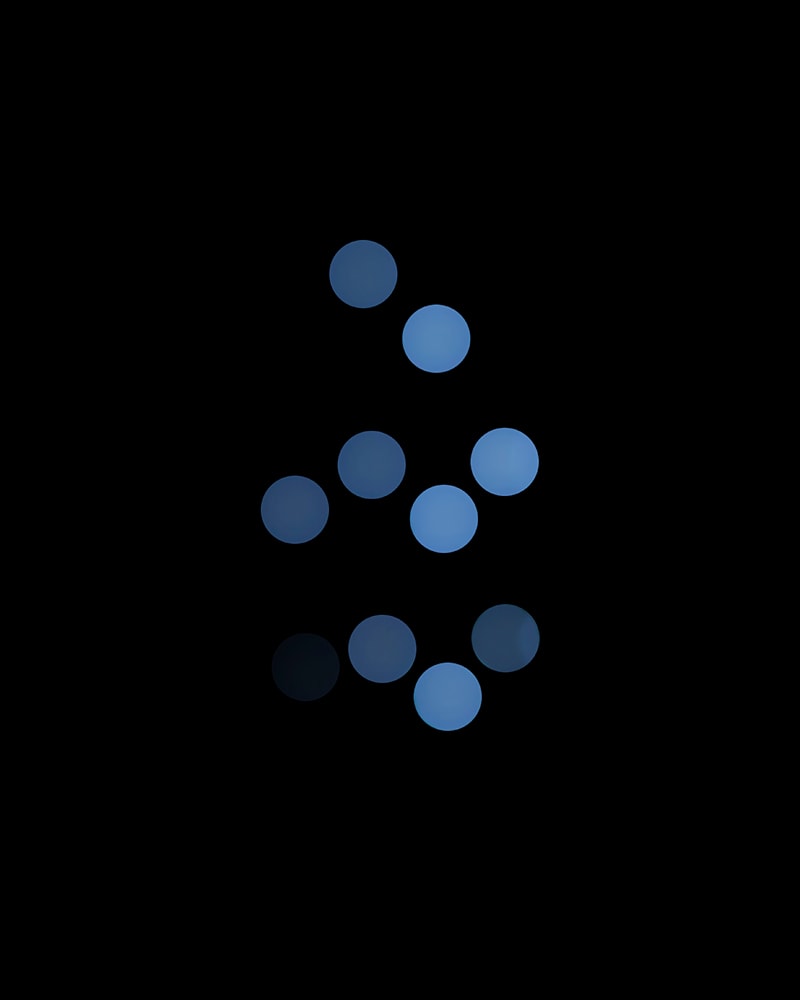昨年アムステルダム、パリ、東京の3都市を巡回した写真展「LUMIX MEETS BEYOND 2020 by Japanese Photographers #7」。本展に参加した岡田舞子は、食品添加物や都会の光をモチーフにしながらも、抽象的かつポップなイメージを作り出し、自らの立ち位置から声を発する。現代社会を批評的に見つめながらも、軽やかに写真表現へと落とし込む岡田の、作品の裏側に込めた想いを聞いた。
インタヴュー・構成=若山満大
写真=白井晴幸
―岡田さんの最新作《Additional》は、添加物を含む食品をモチーフにしたシリーズだそうですね。どうして食品添加物に関心を持ったんですか?
一昨年くらい前から、セレブと言われる富裕層の食事について調べていました。ダイエットや健康維持を目的にお金持ちがやってる食事法を、一般人がマネしてやってみるという文化は昨今定着しつつあります。自分もマネしてみるんですが、そこでわかったことはコストがかかり過ぎるということでした。もうひとつは、代用として選ぶ食品にオーガニックなものはほぼ無くて、もれなく食品添加物が入っているということです。
―セレブの食事を一般庶民がマネするには、安い代用品を使わなければいけない。その食品にはもれなく添加物が含まれていると。
考えてみれば当たり前なんですけど、食品が安く流通するのは添加物で長持ちさせたり、安価においしくできたりするからですよね。いわゆる「うま味調味料」は典型的で、時間とお金をかけなくても簡単に料理をおいしくできる。
―この国の「庶民」として育ってきた僕たちがおいしいって感じる味は、そういう食品添加物によって作られた味なんでしょうね。
そうだと思います。私たちは食品添加物が作った味を「おいしい」と感じて育ってきました。もしグルテンフリーが当たり前の環境で育ってきたら、市販の食パンは「まずい」と感じたかもしれない。
食にかけられるコストの高低は、何をおいしいと感じるかっていう嗜好の問題と相関するなと思ったんです。言い換えれば「食品添加物の味を好む低所得者」と「素材本来の味を好む高所得者」は構造的に生み出されているんじゃないかってことですね。
―おもしろい。食品添加物が作る味への態度と経済格差は関係していると。
食品添加物をモチーフに撮っていて気づいたのは、自分もまた食品添加物を避けては通れない、生きていけないということです。私だって統計的には「低所得者」に分類される身なので、「食品添加物は体に悪いからやめましょう」なんていってられないんですよね(笑)。やめられるなら、もうとっくにやめている。やめられないのは、経済的な事情によるところが大きい。あとは、幼少期からそういうものを常食してきた結果、「おいしい=食品添加物の味」という味覚が形成されたのも大きな理由です。
ほかならぬ私自身が、添加物を摂りながらしか生きていけない、添加物を摂ることにあまり抵抗を感じない体であるっていう事実は、自分にとって切実に響きました。添加物が体に良いとか悪いとかいう議論も大事でしょうけど、問題はもっと根深いところにある気がして。
―食品添加物という、できれば避けたいものと自分が対峙せざるを得ない時、その対峙の仕方をどう変えられるのかってところにクリエイティビティは宿ると思うんですよ。大事なのは対峙の仕方であって、退治の仕方ではない。自分の手には負えない「敵」が目の前にいる、だけど逃げられない。そういう中で「じゃあ、どうするのか」って話。「どうしようもないことを、どうしよう」っていうのは自分たちの世代の課題な気がする。
そう、どうしようもないことはどうしようもない。だから、明るくポップにしてやれってやったのがこの作品ですね(笑)。
―(笑)。撮っているものの中に「自分もいる」という意識は、「Beyond 2020」に出展した前作の《Cell》にもあったみたいですね。
そうかもしれないです。あの作品は田園都市線沿いのマンションを撮影したものでした。ラッシュアワーの混雑した電車の中から、マンションの明かりを眺めていた時にふと撮ってみようかなと思いました。都市っていう過密空間の中にたくさんの人間が住んでいて、動いたり留まったりを繰り返している。自分自身もまた、そんな都市の細胞のひとつなんだなって思いながら。
―都市の本質みたいなものをミニマルなビジュアルと手つきで表現した点が見事でした。そしてもう一つ良かったのが、そうやって社会批判をしている岡田さん自身もまた、当の社会の中に没入しているということです。自分を棚に上げて、あれがダメこれが悪いということは容易い。上から目線の安易な批評は上滑りで、空想的になりがちです。でも、岡田さんの態度はそうじゃない。批判している対象の中に自分が含まれるからこそ、そこにはためらいがあり、自己反省の契機が内包されている。それはすごくいいなって。
いまの50代60代の世代から「いまの若い子たちは殺伐としてるよね」っていわれたことがあります。別に殺伐としてるわけではないと思うんですけどね(笑)。悲しんで嘆いたりしているわけではないし、楽しいほうがいいとは思ってるから。ただ「どうしようもないから、そうしてる」って感じですよ。選挙にはいく、でも何も変わらないだろうと予感している、みたいな。

「LUMIX MEETS BEYOND 2020 by Japanese Photographers #7」東京での展示風景
―わかる。社会的な責務は、とりあえず果たそうとはするよね。選挙もデモも署名も、もはや「選挙に行く権利」や「デモや署名をする権利」を守るためにやっている感じすらある。
どうしようもないことを「これは悪いことだ」「変えるべきだ」って深刻に捉えても仕方ないから。状況として受け入れることの方が大事だと思います。だったら、状況に「受け入れやすい形」を与えなきゃいけない。ある問題に、親しみやすいガワを持たせるということ。アーティストがやるべきことは、そういうことなんじゃないかなって。
―だからこそ、ヤバい状況を明るくポップな映像言語で表現すると。それは批判として一定程度有効だと思いますね。
批判ということでいえば、日本のこと「きれい」っていうのも、もうやめたほうがいいんじゃないかと思うんですよね。そう信じたい気持ちもわかるんだけど、実際そうではないし。そもそも食品に人為的に添加された何かが含まれてて、それがどんな影響を人体に与えるのかわからない中、みんなスーパーやコンビニで日々食べ物を買ってるわけですよね。規格外の量の添加物が入っていても、見た目では絶対にわからない。そういう、かなり不透明な状況に目をつぶったまま、現状を無批判に肯定するのはやめたいなって。
別にジャーナリズムがやりたいわけではないんです。ただ、社会には批判すべき点がいくつもあって、そのことを共有できるといいとは思っています。あとは、批判しているその社会の中に「自分もいるんだ」という自覚があればいい。写真を撮って誰かに伝えるという行為を、そういうスタンスでやっていきたいですね。それが新しい何かにつながるといいなと思ってます。

岡田舞子|Miko Okada
1993年岩手県生まれ。2014年、日本写真芸術専門学校卒業。2015年、KAWABA NEW-NATURE PHOTO AWARDアート部門受賞。2019年、Nonio Art Wave Award 審査員特別賞名和晃平選。今年、アムステルダム、東京、パリを巡回するグループ展「LUMIX MEETS BEYOND 2020」に参加。
>岡田舞子のオンラインギャラリー「IMAGRAPHY」はこちら
2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。