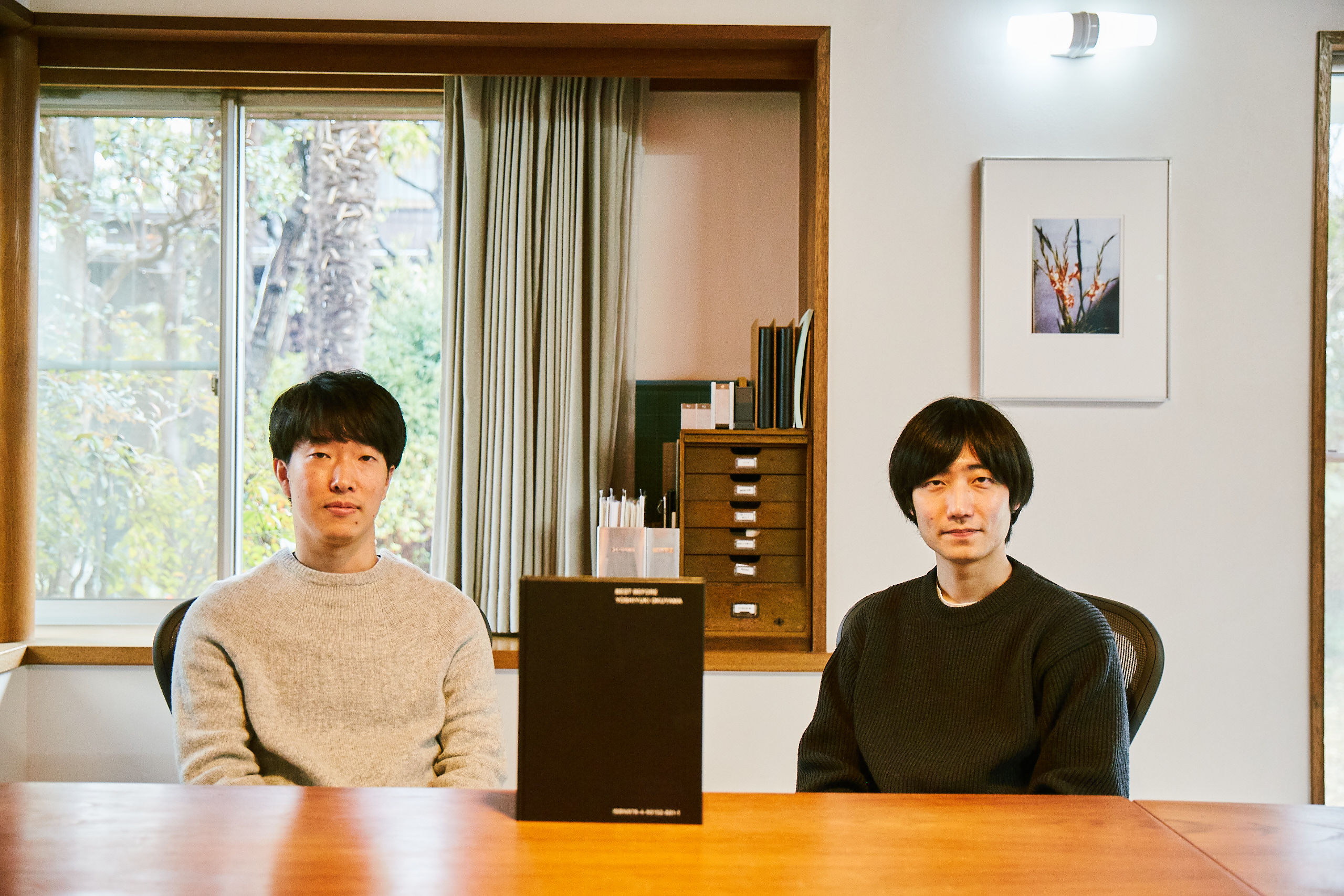約12年間にわたるクライアントワークをまとめた『BEST BEFORE』を出版した写真家、映像監督の奥山由之。常に変化を恐れず、ものすごいスピードで時代を駆け抜け、どの瞬間においてもベストを詰め込んだ445点ものイメージが収録された512ページの超大作は、重厚感がありながらも、軽やかでその装丁にも奥山らしさが表れている。ここでは、同書のために書き下ろした寄稿文にて奥山を「決して消えない光を集める」と評した東京都写真美術館の学芸員である伊藤貴弘とともに、刊行されたばかりの同書について語り合う。アイロニカルなタイトルに込めた思い、写真における言葉の役割、個性的な作品を生み出す秘訣など、写真界を牽引する二人の対話から、この本の底知れない可能性を探ってみた。尽きることのない二人の対話を前・後半に分けてお届けする。
写真=小山和淳
文=IMA
>後編はこちら
ストイックなデザインの中に潜む熱量と葛藤
伊藤貴弘(以下、伊藤):そもそもの経緯から伺ってみたいのですが、いままでのクライアントワークをひとつの形にまとめようというアイデアは、いつぐらいからあったのでしょうか?
奥山由之(以下、奥山):活動を始めてから約10年が経った2、3年前に制作がスタートしました。クライアントワークだと、案件ごとに手法やアプローチの仕方、撮影スタイルが異なるので、表面的な統一感がないのですが、本としてまとめることで散在していた写真に貫かれている本質であったり、表層化していないコンセプト、“自分らしさ”にこの先のどこかで気付きたいと思ったので、編集不可能な状態、つまり本としてまとめておく必要があると考えました。本を作る意義のひとつは、物体として残ることによって、制作当時は無意識だったことに対して、客観視による意識的な気付きができる点だと思います。長い年月を経て見返したときに、客観性を持って、かつての自分はこういうことを表現したかったのではないかと気付ける装置を、クライアントワークにおいても作りたかったんです。いざ制作をスタートすると……この本を見ていただくとわかると思うのですが、レイアウトからクレジット、装丁に至るまで、まとめ上げるのがとにかく大変でした(笑)。十数年間の中で関わってくださった多くの方々から掲載許可を頂き、文字情報を整え、膨大な写真の新たな魅力を引き出せるレイアウト構成を探り、どういう装丁にするか決めるという、本作りでは当たり前のプロセスではあるのですが、その質量が膨大なだけに、総括してひとつにまとめるのは体力勝負でした。出版社の青幻舎の方々を初め、アートディレクターの平林奈緒美さん、僕のマネージャーやアシスタント、本作りに協力して下さった全ての方々に心から感謝しています。
伊藤:これだけの量の自分が撮った写真を見返すというのは、楽しい作業でしたか? それとも撮ったときのことを思い出して辛い部分もあったのでしょうか?
奥山:クライアントワークに限らずの話ではありますが、時間や予算に上限がある中でたくさんの方々と一緒にベストを探るので、当然衝突もあります。仕事をしている最中はある種の興奮状態で気づかなかったのですが、こうやって冷静に客観視してみると、クライアントワークの枠の中でよくこんなにもコンセプチャルな写真を撮らせていただけたなと思いますね。それは表現における自由度の話に限らず、自分一人ではなく、さまざまな方々の技術や才能が集まってようやく作られたものであることの再確認にもつながりました。撮影当時ももちろん思っていましたが、改めて見返すと、関わってくださったみなさんへの感謝の気持ちが強く湧き上がってきました。いろんな人たちと共有した気持ちや思い出がそれぞれの写真に詰まっているので、掲載写真を選び出すのに長い期間がかかりました。それにシリーズとして複数枚でひとつのまとまりになっているクライアントワークもありますし、それぞれの写真が明確に個々の目的のために撮られているので、本を構成する前提で、一枚一枚、独立した”写真”として捉えることも難しかったです。
伊藤:『BEST BEFORE』のために奥山さんが書き下ろされたあとがきを拝読して、作業に集中し過ぎてしまう部分や多忙なスケジュール、矛盾する自分を抱えながら制作されている姿などの葛藤がリアリティを持って伝わってきました。しかもこのボリュームの写真集をまとめるときも、同じような大変さがあったわけじゃないですか。本当にすごいなと思いました。
奥山:ありがとうございます。あとがきの方向性は迷いましたが、仮に胸のうちにある感情を吐露したとしても、今回アートディレクションを担当してくださった平林さんなら、そのエモーションをデザインとして冷静に整頓してくださると思ったんです。普段、ステートメントはあまりそういった感傷的な書き方をしないように心掛けているのですが、今回は、写真集を開くと音が聞こえてくるような、風が吹くようなものにしたくて、自分自身がある種の興奮状態にある様相も残して書こうと思いました。でも、客観的かつ論理的に僕の作品をとらえていただいた伊藤さんと編集者の河尻亨一さんの文章がなかったら、きっと本全体が必要以上にエモーショナルなものに見えていたかもしれません。
―今回伊藤さんに執筆を依頼された経緯を教えていただけますか?
奥山:「flowers」という作品を制作していたときに、伊藤さんにプリントを見ていただく機会があり、その後同タイトルの写真集(赤々舎、2021年)の出版記念イベントで対談をしてくださったんです。僕は、作家として自分の作品に纏わるコンセプトや制作過程を語ることはできても、長い写真の歴史において自分の作品がどういった存在であるのかを冷静に判断するのはまだ難しい。対談のときに伊藤さんが、僕自身が無意識に考えていたことをクリアに言語化してくださったので、伊藤さんの言葉を介して、自分の作品をより深く知るような新鮮な体験ができました。それが、今回依頼させて頂いたきっかけです。
伊藤:改めて写真についてゼロから考え直す機会になったので、とてもありがたかったです。この本のプロダクト的な装丁がすごくいいですね。奥山さんの写真に寄り添って、もっと凝った装丁にすることも可能だったと思うんですけど、“枠組み”がしっかりしている。今回特にクライアントワークという多様な仕事を、一冊にまとめるのは大変だと思います。そういうときに枠組みみたいなものがあると、ひとつひとつの写真がちゃんと際立って見えてくる。『BEST BEFORE』は、それが実現されている装丁だなと思いました。奥山さんの感情が伝わる文章もその枠組みの中でちゃんと収まっていて、それはなかなか簡単にできないですよね。その点でも素晴らしい装丁だと思ったのですが、奥山さんからも色々アイデアを出されたのですか?
奥山:数年前にこの本の企画が始まった時点で、アートディレクションは平林さんにお願いしたいという気持ちが強くありました。アーカイブとしての機能を保ちながら、理路整然とし過ぎず、どこかにふっと可愛げや人間味が立ち上がる本にしたかったので。本に限らず平林さんが手がけられたものは、一見無機質で機能的、ストイックなデザインに見えますが、その中には丸み――物理的な丸みではなくて、ちょっとしたユーモアや可愛げみたいな人間的様相――が垣間見える。モダンなスーツを着こなしてシュッとしているように見えながら、髪の毛の一部が寝癖でちょっとだけハネている人みたいな、どこかほころびのある可愛らしい人柄、そういう印象を平林さんのデザインから受けるんですね。
例えばこの写真集の背に、賞味期限を記すために欧米のスーパーなどで実際に使われているシールを模したデザインや、生産国、重量の記載があるのは、「BEST BEFORE」という「賞味期限」を意味するタイトルにちなんだ平林さんなりのユーモア、かわいげだと思います。また若干だけ小ぶりのサイズになっていることで、分厚い本なのに絶妙な愛らしさを感じる。これ以上サイズが大きいと、威圧感が前面に出てしまったと思うんです。そういった細かなコントロールが素晴らしい。あとは、表紙がシンプルで無機質な印象なのに、裏表紙には過剰なまでの文字の配列がある緩急も平林さんらしいと思っています。無機質なプロダクト的印象と可愛げや人間味という、相反する要素を混在させてほしいとお願いしたこともあり、随所にそういった工夫が施されています。
「賞味期限」を意味するタイトルに込めた思い
―黒い表紙にした理由はあるのでしょうか?
奥山:もともとは『PORTFOLIO』というタイトルで進行していたので、アーティストが持ち歩く黒革の作品ファイルみたいな無機質な佇まいの本をイメージしていました。平林さんにお引き受けいただけるなら、デザイン的遊び心をかき立てるようなコンセプトがなにかあるといいなと思って、第二候補のタイトルだった『BEST BEFORE』を打ち合わせで口に出したところ、平林さんが「デザインのイメージが湧く」と仰ってくださって。ポートフォリオのファイルを模した黒色のビニールレザーだけではなく、シルバーで光沢のあるやや生モノっぽい表紙素材も提案してくださったんです。どちらも魅力的だったので絞り込めず、結果的にシルバーの表紙は限定版として500部限定で作っていただくことになりました。
伊藤:確かに内容的にはポートフォリオに近いのかもしれないけど、初めて『BEST BEFORE』を見たときに、親しみのある写真集だなと思いました。結構手に取りやすいサイズ感で、いろんなところを見る楽しさがある。それはもちろん奥山さんの仕事や表現の幅でもあると思うんですけど、どのページ見ても楽しさと奥行きがあるというか。それが作品だけじゃなく、装丁ともうまく絡み合って実現できている本だなという印象を受けました。
奥山:ありがとうございます。掲載されている写真には、ある種の時代性も反映されているので、この本が10年後、20年後にどうとらえられているのか、それこそが楽しみです。伊藤さんの寄稿文にも書いて頂いてましたが、「BEST BEFORE」というタイトルは、一見アイロニカルですよね。自分としては、「賞味期限」という意味のほかに、単語の意味を知らない人が「いままでのベスト」ととらえるのもいいなと思っていて、そのダブルミーニングを感じ取ってもらえると一番嬉しいです。
伊藤:ベストアルバム的な意味ですよね。

奥山:そうですね。個人の作品制作では作家が伝えたい思想や感情が創作の起点にある一方、クライアントワークは、広告だったら商品、ファッション誌だったら洋服、CDジャケットだったら音楽、というように起点となるモノ、ある種の表現物がすでに存在しています。そして、クライアントワークというのは、その写真の機能が最大限に発揮される瞬間が予め決められている。例えば、ファッション誌で春夏の洋服を撮った写真が秋冬に掲載されても、それでは本来の目的が達成されていない。目的のための機能が最大化される瞬間があるという意味で、クライアントワークにはある種の「賞味期限」が存在すると思っています。但し、「消費期限」ではないというのがポイントです。例えば、ちょっと冷めたポテトの方が好きという場合もあるじゃないですか。写真、音楽、映画にしても何にしても、時間が経過すると、その背景にある時代性が変わったり、それに伴って観る側の感覚基準も変わったりして、「これはこれでいま見る(聴く)とまた別の良さがあるね」みたいにその作品のまた別の側面や魅力に気付けることがあるという意味では、「賞味期限」というタイトルはポジティブであり、作品と時間の関係性を言い表せていると思います。人によって味のとらえ方は様々であって、「賞味期限」は決して作品のリミットではないというのが僕の考えです。けれどほとんどの人がいまのところベスト盤的な意味の「BEST BEFORE」ととらえていて、あまり伝わってなかった(笑)。
伊藤:「BEST」という言葉に引っ張られちゃう人も多そうですね。
奥山:そうなんですよね。このインタヴューで意図が伝わると嬉しいです(笑)。
伊藤:やっぱりタイトルを最初に伺ったときに、これは触れざるを得ないというか。いままでの仕事をまとめたタイトルが、「ポートフォリオ」とか、「ベストワークス」のような、ある種の定型のタイトルじゃなくて、あえて「BEST BEFORE(賞味期限)」と名付けたわけじゃないですか。そこには奥山さんの意図や想いがあるから、直接的には聞かなかったのですが、自分もそれを想像して書く必要があると感じました。もうひとつ自分が意識したのが、被写体である時代の先端を行くミュージシャンや俳優の方々です。言い方がすごく難しいんですけど、その方たちにも「BEST BEFORE」という言葉が響く気がして。東京都写真美術館で開催した個展「新・晴れた日 篠山紀信」(2021年5月18日〜8月15日)の準備に携わり、当時のスターを撮った写真を見てきた経験もあるので、タイトルに込めた思いをちゃんと汲み取ってテキストにする必要があると思ったんです。

プレッシャーをポジティブに転換する力
奥山:自分で自分を追い込む癖があるので、このタイトルをつけることで、無意識下で自分にプレッシャーをかけているのかもしれません。
伊藤:すごくプレッシャーがかかりますよね。
奥山:本の背に印字されている「23 JAN, 2022」という日付が、作家としての自分の賞味期限だとは思いたくないじゃないですか?賞味期限みたいなものがあるのだとしたら、当然その期間をどこまでも延ばしたいし、仮に賞味期限があったとしてもそれを過ぎた上での魅力を放っていきたい。もしほかの誰かが「賞味期限」というタイトルの同内容の本を作っていたとしたら、すごく勇気があるなぁ…と客観的に思いますね。僕自身、まだこのタイトルにドキドキしていますし。ここからより精進していきたいと思います。
伊藤:そういう気質は、制作にとってポジティブに働いている部分が大きいですよね。大変な部分はもちろんあるにしても、制作を続けるためのエンジンみたいな。
奥山:そうですね。毎日のように作品制作に向き合っていると、ルーティーン化しかねない。なので、常に新たなアプローチを探そうとする気持ちや、自分自身が新鮮な気持ちで感動できるような創作をしたいという意識が強くあります。けれど同時に、人一人から生み出せる表現の幅には限界がある。そうすると、作れば作るほどやったことが増えていって、まだやっていないことが減っていく。同じことを繰り返せばすぐに作れても、新しいことに挑戦すると、慣れていないことばかりに囲まれるので、自ずと時間がかかってしまう。この方針を守っていくと、ひとつのものを作るのにかかる時間が年々長くなって、作れるもの自体が減ってくる。でも仕方ないんですよね……。1度作ったものを縮小再生産したくない。『BEST BEFORE』を見返すとよく分かるのですが、やはり初期の方が作品の点数が多く、けれどその分似通った写真が多い。年々作品数は減るものの、明らかに新しいことへ挑戦している様子が伺えます。
僕は写真と映像、両方の創作をしていますが、写真においては写真集や展覧会といった個人の作品制作の他に、ファッション、広告、音楽、ライフスタイルなど様々なジャンルの商業写真があり、映像においても、MV、CM、映画とそれぞれを同時に進行しています。まるで、回転椅子に座った自分の周りをいくつもの白いキャンバスが囲んでいて、このキャンバスには油絵を、こっちには水彩画を、これにはデッサンを……みたいな感じで、それぞれのキャンバスに個々の手法で少しずつ描き足していく。そんな感覚の日々なんです。特定のキャンバスばかりに描いていると、久々に別のキャンバスに戻ったときに、画材の使い方であったり描き方そのものがわからなくなっている。また1からなんです。ただ、その状況を自分から望んで作っています。やっぱりひとつのキャンバスだけに描き込み続けていると、描いた部分ばかりが増えていって、まだ描いてない白い部分が少なくなってしまう。一度描いた線の上からもう一度同じ線を描いたらもっと美しい線になるかといったらそんなことは殆どないと思います。常に新参者の気持ちで、まだ向き合ったことのないキャンバスに、使ったことのない画材で、描いたことのない絵を描きたい。ただもちろん、手段と目的の順番が逆になっては意味がないと思っています。つまり、そもそも熱烈に「描きたい!」と思っている絵しか描かないです。
話がだいぶ逸れましたが……、そういった葛藤も含めてあとがきを書きました。これは不思議な感覚なのですが、作品作りにのめり込むと、あることが”わかった”という瞬間に”わからない”ことが出てくるんです。それを繰り返しているうちに、発表の日がやってきて、結局”わからない”を残したまま発表している。すべてわかりきって発表した作品は、いままでで一つもありません。さらに不思議なのは、次の創作をしているときに、過去の“わからない”を見返すと、急にわかったりする。こうして、過去に残した疑問や課題が、いまの作品を作り上げていくことがよくあるんです。

伊藤:自分は文章を書くときに、自分の文体みたいなものがなんとなくあって、写真について書くスタンスもなんとなく定まっている。奥山さんと違って毎回新しい試みはしていなくて、積み重ねていく感じで書いている部分があるんです。やっぱり新しさみたいなものを取り入れたいとは思うんですけど、そうすると自分を見失ったり、投球フォームが崩れるみたいなことがあったりするじゃないですか?
奥山:そうですね。なんで新しいことに取り組みたいんだろうな……。
伊藤:以前、ミュージシャンのアルバムの話をしましたよね? ファーストアルバムで華々しくデビューした後に、実験的なアルバムを出すと、オーディエンスの反応が「ん?」みたいな感じになることがある。それともちょっと似ているというか。
奥山:その話しましたね(笑)。20代で作るファーストアルバムは、約20年間抱いてきた思いのすべてを凝縮してバーンと世の中に投じて、続くセカンドは、その勢いの余波みたいなもので作れることもあって、サードになると、それまでとは違うものを作ろうという話になりコンセプトが必要になる。コンセプト出現のタイミングで、ファースト、セカンドでついてきたファンが離れることがありがち、という話をしましたよね。往々にして作り手には、まさに投球フォームを変えることが必要になるタイミングがあると思うんです。その一方で同じものを作り続けることの美学も当然ありますし、同じように見えて当人の中では細かい違いや新しさを見出している場合もある。僕は創作をする中で、感じたことのない感情に出会いたい性分なので、悪く言えば飽き性とも言えるかもしれません。
―例えば、誰も見たことのない被写体の表情や姿を引き出すために心がけていることはありますか?
奥山:クライアントワークで人物を撮るとき、タレントさんのよく見るその人らしさみたいなものが、どの媒体で見てもある種一面的だなと思うことがあります。でも、それはその人自体は多面的なのに、その人をとらえる側の人たちが、言葉に集約しやすいようにその人を一面的に描き、それに被写体も応えている気がします。面には裏と表とがあり、表と裏があるということは奥行きを作ればまたほかの面が出てくる。僕は、その人の多面性をこの角度から見たいという思いが常にある。それもおそらく、自分の多面的な部分も見たいことにつながるような気がしています。自分らしさが型となり、固まってしまうのが怖い。常にチャレンジすれば、経験したことのない壁にぶち当たり、新しい物事のとらえ方に気づき、新しい感情に出会うことで成長もある。この本をめくっていると、自分の中にあるさまざまな面を探ろうとしているのが感じられますし、それを引き出してくださったのはまわりの人たちだったと思います。この12年間で奥山由之という人物は変わっていきましたが、同時に一貫しているものもあると思うので、それがいつか客観的にわかるといいなと思います。

| タイトル | |
|---|---|
| 出版社 | 青幻舎 |
| 発行年 | 2022年 |
| 価格 | 8,800円(税込) |
| URL |
>後編はこちら
奥山由之|Yoshiyuki Okuyama
1991年東京生まれ。第34回写真新世紀優秀賞受賞。第47回講談社出版文化賞写真賞受賞。主な写真集に、『flowers』(赤々舎)、『As the Call, So the Echo』(赤々舎)、『POCARI SWEAT』(青幻舎)『BACON ICE CREAM』(PARCO出版)、『Girl』(PLANCTON)、『君の住む街』(SPACE SHOWER BOOKS)、『Los Angeles / San Francisco』(Union publishing)、『The Good Side』(Editions Bessard)、『Ton! Tan! Pan! Don!』(bookshop M) 、台湾版『BACON ICE CREAM』(原點出版)などがある。主な展覧会は、「As the Call, So the Echo」(Gallery916)、「BACON ICE CREAM」(パルコミュージアム)、「君の住む街」 (表参道ヒルズ スペースオー)、「白い光」(キヤノンギャラリーS)、「flowers」(PARCO MUSEUM TOKYO)、「THE NEW STORY」(POST) など。近年は、映像の監督業を中心として活動をしている。
伊藤 貴弘|Takahiro Ito
東京都写真美術館学芸員。1986年東京生まれ。武蔵野美術大学美術館・図書館を経て、2013年より東京都写真美術館に学芸員として勤務。主な企画展に「松江泰治 マキエタCC」展、「琉球弧の写真」展、「写真とファッション 90年代以降の関係性を探る」展、「小さいながらもたしかなこと 日本の新進作家 vol. 15」展、「長島有里枝 そしてひとつまみの皮肉と、愛を少々。」展、「いま、ここにいる―平成をスクロールする 春期」展など。