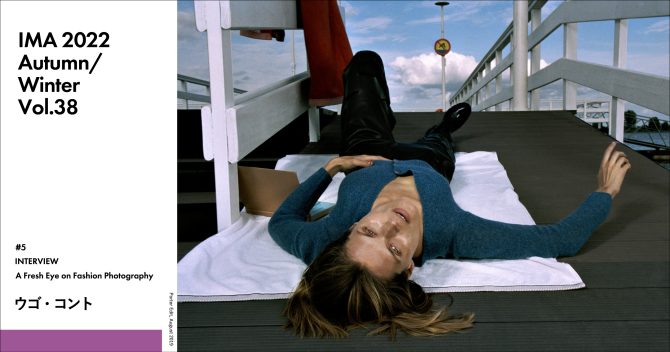東京・六本木の森美術館にて「マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート」展が開催されている。現代を取り巻く新しいテクノロジーであるAIやVR、ゲームエンジンなどを採用した現代アートを展覧している。ここまで同様の分野にフォーカスした展示は過去無かった。新技術と作家の関係、またこうした技術がもたらす鑑賞体験とは何か?現実と仮想空間が入り混じる本展について、展覧会アドバイザーを務めた畠中実氏に寄稿頂いた。
文=畠中実
メディア・アートというジャンルは、いずれ現代美術に包摂されることになるだろう、といったことが言われるようになって久しい。それは、メディア・アートというジャンルが、技術的、手法的な新しさに多くを負っているということと、それが一般化して、新しさという価値が淘汰されていくという状況変化についての言説でもあるだろう。個人的には、そのような状況を認めつつも、そうしたエントロピー増大による均質化の方向ではなく、いまだ芸術と見なされていない何かが生まれる可能性を持ったメディア・アートという領域は存在し続けると考えている。しかし、あらゆる新興芸術が、いずれある種の本流(というものがあるのか、という議論はさておき)に組み入れられていくことは必然とも言える。
森美術館で6月8日まで開催中の「マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート」(以降「マシン・ラブ」展)もまた、そうした状況認識から出発している。現在、コンピュータで生成されるイメージがインタラクティヴに反応するようなメディア・アート(もちろんこれは、このジャンルのある側面、あるいは一部の特徴を表したものにすぎない)が、現代美術の動向の中でも注目を集め、多くの作品が発表されている。アーティストは、そうした同時代の新しい手法、手段、技法を無視できなくなっているとも言えるだろう。直接的に新しいメディアを手段にするのみならず、現在のメディア環境の中で発想された伝統的な技法による作品をはじめ、同時代のテクノロジーから触発されて制作を行なっているのである(近年では、2023年から2024年にかけて、金沢21世紀美術館で「DXP (デジタル・トランスフォーメーション・プラネット) ―次のインターフェースへ」展が開催されているなど)。
そうした状況を加速させた一因として、コロナ禍が挙げられる。それは、移動や集会の制限にともなう、展覧会のヴァーチャル化にはじまり、フィジカルな制作および発表の場の喪失、といったことに起因する。たとえば彫刻という立体を扱う形式では、3DCGによる三次元データの造形が試みられるなど、制作のデジタル化が促進された。そして、多くのアーティストが、コンピュータを使用し、インターネットを介して作品を制作するようになった。それ以後の技術的状況における、NFTの普及や生成AIの急激な進化、VR作品の急増はご存知の通りである。
しかし、規制の解除などの状況の変化にともない、国内外問わず、美術館という制度は、展覧会をフィジカルに開催可能になったのであれば従来通りの機能に戻るべき、と言わんばかりにヴァーチャル化と美術館のオルタナティヴな可能性を閉じてしまったように感じる。一方、そうした制作環境の変化は、私たちをとりまくテクノロジー環境をいっそう意識させることになり、アーティストたちに同時代的な現代美術の主題として取り上げられるようになった。状況の変化とともに同時代のあらたな表現手法を発見し、メディア・アート的な作品を展開するようになったアーティストたちも多く現れた。翻って、それは現代美術がもはやメディア・アート的な環境に包摂されていることの証左とも言えるのではないか。そこには、ジャンルとしてのメディア・アートや分類としての現代美術にとらわれない、ものの見方としてのメディア・アートが存在しているのではないかと考える。

ゲームエンジンによる映像作品。佐藤瞭太郎《アウトレット》2025年 展示風景:「マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート」森美術館(東京)2025年 撮影:竹久直樹 画像提供:森美術館
「マシン・ラブ」展は、森美術館のこれまでの展覧会の中でも、メディア・アート的主題や表現に特化した展覧会である。もちろん、これまでも森美術館では、多くのテクノロジーを使用した作品も展示されてきているし、同館はそうしたものに果敢に取り組んできた美術館でもある。そして、今回の企画は、それが無視できないほどに、ある傾向として表れ、テーマとして取り上げる必要を感じさせる、という趨勢によって発想された展覧会だということはたしかだろうと思う。日本、特に東京には、メディア・アートを専門にする施設は、展示施設ということではそもそも数が少ないし、その規模も森美術館ほど大きい場所はない。「マシン・ラブ」展は、12組の出品作家が、それぞれ与えられたスペースの空間全体を使って、大規模なインスタレーションを連続的に展観している。さらには、その途中にアドバイザーを務めた谷口暁彦のキュレーションによるインディー・ゲームセンターもあり、それだけでも十分すぎるヴォリュームを持っている。

インディー・ゲームセンター 展示風景:「マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート」森美術館(東京)2025年 撮影:竹久直樹 画像提供:森美術館
それぞれの作品は、メディア・アートの特徴のひとつでもある、さまざまな領域の学際横断的な専門性が駆使されており、テーマもそれを実現するテクノロジーも多岐にわたる。ゆえに、来館者にとってはあまり馴染みのない専門用語が作品解説にも頻出するため、展覧会の冒頭には作品鑑賞のための技術的なキーワード解説が置かれているのも、そうした性質を表している(しかも、生成AIによって執筆されている)。個別のアーティストや作品について、ここでは詳述する紙幅がないが、副題にある「ビデオゲーム」や「AI」だけではなく、デジタルデータをもとにフィジカルな造形を行なったり、ロボット技術を駆使したり、現実の展覧会場に存在する作品が、同時にメタバースにも存在していたり、というような表現手法の多様さも、現在のテクノロジー状況を反映しているだろう。またそれは、現実空間と情報空間とが並列かつ等価に扱われるようになった現在のアーティスト、ひいては私たちの状況を照射するものでもある。どこか現実離れした、まるでゲームの世界に迷い込んだような作品の数々は、現在知らないうちにテクノロジーに耽溺している私たちの姿を映し出すものでもあるのかもしれない。
それぞれの作品が、異なるテーマと世界観を持っており、個別にじっくりと咀嚼するのには、ある程度の体験時間(と体力)も必要なので、時間に余裕を持ってご覧になることをおすすめする。
| タイトル | マシン・ラブ:ビデオゲーム、AI と現代アート |
|---|---|
| 場所 | 森美術館(東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー53階) |
| 会期 | 2月13日(木)~6月8日(日) |
| 時間 | 10:00~22:00(火曜日は17:00まで、4月29日、5月6日は22:00まで) |
| 休館日 | 無し |
| 料金 | 平日/一般2000円(1800円)、学生(高校・大学生)1400円(1300円)、中学生以下無料、65歳以上1700円(1500円) |
| URL | https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/machine_love/index.html |