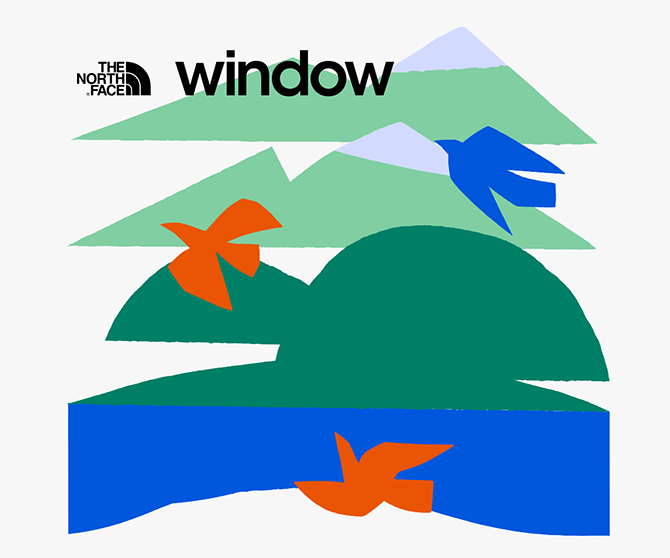人も企業も、“SDGs”を避けては通れない現代。ものをつくるアーティストも同様だ。アートとSDGsはいまどう響き合っているのか?アパレルブランド「ザ・ノース・フェイス(THE NORTH FACE)」と共にジェンダーや環境をテーマに作品づくりを行う作家のクリエイティヴィティを考える。
ザ・ノース・フェイスは、自然や環境保護活動はもちろん、女性のためのアウトドアショップ「THE NORTH FACE 3(march)/ザ・ノース・フェイス 3(マーチ)」の出店やトークイベントを開催するなどジェンダー格差是正にも取り組む。また、こうした活動をオウンドメディア「WINDOW」で発信している。凝ったデザインから、SDGsをアートに訴えてくるサイトだ。
そんなザ・ノース・フェイスと訪ねる第2回目は、フェミニズム的な概念を反映した作品で知られる写真家の長島有里枝さん。金沢21世紀美術館では、自らキュレーションした「ぎこちない会話への対応策—第三波フェミニズムの視点で」展が開催中(2022年3月13日まで)。ザ・ノース・フェイスをプライベートで愛用しているという彼女に、展示の意味と、いまのフェミニズムについて聞いた。
撮影=大久保歩
文=龍見ハナ
―「ぎこちない会話への対応策―第三波フェミニズムの視点で」展、とても新鮮な気持ちで拝見しました。何より、作家のラインアップに非常に興味を持ちました。とくに良い意味で驚き、面白いと思ったのが、小林耕平さんの作品。美術館という空間で行われるフェミニズムについての対話と聞くと、それ自体が自分自身の肌感覚から遠い、権威的な存在のように感じてしまう可能性もあると思ったんですが、日用品を素材とした作品に、アートの語彙で新たな意味を与えようとする小林さんの作品によって、有里枝さんのフェミニズム観のようなものが、ぐっと身近に感じられました。
SDGsと真剣に向き合っている人ほど、昨今、SDGsという言葉が企業ブランディングなどに頻繁に使われている現状に対し、警戒心を持ってしまうと思います。わたしが大学院で勉強を始めた10年前に比べて、フェミニズムをめぐる現状もいままさにそのような局面にあるのかもしれません。
議論することそのものがフェミニズム的なことで、それも運動の一部なんじゃないかとすら思うんですが、学術の世界ではそれが当たり前でも、議論が白熱するという状態そのものが日本の、特に女性にとっては「怖い」と感じられることもあるのかな、と思います。喧嘩している、怒っているように見えるし、実際SNSを通じて、ミソジニストとフェミニストが戦う場面も多いですから。
ただその際、男性vs女性という、単純な構図が捏造されがちです。だからこそ、小林さんをはじめとする男性作家の作品をこの展覧会に含めたかったんです。実際、小林さんの作品のやろうとしていることは、フェミニズムの実践の一番基礎の部分と通じ合うものがあると思っています。
―本展に寄せたステートメントの中で、有里枝さんは「要するに、フェミニズムの実践が必ずしも『フェミニスト』だけに担われていたわけではないことを、第三波フェミニズムは示したといえる」と書かれていますね。

展覧会を企画するにあたってまず念頭に置いたのは、“ある展覧会は、なにをもってフェミニズム展とみなされるのか”ということについて、一度きちんと考えてみることでした。
今回は、作家がフェミニストか、フェミニスト・アートを制作しているかということより、作品にフェミニズム的な解釈が付与できるかどうかという点に焦点を当てています。
そこでまず、自分が作品のファンだったり、活動に親近感を持っていたりする作家さんなら「フェミニズム的に正しい」だろうという確信に基づき、作家のリサーチを進めました。さらに、フェミニズムに関する議論や対話が可能な相手だとわたしが思えるアーティストから優先的に選び、参加の可否を打診しました。
―有里枝さんがその作家を好きなのであれば「フェミニズム的に正しい」という確信は、有里枝さんが女性であり、フェミニストであり、という当事者としての感覚から来るんでしょうか?
そういうわけじゃないし、そうともいえます。説明するのが難しいけれど、自分は「女性」だという意識が思春期までは希薄でした。いまは自分を「女性」だと思っていますが、それが自分の本質という感じじゃなく、あくまで外から与えられたもの、という感覚です。
中学でサッカー部への入部を「女だから」という理由で断られたことや、親友だと思っていた男子に恋愛対象として見られていくことなどがショックで、なぜわたしは女なんだろうと考え始めたのが、フェミニズム的な関心の始まりだった気がします。
「どこにも属せない」という感覚を強く持っていたということは、周縁化されやすい立場にいたということだったのかもしれません。そのせいで、安全だと思える人や場所に敏感だったように思います。そういう意味では、わたしが好きなものや居心地のいい相手は、わたしを虐げない=フェミニズム的に正しいはずだ、と信じてはいるかもしれません。
―参加アーティストの方々と、とても丁寧に対話をされたとのことですが、そのプロセスにはどんな意味がありましたか?
自分の感覚に自信があるのと同じくらい、自信がなくもあって。ほかの人の考えや知識を参照しないと変な方向に突っ走ってしまうんじゃないか、また笑われちゃうんじゃないか、と不安なんです。だから、普段から人との対話を大切にしています。
今回の展覧会では、男性がフェミニズムに参加することの重要さについて、人々の対話が生まれるようなことをしたいというのが目標の一つでした。そういう展覧会自体があまりないので、わたしが何をしようとしているのか参加作家に説明する必要があったし、そのチャレンジを理解しサポートしてくれることを、わたしも彼らに期待していたんだと思います。
どこにも属せない、という感覚はわたしに、どの世界でもどこかアマチュア的な存在だという意識を持たせていると思います。写真の世界では「女の子写真」といわれたり、文筆やアートの世界では「写真家」と見なされたり。それも一つの周縁化のかたちですよね。でも、どっぷりとそのなかにいるわけじゃないからこそできることってあるとも思っていて。かなりオリジナルな立ち位置である分、丁寧な対話が必要だと感じるんです。
正しいではなく、壊そうとする力が大事
―対話が大事ということに反対する人はいないと思いますが、でも実際のところ、本当はどう思っている?ということを確認し合いながら進んでいくことって、そう多くないとも感じます。

昔から、疑問が湧くとすぐに「どうしてですか?」と聞く癖があって。目上の男性には「たてついている」と思われることも少なくなくて、怒られることがよくありました。でも、アメリカで暮らしていたときは逆にわたしのほうが、何に関してもすぐに「Why?」って聞かれる国だなぁ、と感じていました。だから、日本のコミュニケーションは「俺の話に口を挟むな」という圧力を根底に持っているのかもしれないですね。
ただ、最近はわからないことをわからないままにしておくことの面白さ、奥深さみたいなものについてもよく考えるんです。これについては、プライベートでのパートナーの影響は大きいと思いますし、あとは社会学の勉強を続けるうえで「何が正しいか」をより多角的に眺める訓練ができていくと、絶対に正しい答えはない、というところに行きつくこととも、深い関係があると思います。正しくある、ということ自体にどのくらいの意味があるのかわからない、というような感じでしょうか。
40代後半のいま、周りにはフェミニズムを学んで「正しい」知識を身につけた人と思われている気がしますが、本もそれほど読んでいないし、賢いとは思えないことをいってしまうときもあって、“そんなんじゃないのに”と自分では思っています。ただ、ポジティブすぎるかもしれませんが、アマチュア的な存在でいることや知らないことが多いと考えていること、完璧な存在からは程遠い自分でいることって、すごく大事だなとも思うんです。きっと、その「ほころび」みたいなもののおかげで、わたしの話を聞いてみよう、あの人と話してみてもいいかな、と思ってくれる人がいるんじゃないかな。
―展覧会からも、よい意味でそのほころびを感じましたし、ほころびがあるからこその「居心地の良さ」もあったように思います。
ある人にとって「正しい」ことが、他の集団にとって間違えていることって、珍しくないですよね。自分の「正しさ」を押し通そうとしすぎることは、そう考えていない人を「間違えている人」だったり、「自分よりも劣った人」だったりにしてしまう、という危険性もあります。いっぽうで、自分が正しいと思うことをお互いに伝えあって先に進むことは、悪いことではありません。人間はそうやってここまで歩んできたという側面もあると思うので、重要なのは、どうやって相手の話を聞くのか、ということなんじゃないでしょうか。
アーティストとして、正しいか正しくないかよりも、新しいアイデアが既存の社会規範を壊そうとする場面、そういうカウンター的な言説が生まれてくる場所が社会に確保されている、ということのほうが大事だと思うんです。突拍子なく思えても馬鹿にしたり切り捨てたりせず、それを真面目に検討するみたいなことが、とても大事だなぁって。
いまって、お互いの距離が遠いのに、短時間でコミュニケーションを交わすことが可能なインフラが整っていますよね。そのせいか、ちょっと間違えるだけで、見ず知らずの人から愛なき言葉で激しく叩かれてしまう場合もあり、それを恐れて表現を躊躇せざるを得ない空気が簡単に醸成されてしまいます。善意にあふれているのに、自信がなくて黙っている人たちが増えれば増えるほど、政治も社会も悪い方向に進みがち。そういう抑圧がわたしたちの社会にあることは、非常に危険だと感じます。
ーフェミニズム的に正しいかどうか、という意味でも、小林さんだけでなく男性作家が複数人参加していることに、重要な意味があると感じました。
フェミニストであることって、もはや当たり前だと思うんです。つまり女性と男性を対等に、 なんて、わざわざいう必要はないんじゃないかというくらい、実は当然のことですよね。
動物愛護や環境保護なども同じで、この世界で共存する生き物すべてに、自分たちに対するのと同じような関心を持って接することが「運動」としてしか達成されない状況は残念、と考えることだってできるでしょう。子供の頃、わたしが大人になる頃にはますます平和な世界になると考えていたけれど、未だにあらゆるものの平等を訴えなければいけない環境に、わたしたちはいるんです。
フェミニズムが素晴らしいのは、単に女性の救済だけを目指しているわけではないところです。強くなったり、一番正しくなったりすることを目指すのではなく、誰かが誰かのまま、たとえ弱いままでも搾取されたり迫害されたりせず、安心して生きていける世界を目指す思想だと、わたしは捉えています。それって「おんなこども」だけじゃなく、誰にとってもいいことでしょう。そういう理想を掲げて努力できるから人間なのであって、この世界のすべての命のためのこととして、それをやろうよ、と。
―それは第三派フェミニズムへの批判に対する、有里枝さんの姿勢を表すものでもありそうですね。

第三派フェミニズムは、商業主義と結びついているという批判をずっと受けてきました。いまの時代には、フェミニズムをブランディングに利用するだけの表層的な動向もあります。ただ、当然ですが、多くのフェミニストの取り組みは本物ですし、企業や自治体のイメージ戦略の一端かもしれなくても、そのなかに必ず誠意はあると思う。彼らの活動によって発言する場が与えられるのであれば、そこで意見をいっていくことは重要だとも思います。
すべての人が大学に進学し、専門的な教育を受ける機会を持てるわけではありませんし、その年齢に達していない若者も社会にはいます。テレビやラジオ、雑誌のような、安価かつ手軽に享受できるメディアや、ポップカルチャーに乗らなかったら、1990年代の若者にあれほどフェミニズム的な思想は広まらなかったと思います。
当時の若者たちは、フェミニズム的な思想に基づいたものづくりをしているアーティストやミュージシャンの表現を「かっこいい」と思うことで、直感的にフェミニズムの考えに親しんでいきました。憧れのロールモデルが着ているファッションを真似たりするレベルのことであっても、長い目で見れば彼らの人生にとって十分な価値があったのではないでしょうか。
わたしも、90年代の西海岸に暮らして、ストリートカルチャーやヒップホップアーティストの影響で、ザ・ノース・フェイスを知りました。オーガニックフードを食べることや、週末は山に行って過ごす、というライフスタイルを教えてくれた恋人や友人たちにとっても、憧れのブランドでした。
ーザ・ノース・フェイスも、ジェンダー格差是正を目的に“SHE MOVES MOUNTAINS 私が動けば、世界が動く。”というキャンペーンを行っています。2021年の国際女性デーにはトークイベントを実施し、地道に啓蒙しています。しかし昨今、企業の広告においてジェンダー差別と受け取られて炎上することもありますが……。
自分の作品もですが、誰かの活動を矮小化したり、単に消費しようとする人や媒体があることについては、あらかじめそれを避けることができません。残念ながら、間違えた解釈を流布されたり、嫌な思いをしたりしたら、それをきっかけに対話を始めていくしかないでしょうね。
失敗は、していいと思います。わたしの父は男尊女卑的な考えも持っている人ですが、それに抗議をするわたしを子供なのにとか、女なのにとかいう理由で黙らせようとは絶対にしません。誰かが完璧な悪人であることは稀で、ほとんどの差別やハラスメントが難しいのは、それが自分にとってどうでもいい人からの行為ではないから、ではないでしょうか。それでも、本当はいい人だからなどの理由で、自分が我慢をしてその問題を受け流してしまうのは違うと思います。諦めずに、傷ついたということを伝えたいですよね。一人でできなければ、身近な信頼できる人に相談してほしいなと思います。親しい人ではなく、専門の機関に相談するという方法もあります。
それから、企業のケースと個人のケースを混同して語ることはできないですよね。企業には企業としての社会的な責任がありますし、キャンペーンをおこなうことが利益を得ることに結びつく、というビジネスの基本的な戦略がある以上、その内容について、事前に十分な検討をおこなう責任があると思いますから。ただ、企業や政治家が何か失敗をした場合にも、一番大事なのが誠実さであることには変わりがないと思います。自分に必要な製品を選ぶとき、わたしが基準にするのはその企業が利益というものをどのように捉えているのか、ということです。安い商品を供給できても、不当な賃金で労働させられている人がその裏にいれば商品は買わないですし、いずれ使えなくなったとき、環境にどんな負荷がかかるのかを想像して作られていないものも嫌だなと思います。女性の重役がいるかどうか、利益の一部が社会貢献に還元されているかどうかも気になります。

「90年代アメリカ西海岸で過ごすと、ザ・ノース・フェイスってかっこいいんですよねえ」と話す。
ー最後に、今回のキュレーションのプロセスそのものが「ぎこちない対話への対応策」であり、その意味で、この展覧会そのものが有里枝さんの作品ともいえると感じました。有里枝さんはアーティストとして、会話を生んでいくという目的意識がこれまで以上に強まっている印象を受けます。
おっしゃる通り、自分の制作だけでなく、書評を書いたり、コンペの審査員をしたりなど、他の作家と関わり、彼らを評価するような仕事も増えました。そうした活動を通じて改めて気付いたのは、自分が美しいと考える作品には、既存の価値観をいい意味で揺るがすようなものが多いということ。人々がそれについて対話を始め、「結局わからなかった」という結論でもいいんだけれど、なにかしら新しいコンセンサスを得ていくプロセスを提供する、そんな作品に惹かれているんだな、ということです。
自分が美術家かどうかとか、結果として生まれた作品の評価がどうなのかとか、大切なのはそういうことだけじゃないんだろうな、と思うんです。他者との関わりによって生まれるケミカルリアクションに、期待しているのかもしれません。
長島有里枝|Yurie Nagashima
1973年、東京都生まれ。武蔵野美術大学在学中に公募展を経てデビュー、カリフォルニア芸術大学MFA修了。2011年、武蔵大学大学院に社会人枠で入学し、フェミニズムを学ぶ。写真集『PASTIME PARADISE』で、第26回木村伊兵衛写真賞受賞。短編集『背中の記憶』で第23回三島由紀夫賞ノミネート、第26回講談社エッセイ賞受賞。第36回写真の町東川賞国内作家賞受賞。アーティストとして活動する一方、文芸誌や新聞への寄稿、大学で講師を務めるなど、活躍は多岐にわたる。主な著作に『「僕ら」の「女の子写真」から わたしたちのガーリーフォトへ』(2020年)、主な近作作品集に『Self-Portraits』(2020年)などがある。