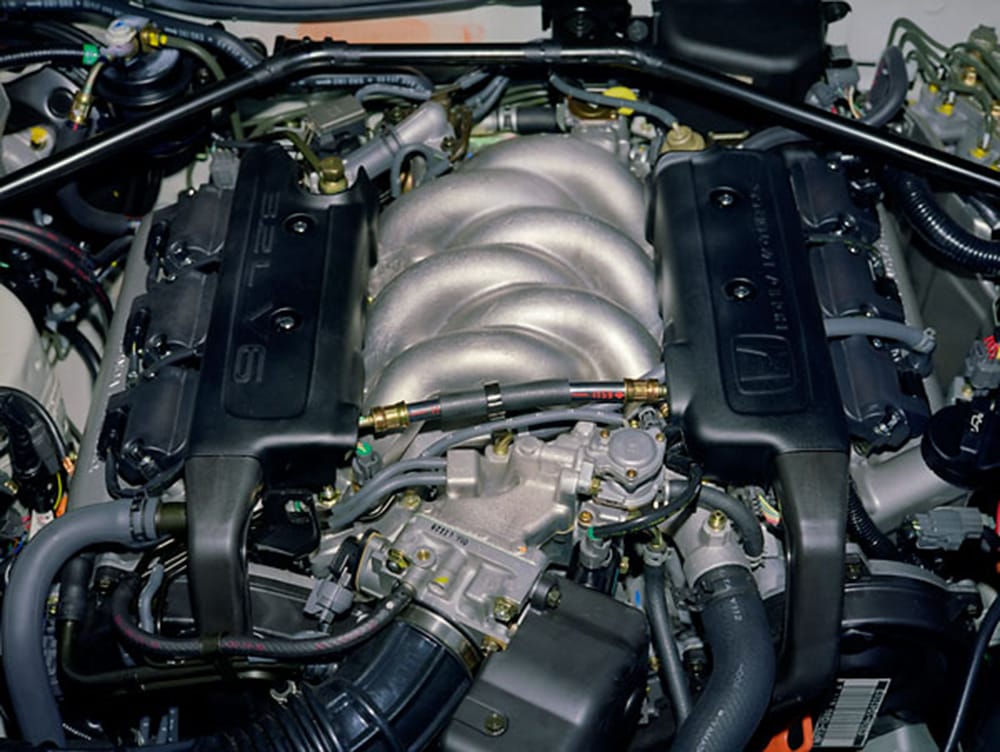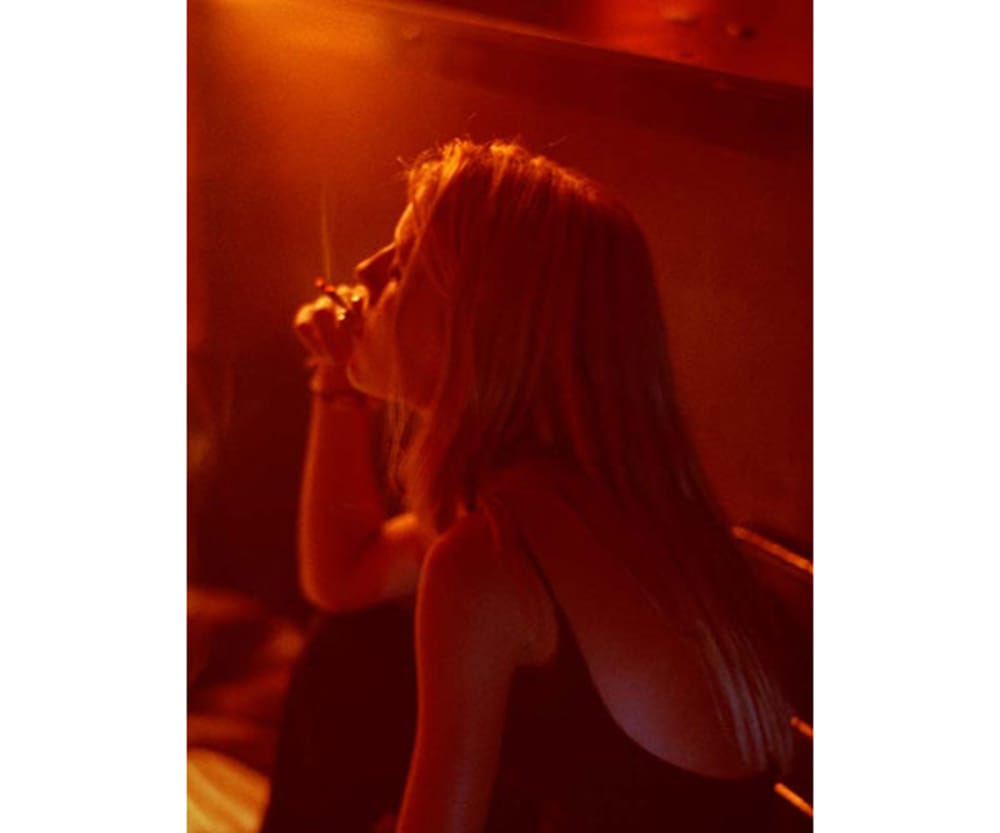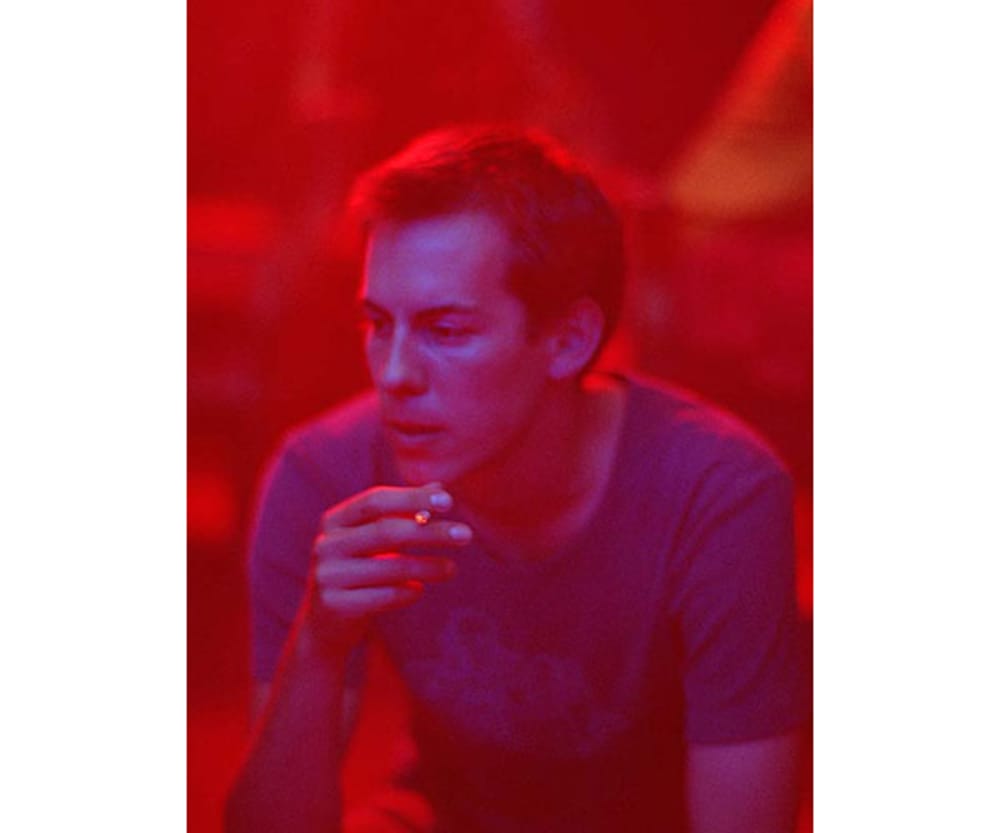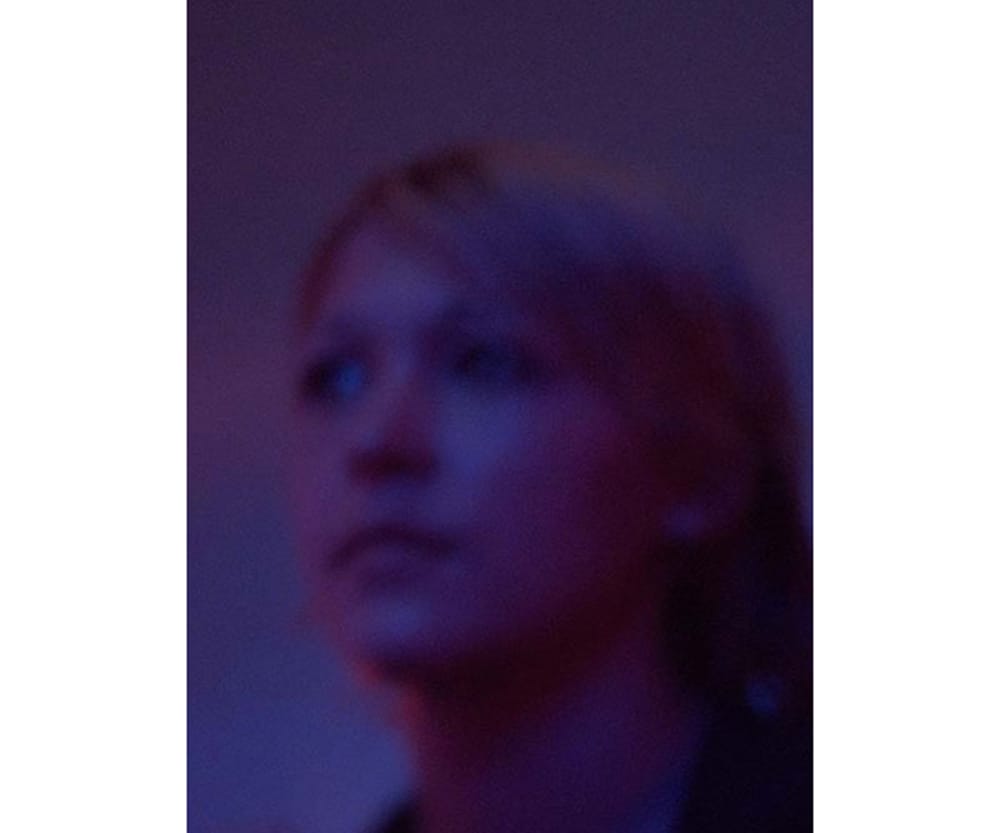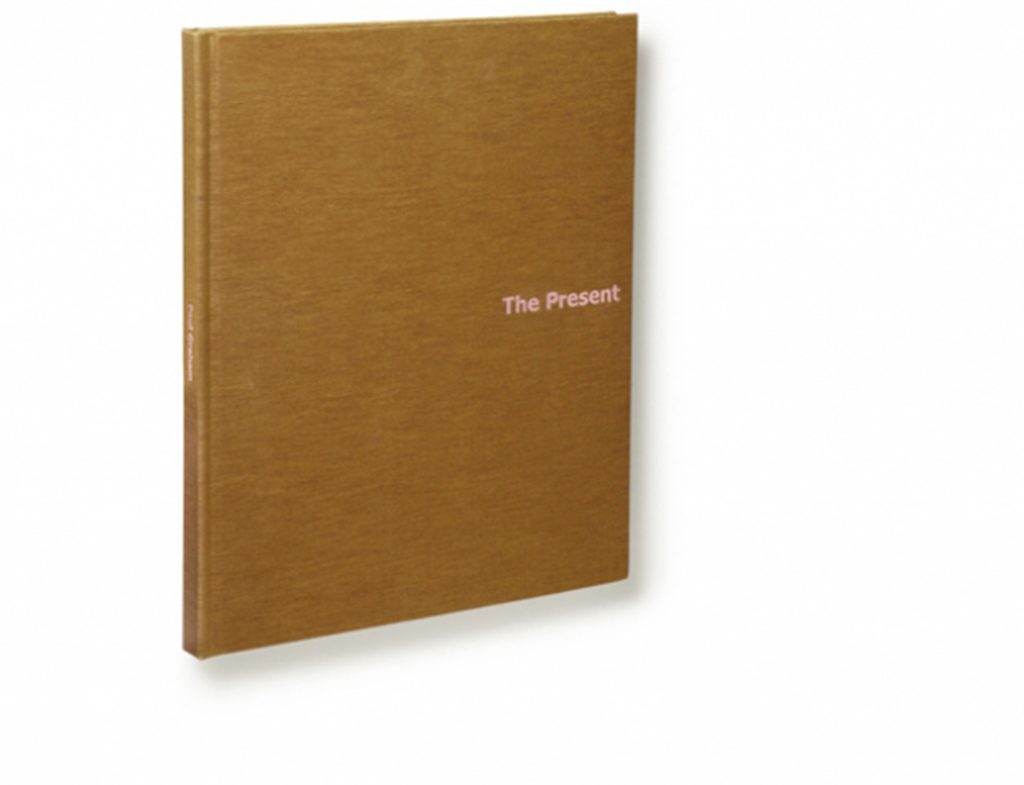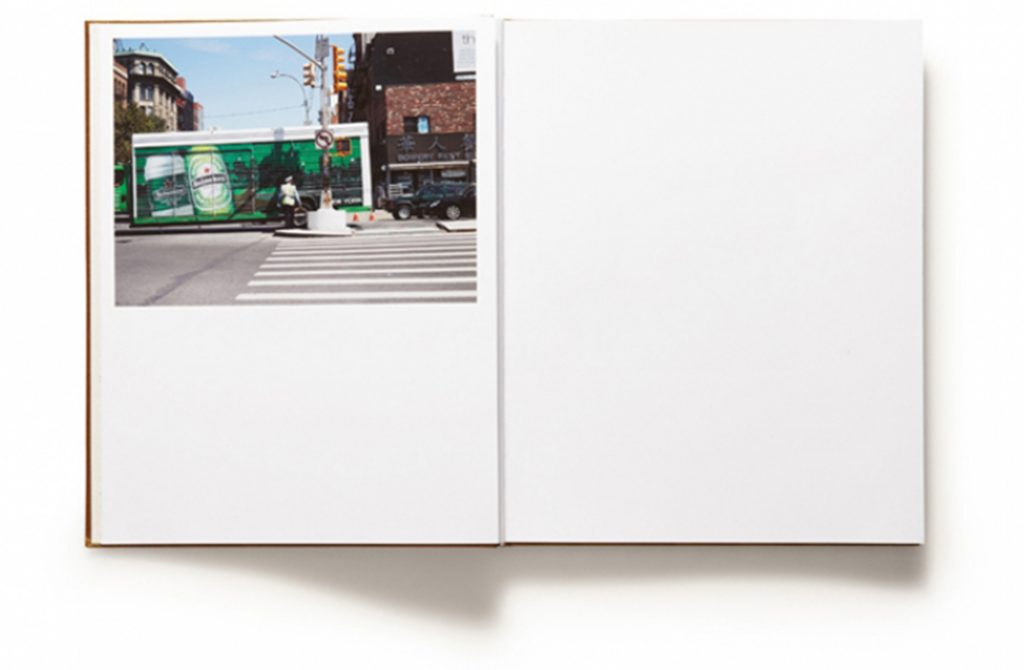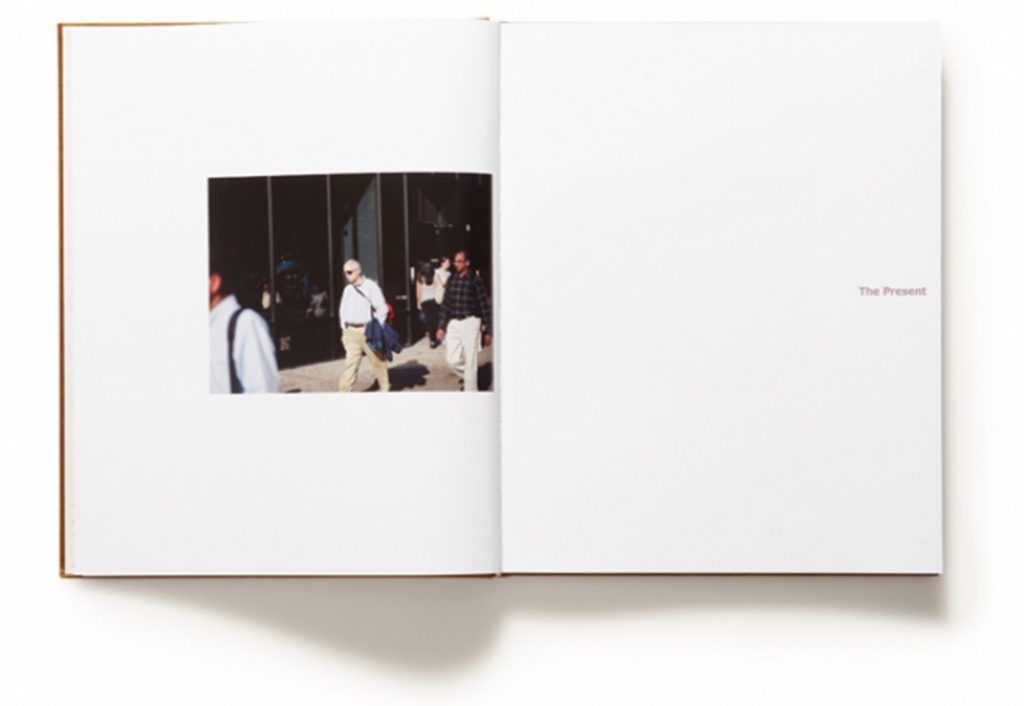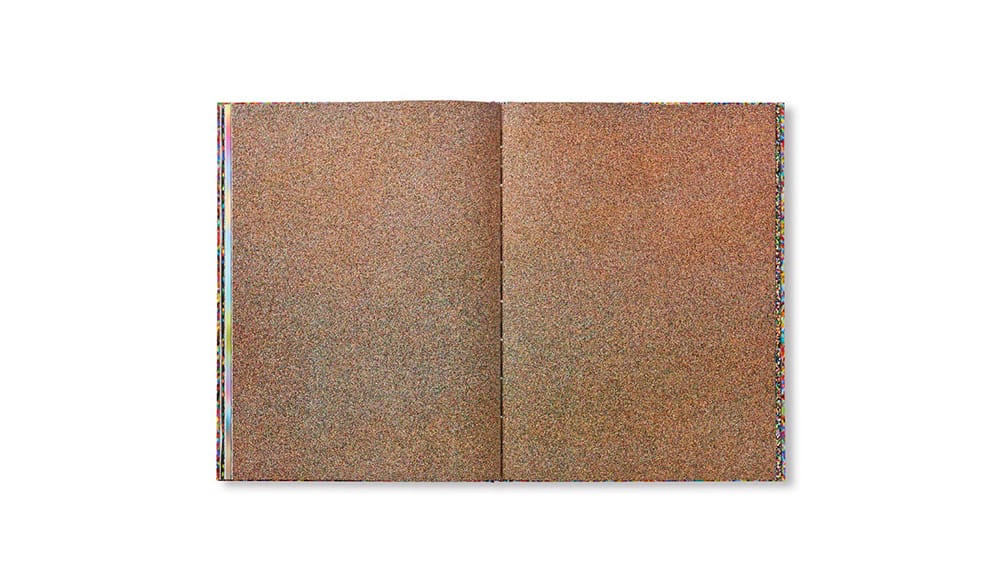イギリスに生まれ、アメリカへ移住してから自身の写真表現を突き進んできたポール・グラハム。ドキュメンタリー写真から出発した彼は、1990年代にアメリカへ移住後、2007年にMACKから出した12冊組の写真集『A shimmer of possibility』で脚光を浴びる。一見すると何も起こっていないように見えるストリート写真のシークエンスには、イギリスとアメリカの写真文脈を経てきた彼の鋭い社会批評と、写真の構造を再解釈するようなコンセプトが潜んでいる。時代の潮流と逆行し、常に新しい写真表現を開拓してきた彼の長いキャリアについて聞いた。
インタヴュー=石野郁和
写真=高橋マナミ
―まず初期作品集『A1-The Great North Road』(1983年)、『Beyond Caring』(1986年)と『Troubled Land』(すべてGrey Editions、1987年)は、生まれ育ったイギリスの政治状況に基づいた、とてもポリティカルな作品ですね。白黒の写真が主流だった時代にカラーで撮影されています。あの時代のヨーロッパのドキュメンタリー写真の中では、写真を起用したコンセプチュアルアートの方に近かった。その中でどのように制作されたか、またあの頃のイギリスの政治状況そして写真の世界についてお話ください。
確かあれは1984年で、もう35年も前です。マーガレット・サッチャーの時代で、失業率がとても高かった時代です。彼女はイギリスの労働組合の力を削ぎ、それによって失業率がとても高くなっていました。その時私自身も無職のアーティストでした。無職の坑夫や機械整備士とはまた違うけれど、無職であることには変わりはありません。職業安定所には長い行列ができていました。しかし同時にその頃に私はカラー写真の発展に気づいていました。すでに『A1-The Great North Road』を本として出版していました。そこで写真の古典的なテーマである失業をカラーで撮影してみたら面白いだろうと思いつきました。
私はその頃まで人々が常に執着してきた社会的な白黒写真を、カラーで撮影したんです。それは北アイルランドを撮影した『Troubled Land』も一緒です。あの時は伝統的で美しく、非現実的だと評されていた風景写真を、戦争写真や争いの写真と混ぜました。そのようにして、84年、85年にこのシリーズを作り、本を87年にGrey Editionsから刊行しました。
―後の『A shimmer of possibility』や『The Present』に比べて、『Beyond Caring』の構図は緩く、傾いています。写真の中ではほとんど何も起きていない様は、その頃の経済が下落した社会に生きる人々の心理状態を表しているようです。
あの頃人々は待つことしかできず、無気力そのものでした。仕事もないしやることもない。自分の面談の時間を待つしかなく、それ以外選択肢はなかった。そして監視にバレないようこっそり撮影するために、カメラを首にぶら下げたり、膝のあたりまで下ろしたりしていたので、時々傾いている。その構図は好きでした。意図的に傾けていないということ、そして傾いているものをそのままにしたことが良かったのです。
―確かに、その時の人の心理状態とマッチしていますね。
世界は少しずつ悪い方向に流されていっていて、嵐の中の船に乗っているみたいで、自分では何もコントロールできませんでした。この時はプラウベルマキナの6×7の中判カメラでカラーフィルムを使っていました。こうしてイギリスでの3作品が本として出版されました。『A1-The Great North Road』、失業・無職に焦点を当てた『Beyond Caring』と北アイルランドの抗争を取り上げた『Troubled Land』です。この3シリーズはひとつのまとまりとして、1980年代初期のあの“魔法の王国”をテーマにしたものです。
―ニューヨークと日本を行き来しながら、日本で『Empty Heaven』(1995年、Scalo)を制作しています。なぜ日本で撮影しようと思ったのですか?
まずニューヨークから撮り始めていました。最初の3シリーズを終えた後、私はイギリスを離れたかった。その頃にはマーティン・パー、アンナ・フォックス、ポール・シーワイトなど、皆がカラーで撮影していました。そしてそれが「ブリティッシュ・カラー・ドキュメンタリー・フォグラフィー」として大きく取り上げられていました。ニック・ワプリントンなどもそうですね。私はその写真家の一人ではありたくないと思い、ヨーロッパ内で仕事を始めました。
その頃のヨーロッパは、新しいヨーロッパのあり方、EUとしてのあり方を追い求めて未来へ進もうとしていました。国境がない国々が共に進むように、どの国でも働けました。同時にその裏には過去の陰が存在していました。差別主義はまだ根強く、常に過去の影と未来への希望の双方から生まれる緊張感がありました。なので、その頃の作品は過去と未来の間を行き来しています。そしてその頃、日本人の恋人がいたので日本を訪れたのですが、日本に来て正直驚きました。ヨーロッパで興味を持ったその緊張感や、過去の陰影とその過去を受け止めて未来へ進む志は日本も同じだったんです。
―面白い見方ですね。
20世紀のドラマチックな歴史ですね。日本は他の国と同様とても暗い過去がある。それでも意識的に再生するように、未来へと歩んでいた。そういう点をつなげる方向へ思考が向いていました。
―あなたの作品の移り変わりにとても興味を持っています。最初の3部作の後、Scaloから2冊『Empty Heaven』(1995年)と『End of an Age』(1999年)の写真集を出版していますが、日本を撮ったこの『Empty Heaven』について聞かせてださい。
『Empty Heaven』は明らかに私の内側とのつながりを表現しています。ここは日本なので詳しく話すと、これは過去の陰、第二次世界大戦、原爆などと、ハッピーでキュートな現代とのつながりでもあります。これを最初に作り始めた時、人々に私はクレイジーだと思われました。そしてこのふたつの極端な影と光の間を行き来しているときに、スーパーフラット運動が始まりました。
―村上隆さんの芸術運動ですね。
あれとほとんど同じ問題を取り扱っています。でも私の方が村上隆より先だった。
―この写真集の構造はスーパーフラットのコンセプトにとても似ていますね。同じページの中に存在する写真が、ひとつが突出していることはなく、全部同じヒエラルキーの内に存在しています。
そうです、なので驚きました。スーパーフラットとカワイイ、アニメ、フィギュアなどが過去のトラウマに言及しているというつながりが見えて、とても興味深いと思いました。
―最初の3部作では、ポートレイトはある一定の距離感を保って撮られていましたが、『Empty Heaven』や『End of an Age』では急に被写体との距離が縮まったように思えます。何か変化があったのですか?
親密度ですね。『Empty Heaven』に写っているほとんどの女性は私の友人でした。男の人たちはみな、東京の金融街で、霞が関で働いている、主に金融系の官僚です。『End of an Age』はナイトクラブで強いフラッシュを用い、はっきり見える写真と、フラッシュなしで撮った写真が混ざっています。ふたつの違いは、いま生きているこの世界をはっきりと見たいか、それともあやふやな焦点と色で構築される快楽の世界に逃げ込みたいかです。お酒、ドラッグ、タバコなど。そのふたつの視点を往復しているような感覚です。
―どちらの方向へ意識を向けるかですね。
行き来しながらどっちを選ぶかね。ほとんどの人がそうだったように、若い時は世界がとてもはっきり見えています。苦難も、理不尽な部分も感じています。貧困、環境、政治などに対する憤りもあるし、若いからエネルギーに満ち溢れていて、だから外に出て少しでも忘れようとする。飲んで、遅くまで起きて、音楽を大音量で聴いて、その意識から逃げる。多難なこの世界がはっきりと見えてしまう現実と、そこから逃げようとする気持ちの狭間を写し出そうと思ったんです。
―いまお話いただいたことは、その後の『American Night』(SteidlMACK、2003年)にも通じると思います。『American Night』の白い写真は、人々の見る行為に対する抵抗にも見えます。人はよく自分が見たいものを見ようとしますが、実際には自分では何が見えているか気づいていない、といったような。なぜこのようなシリーズを制作されたのですか?
『American Night』を作っていたのは、アメリカに移住はしていなかったものの、頻繁に行っていた頃でした。“Elephant in the room”ということわざを知っていますか? 誰も話そうとしない大きな問題のことを言います。例えば誰かの家に招かれて、そこに到着したら部屋の真ん中に大きなゾウがいる。けれど客はみな天気の話などしかしないで、ゾウには目もくれない、という意味です。アメリカでは社会的な貧富の差、特に黒人系やヒスパニック系アメリカ人の貧困がそうだった。誰もその現実に目を向けたくなかったし、誰もその話をしたくなかったんです。
―近年の情勢もいまだにそうですね。
貧困や社会的な分裂のようなテーマはよくモノクロで撮影され、影が多くて暗い写真が素晴らしい作品とされていました。このシリーズはその真逆をやったので、これらの写真はとても珍しかった。単純に過度に露光しただけなのですが、すべて明るく、何もよく判別できないようにしたんです。フィルターでも薬品でもなくただ単に、しぼりからカメラに入ってくる光量が多すぎるだけなんです。
―あなたの作品はイギリスのニュードキュメンタリーなだけではなく、コンセプト重視の作品が多いですね。
そうかもしれません。でもそのコンセプトは作りながら浮かび上がってきます。座ってコンセプトについて考えぬいたものを外で撮影するのだけではなく、この世界と自らが関わっていくことで生まれます。
―いまの時代、特にデジタルカメラだとそこにコンセプトがなくても何でも撮れてしまいます。しかし、あなたの写真にはいつも異なる視点があると同時に、コンセプチュアルですよね。そのあたりのバランスはどう意識されていますか?
正直わかりません。作りながら考えています。この世界が私に見せてくれるものと、自分の意識が理解するもののバランスだと思います。例えばこの世界についてある賢いアイディアを思いついたとする。そして外に行ってこの賢いアイディアを表現できるよう写真を撮る。でも何かうまくいかない、というのはこの世界はまったく協力的でないからです。でもそこで、広い視野と探究心を持って外に出てみる。そしたらこの世界は私が思いついたくだらないアイディアよりもっと面白いものを見せてくれる。結局は自分の目と頭の両方を使って制作する必要がある。そのバランスはやってみるしか、他にわかりようがないんです。答えとなる魔法の言葉は存在しません。
―あなたの評価を決定づけた『A shimmer of possibility』(SteidlMACK、2007年)の頃には、似たようなプロジェクトをまったく別のアプローチで表現していますね。
『American Night』『A shimmer of possibility』と、ニューヨークを題材とした『The Present』(MACK、2012年)ですね。『American Night』は、アメリカでの目に見えない社会的分裂をテーマにしています。『A shimmer of possibility』は“視覚的な俳句”をテーマに作っていて、日常の断片を途切れ途切れに写していったシリーズです。例えばバスを待つ人、草刈りをしている人、買い物をしにいく人、タバコを吸っている人などの、とても一般的な光景を、断片的に短いシークエンスとして羅列しました。『The Present』はニューヨークの街の中で撮影していて、フレームの中に人が入ってきて、一瞬焦点が合います。そしてまた次の人が来ます。あたかもこの枠の中が舞台やステージのように。
この3作品は、よくよく見てみると、『American Night』では絞りを開いて光をたくさん取り入れて撮影しています。『A shimmer of possibility』ではシャッタースピードを使って、時間を短く切っています。『The Present』は、フレームの中を人が自由に行き来しているので、焦点についてです。絞りとシャッターと焦点が、カメラで写真を撮る際の3つの調整要素です。ひとつのシリーズはカメラ機能の一部分に紐づいています。絞りは光、シャッターは時間、そして焦点は自覚、あるいは意識と考えるともっと面白いですね。このカメラの要素ひとつひとつが、それぞれの写真の大切な要素とつながっている。と同時にアメリカでの社会状況を示唆しています。
―アメリカはいつでも国の構造、融通のきかない構造が問題になっていますね。白と黒で分けられていてグレーゾーンがない。あなたの作品は写真という構造や観念の分解を試みているように思えます。そういうお考えはお持ちですか?
とりわけそういう風には考えていません。単純に自分が面白いように制作しています。ただその後の作品はもっとパーソナルなものになってきました。特に『Does Yellow Run Forever?』(2014年)、『Paris 11-15th November』(2016年)と『Mother』(すべてMACK、2019年)あたりからは写真の構造に言及する部分が減り、もっと家族に焦点を当てるようになりました。『Does Yellow Run Forever?』は私のパートナーの話で、『Mother』は母についてです。最近では、社会的問題を積極的に取り扱ったドキュメンタリーから、どんどん自分の人生や家族へと意識が向いて行きました。
―なぜ最近はパーソナルな作品へと移行したのですか?
歳をとったからですね(笑) 。
―出版についてもお聞きかせいただけますか? あなたのアーティスト活動の中でとても重要な要素だと思います。
最初の3冊は自費出版でした。1982年の段階では誰も私の作品に興味を持っていなかったので、出版をしてくれなかったんです。そこから当時の写真界の王様のような存在だったScaloのところに行って、ウォルター・ケラーと出会いました。そのScaloが小規模の印刷所を見つけて、それがSteidlだった。そしてマイケル・マックがSteidlとSteidlMACKとして一緒に仕事をしていて、彼はそこのディレクターでした。その時に私も一緒に仕事をするようになりました。そして彼はいま、自身の出版社MACKを立ち上げ、私の本を出版しています。
―Scaloとの仕事はどうでしたか? 私たちの時代から見ると、Scaloは本当に素晴らしい本の数々を出した出版社だという印象です。
素晴らしかったです。印税は一円ももらえませんでしたが、本が作れましたからね。
―MACKのディレクターである、マイケル・マックとの仕事はどういう流れで進められましたか?
彼はとても協力的です。彼以外に、白い写真ばかりの『American Nights』や、あまり劇的な展開がない12冊の『A shimmer of possibility』を出版してくれる人は思いつきません。彼は理解し、やり遂げてくれます。本当に素晴らしいです。
―『A shimmer of possibility』を作る際、マイケルは最初から12冊出版することに興味を持っていましたか?
最初から協力的でした。最初は10冊の予定で、9冊はもう決まっていて、最後の10冊目を決める時に彼に3案提案しました。すると全部出版し、12冊にしようと言われたんです。
―素敵ですね。あなたの写真集にはとても美しいシークエンスがありますが、ご自身で写真の順序など決められますか?
すべて自分でやります。素晴らしいことに、最近のテクノロジーのおかげで随分楽になりました。PCひとつあれば本が一冊作れます。どう流通させるかが難しいかもしれませんが、本は作れる。それによって写真家の間で色々な交流が生まれています。ギャラリーに所属していないかもしれないし、無名かもしれませんが、本が良ければ人はそれを評価します。
―出版社がこんなにも多いいまの時代で、ここまで自己出版やZINEが増えているのも面白いですね。
ここ10〜15年は、素晴らしい時代だと思います。主流な出版社だけではなく、色々な人がいい本をたくさん作っています。例えば試しに10冊ダミー本を作ってみて、それがよかったら出版してくれる人が出てくる。
―ご自身でもたくさんの本をチェックされていますか?
本当に買いすぎていますね。パリフォトなどに行った時に一番楽しみなのはブックフェアです。
―本についてお話ししていただきましたが、展示についても聞かせていただけますか?「A shimmer of possibility」(MoMA 、2009年)や「The Present」(Pace Gallery 、2012年)、「Does Yellow Run Forever」(Pace Gallery、2014年)は、全部異なる展示でした。展示の仕方もとても独特ですが、その辺りについてもう少し詳しく話してもらえますか?
基本的にはその空間を大切にするようにしています。本の中でやるべきことと壁面でやるべきことはまったく違うので。そしてすべての展示は少しずつ違います。「A shimmer of possibility」では色々な配置を試しました。上に置いたり、下に置いたり、小さくしたり部屋の角を使ったり、ギャラリストとうまくまとまるように試行錯誤しました。例えば「The Present」は写真を地面の近くに展示しています。

ポール・グラハム「a shimmer of possibility」(MoMA、2009年)

ポール・グラハム「a shimmer of possibility」(MoMA、2009年)

「Paul Graham: The Present」(Pace/MacGill Gallery、2012年)
―作品の制作をしている際に、展示や本のことも考えて制作していますか?
制作しながらつながっていく感じです。例えば『The Present』は観音開きが多くなっています。写真が一度隠れて、そしてまた現れる、その繰り返しです。とても印刷が難しかったです。それにまだ話していませんでしたが『Films』(MACK、2009年)もありますね。
―ぜひ聞かせてください。
これを作っているのはアナログからデジタルへ移っている時でした。『A shimmer of possibility』(2007年)ではまだフィルムを使っていましたが、何枚かはデジタルのものを選んでいます。カメラはCanonとPhase Oneを使っていました。
『The Present』(2012年)はすべてデジタルで、Phase Oneを使っています。ある意味ここでフィルムから離れた感じです。『Films』は抽象的なイメージのように思えますが、実際はとても科学的で、これらのノイズはフィルムの粒子なんです。『A1-The Great North Road』や『Empty Heaven』、『End of An Age』を撮っていたときのフィルムのかけらを寄せ集めて作りました。
―ちょうどKodakの業績があまり良くない、2009年に出版されましたね。
「Eulogy」という言葉があります。さようならを伝えるスピーチの意味です。あの頃はちょうどフィルムが終わりかけていた頃でした。だから「フィルムにさようなら」ということになりますね。まだ時々フィルムは使いますが。
―あなたのタイトルはポエティックなものが多いですが、どういうタイミングでタイトルは決められますか?
本によりますね。『A shimmer of possibility』はいいタイトルだと思います。『The Presents』も。『Paris 11-15th November』はそうでもないですね。『Does Yellow Run Forever?』もいいタイトルですね、でもこれはある友人が書いた歌から来ているんです。40年ほど前に彼が書いた、確か1980年頃のブリストルのバンドの曲のタイトルです。
―タイトルがどのように生まれるのか、とても興味深いです。『The Whiteness of the Whale』(MACK、2015年)は、ハーマン・メルヴィルによる小説『白鯨』(1851年)からですよね?
有名な章のひとつで、写真集の中にもこの章を入れています。『American Night』は、実はフランス語の“La nuit Americaine”から来ています。英語だとあまり良い響きではなくなってしまうのですが、私がフランス語を付けているとカッコつけている感じがして。元は映像撮影のテクニックのひとつで、昼間とか明かりが多いときに夜のシーンを撮影するために、たくさんのフィルターを介して暗く撮ることを言います。例えばフランソワ・トリュフォーがこの手法で映画を撮っています。英語だと“Day for night”です。
―作品にはよく映画のような雰囲気がありますね。『A shimmer of possibility』と『The Present』は色々な人の、例えば違う国や、大陸に住んでいる人についての映画のようです。『A shimmer of possibility』では、あなたの写真の撮り方は、被写体にどのように近くかによってその感覚が生まれていると思います。ある種のパフォーマンスですね。一方『The Present』ではニューヨークでカメラをセットアップして、被写体の人々が自らカメラの前で動いてパフォーマンスをしているように思います。
そうですね、でも『The Present』は三脚を使っているわけではないんです。なので私も少しずつ動いています。本当に少しずつですが。
―『The Present』では、人々がフレームに入ってきて、『A shimmer of possibility』ではあなたが動いて被写体をフレームに収めている感じがします。普段よく映画を見られますか?
映画は大好きで、昔は映画館に週2、3回は通っていました。ただ大事なのは、私は映画を作る人間ではないし、たったひとつの物語の流れに縛られたくないんです。そういう意味で一枚の写真がひとつのストーリーラインに縛られないのが好きなんです。色々な物語の可能性があるということが。そういう意味で非物語的で、映画とは真逆なんです。
―最新刊の『Mother』はどのような作品でしょうか?
私の母のポートレイト写真集です。90歳でいまは養護施設にいます。今回は彼女がいつも同じ椅子に座っている姿を、大体同じ場所から2年かけて撮影しました。彼女はほとんどの時間眠っていますが、少しずつ焦点が変わっています。服も一日ずつ違う色です。一人の老人の人生が指の間をすり抜けていくような光景で、美しくもどこか悲しい感じの作品です。今回は中判のデジタルカメラで撮影しました。時々焦点が合っているのが1本の髪の毛だったり、まつ毛、爪、腕の肌の一部分やボタンから垂れ下がっている糸だったりします。とても狭い焦点で、他はぼやけていて、この小さなディテールから彼女のいままでの人生の歩みを見せています。
| タイトル | 『Mother』 |
|---|---|
| 出版社 | |
| 出版年 | 2019年 |
| 仕様 | ハードカバー/60ページ |
| URL |

ポール・グラハム | Paul Graham
1956年、イギリス出身。ニューヨーク在住。2009年のニューヨーク近代美術館での個展や、2010年のホワイトチャペル・ギャラリーでのキャリア中盤の作品を集めた回顧展で知られる。また、第49回ヴェネツィア・ビエンナーレや、テート・ギャラリーが20世紀の写真家をテーマにして主催した「Cruel and Tender」などの著名なグループ展にも参加している。写真集も20冊以上出版しており、代表作に2008年出版でパリ写真賞の過去15年で最も価値ある写真集として選出された『a shimmer of possibility』がある。グッゲンハイム奨励金やドイチェ・ベルゼ写真賞のほか、写真界最高の栄誉とされるハッセルブラッド国際写真賞など、受賞歴も多数。
2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。