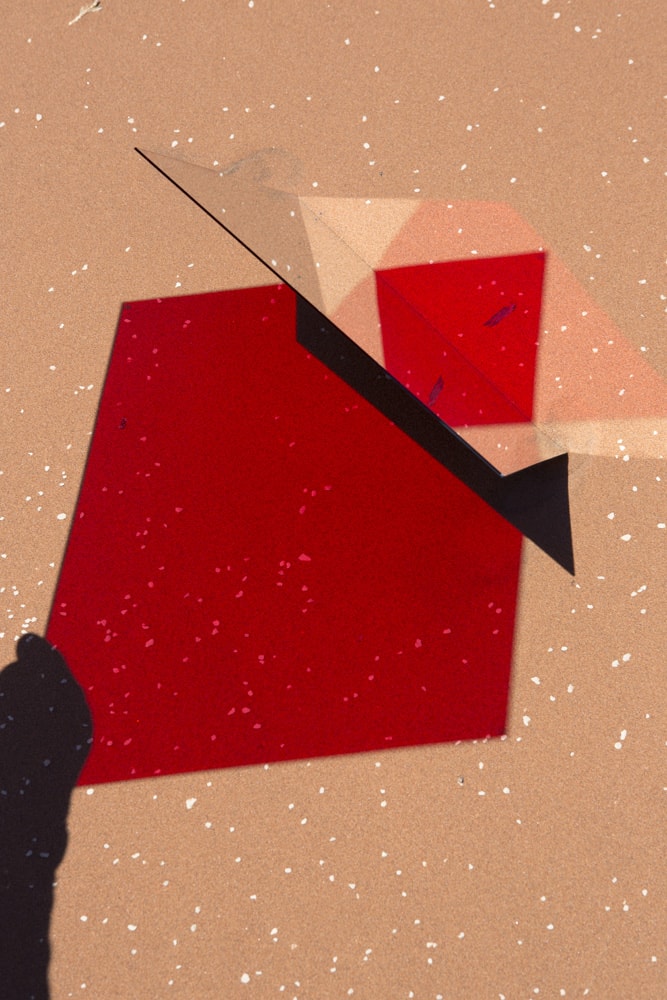ヴィヴィアン・サッセンの作品を象徴する、まばゆい光と色濃い影。 幼少期を過ごしたケニアでビビッドな色彩に囲まれて育ち、 その頃の記憶を拠りどころにしながらファッションと写真を学び、父の死を経て、 ただ美しいだけでなく、生と死が隣り合わせで存在するイメージを生み出した。 最新作を起点に彼女の生い立ちを振り返り、見る者に解釈を委ねる唯一無二の世界観の裏側まで迫る。
文=ジョアナ・クレスウェル
写真=西堀綾子
1678年、フランス王ルイ14世が建築家のジュール・アルドゥアン=マンサールに、あらゆる面で想像を絶する繁栄の象徴となるように、贅を尽くしたきらびやかな空間を造ることを命じ、ヴェルサイユ宮殿の「鏡の間」の建設が始まった。
吹き抜けの天井はフランスの栄光を描いた絵画で埋め尽くされ、アイボリーの石像や金箔を施したブロンズ像が飾られた部屋の真ん中には、氷の彫刻のような重厚なクリスタルのシャンデリアが低く、吊り下げられた。しかし、何よりも難題だったのは、357枚もの鏡を用意することだった。この部屋のビジョンを明確に描いていた王は、フランス製の素材のみを使うことに固執したが、その当時、腕が確かな鏡職人はヴェネツィアにしかいなかった。
鏡の製法を独占しようと考えたヴェネツィア政府は、職人たちに秘密厳守を誓わせ、国外で鏡を作った者は処刑すると脅していた。それにもかかわらず、フランス政府は輝かしい名誉を約束して最高の職人たちを説得し、こっそりと国境を越えさせたのだ。こうして彼らは国を捨て、生涯をかけて限りなく美しいものを作り上げたのである。
ヴェルサイユ宮殿の歴史上、些細な出来事である鏡の逸話に冒頭で触れたのは、筆者がヴィヴィアン・サッセンについて調べる中で知ったこの物語が、その後数週間かけて彼女の人生についてまとめている間も頭から離れなかったからだ。優れた建築の多くは、このような人間の物語の上に築かれたのではないだろうか。
重要なものもそうでないものも含め、歴史とは個人の物語の中で展開してきたが、すべての努力も存在も、最後には鏡に息を吹きかけたときの湯気のように、跡形もなく消えてしまう。2019年に半年をかけて、宮殿が閉鎖されている間に撮影を行う許可を得たサッセンは、最新作「Venus & Mercury」を制作した。
そしてサッセンもまた、これまで大々的に語られてこなかった物語に、特に惹かれたという。彼女はマリー・アントワネットが恋人に宛てて書いた私的な手紙を読み、写真に収めた。歴史に埋もれた女性の話を掘り起こし、アイボリーの石像のフォルムを用いてコラージュし、その上に彩色を施した。また、偶然出会った宮殿の外にある街で生まれ育った若い女性たちを、実在の人間—生身の身体—として写真にとらえている。
サッセンは、宮殿での体験を熱っぽく話してくれた。プロジェクトを開始したときから、イマジネーションが湧いてきて止まらなかったという。「ヴェルサイユ宮殿で一日中、それも自分以外誰もいないときに撮影できたのは、大きな特権でした。私はすべてのドアを開けて、かつて公開されたことのない秘密の部屋をのぞくこともできました。召使いの少女が眠った屋根裏部屋の小さなベッドに横になってみたり、ル・アモー(宮殿の一角に作られた小さな村を模した庭園)のマリー・アントワネットの私室に入ったりしました」。
それは説明し難く、気のせいかもしれないというが、サッセンは宮殿で電気が体を貫くようなエネルギーを感じたという。鏡の間に足を踏み入れたときも、その強いエネルギーに魅了され、ヌードのセルフポートレイトを撮りたいとすら思ったと話す。「別の日にまた行って撮影しようとしたのですが、なんだかむなしさも感じて、結局はやめました」とサッセンは笑うが、筆者としては、これまで自己を探求する作品を多数生み出してきた彼女自身のポートレイトを撮っていたとしたら、それはいろんな意味で新作に合っていたのではないかと思う。
この作品について鏡から言及し始めるのは、サッセンにとって鏡とは、彼女が “別世界”と呼ぶものの強力なメタファーだからである。サッセンいわく、“別世界”とは、意識の外側に存在し、眠っているときや遠い昔の記憶を思い出しているときに現れるという。
「昔から私たちの理解が及ばないものに惹かれてきたので、別世界に足を踏み入れさせてくれる鏡は私にとって重要なもの。私はイメージに文脈を詰め込みすぎないように、いつも気をつけています。より抽象的なイメージにするために、文脈は取り除く。既にあなたの中にあるものを映して見せるという点で、私のイメージは鏡の間に似ています」
これまでに16冊の写真集を出版してきた48歳のサッセンは、既に自分の中にあるものにインスパイアされながら、鏡像や分裂した自己、夢や悪夢、記憶の中の瞬間や想像の世界に存在するものをテーマに写真を撮り続けてきた。彼女の衝動がどこから来ているのかを理解するには、彼女の人生を始まりから見ていかなければならない。
いまでも夢に見るケニアという“故郷”
サッセンは1972年にソーシャルワーカーの母と医師である父の下にアムステルダムで生まれ、2人の弟がいる。どんな子どもだったかと尋ねると、内気で人見知り、空想に没頭する傾向があったという。いつも何かを作ったり、描いたりしていたそうだ。2歳になると父親の仕事の関係で、ケニア西部の小さな村ニャボンドに家族全員で引っ越し、5歳になるまでそこで過ごした。父親は現地の病院で働き、近所にはポリオの診療所があった。サッセンの幼少期の記憶には、病気や障害を持った患者を見かけた体験が色濃く残っている。「父が医師だったことは、私に大きな影響を与えたと思います。父が生と死に関わっていることに感銘を受けていました」。
彼女とのメールのやりとりにおいて、サッセンが「生」と「死」という単語を大文字にしていることが目に留まった。それはちょっとした意思表示だが、彼女がこれらを重視していることを意図的に伝えようとしていると感じた。幼い頃、夕食時に父が母に向かって仕事のことを話すのを耳にしたり、緊急の呼び出しに応じて家を飛び出していく父親の姿を見ると、怖くなることもあったとサッセン。「そのときの経験から、大きくなるにつれて死を恐れるようになったんだと思います」。
サッセンは、人格形成に大きな影響を与える幼少期を過ごしたアフリカへの深い愛着を持つ。ケニアの思い出は「光、影、色、人々。黒いインクで塗られたような真っ暗な夜と満天の星空」として永久に心に刻まれ、いまでもサッセンはその場所を夢に見続けている。インタビューの中で、彼女はケニアでの子ども時代のことを「マジカルな思考が育まれた時期」と呼んでいた。彼女のビジョン、その後何十年にもわたってイメージを生み出すこととなるファンタジーの基礎が形成された時期であった。
サッセンは家族でオランダに戻ってきた日のことを思い返し、「スキポール空港に着いたのは夜でした。空港の明かりを見て、空の星がすべて地上に落ちてきたと思いました。オランダでは長い間ずっとパラレルワールドに閉じ込められているような気がして、ケニアに恋い焦がれていました」と話す。
鏡と別世界の概念は、ここにも見られる。多感な時期に人生を根本からひっくり返されると、存在すべきではない場所にいるような奇妙な感覚に悩まされることになる、とサッセンは過去を振り返る。オランダを去る前のことを思い出すには彼女は幼すぎたし、帰国したときには、ケニアを恋しく思わずにはいられないほど成長していたのだ。しかし、大人になったいまケニアに戻ったとしても、彼女はアウトサイダーでしかない。ケニアでの日々を昨日のことのように思い出せても、彼女はケニア出身として受け入れてはもらえない。それは、生まれてこのかた掻き続けてきたかゆみのような、奇妙な感覚である。
撮る側へ転身することで、手に入れたパワー
大学でサッセンはファッションを専攻し、後に写真と美術に転向する。この時期はヌードやセルフポートレイトを撮りまくり、自分自身のセクシュアリティを探求し、初めての恋愛をしたという。アーネムの美大生だった頃、いまでは非常に有名なデザイナーになったヴィクター&ロルフの卒業コレクションのモデルを務め、その後も彼らの初期のコレクションでランウェイを歩いたり、映画やキャンペーンに出演したりした。
長身・金髪で目が大きく、控えめな性格だが変わった自意識を持っていて(当時の自分をサッセンは「シャイな目立ちたがり」と評している)、約4年間にわたりファッションモデルとして多くの写真家に撮影された。
その後、彼女は、撮影時に自分の体を自分でコントロールできないことに違和感を持ち、モデルであることをやめた。「カメラの後ろに男性がいると、必ず緊張関係のようなものが生まれます。それは性的な衝動に基づいていることもありますが、大抵は力関係です。男性と女性の間の力関係が面白くて、自分から求めたこともありました。でも、それは簡単なことではなく、決して心地いいものではありませんでした」。
それ以降、サッセンはカメラの後ろに身を隠し、写真家としてのキャリアを築くことに専念した。初めの頃はなかなか芽が出ず、結婚式やイベントから企業の制服の撮影まで、お金のためのつまらない仕事でもなんでもやったという。雑誌『the Gentlewoman』のインタビューでは、保険会社のオフィスを撮影するためにオランダ中を回ったときのことを話している。
「地図とカメラを持って折り畳み自転車であちこちの街を巡り、醜いオフィスの建物を撮りました」。サッセンはどんな仕事でも自分の腕を磨くために一生懸命取り組み、仕事を終えて家に帰ると、『i-D』や『The Face』などのファッション誌を読み漁り、シュルレアリスムや影について書かれている文献を片っ端から読んでいたという。
その頃からサッセンは、ファッションとアートの間を行き来する、幅広いジャンルに興味を持っていた。後には、ルイ・ヴィトンのキャンペーンから、ヴェネツィア・ビエンナーレまで、両方の分野で認められるようになり、ファッションでは自分の外向的な部分を、個人的な作品では内向的な部分を表現するようになったと話す。
人生と作品に大きな影を落とした死
22歳のときに、サッセンは父親を自死で失う。それは彼女の足元が壊れゆく出来事であった。この体験はそれから何年も亡霊のように彼女の人生に影を落とし、彼女が作ったほぼすべての作品に、その影響が入り込むこととなる(これをサッセンは“潜在的な死の要素”と表現する)。2017年にはオランダの雑誌『See All This』でのインタヴューで、彼女は父の死を知った日のことを話している。「ユトレヒトの美大の暗室にいると、ワークショップのアシスタントが私を探しに来て、『すぐに家に電話をしてください』といわれました。彼が私を事務所にひとり残していったので、何かおかしいと感じました。弟が電話に出たとき、母に向かって『教えたほうがいいかな?』と尋ねているのが聞こえました。それから彼は『お父さんが死んだ』と私に告げました。あっけないものでした」。サッセンは一瞬、身動きもできずに立ち尽くし、突然激しい怒りが込み上げてきたという。
彼女はテーブルの脚を蹴ると、押し寄せる怒りの波を感じながら部屋をぐるぐる歩き回り、その後は、心が空っぽになったような気がした。部屋の外で待っていた友人に彼女は、弟と同じように、何の感情もこもっていない短い言葉で伝えた。「父が死んだ。窓から落ちて」と。
暗室にいたときに悪い知らせを聞くというのは奇妙な体験ではないか?と暗室という場所の意味について対話を始めてみた。まず筆者は本棚を漁り、「暗室は水の性質を持った子宮のような場所、世界から隠れて涙を流し、感情を処理するための場所」と述べたドイツ系アメリカ人のアーティスト、エスター・タイヒマンの言葉を引用した。
するとサッセンは、「この言葉には、とても共感できます。いま思えば、父を亡くして以来、暗室で長い時間過ごすことはなくなりました」と彼女は物思いに沈みながら言葉を返した。それから、2年前にイギリスで、写真家の故リー・ミラーの暗室を訪れたときのことを語ってくれた。「そこにいるととても悲しい気持ちになり、暗室から出ると、突然体中の力が抜けてしまいました。それは、私が押さえ込んできた不安や苦悩に関係しているのかもしれません」。場所は私たちの記憶に残る。それは、ある場所で過去に感じた感情は、そこに戻れば蘇るという心理地理学の基礎でもある。だからこそサッセンは、アフリカの景色と人々に強く惹かれるのだろう。
卒業から数年後の2002年、サッセンと夫のヒューゴは、アフリカ各地を巡る旅に出た。東部を周り、彼女が子ども時代を過ごしたケニアにたどり着くルートだった。彼女は、「あの旅では、作品を作ろうとは思っていなかった」という。しかし、アフリカを再訪してみると、幼い頃に暮らしたこの土地に見え隠れする、鮮明な夢のようなシーンが、おのずから姿を現し始めた。
2008年に出版された彼女の初めての写真集『Flamboya』は、この旅で生まれた。このシリーズに収められたイメージは、まるで幻覚のようだ。2011年に刊行した『Parasomnia』—医学用語で睡眠時随伴症のこと—では、学生時代に生死をさまよった体験に立ち返りながら、「眠りと夢」というテーマを探求した。口や目が覆われていたり、うつぶせで水に浮いている体など、どのイメージも美しく魅力的だが、死後の世界を感じさせ、不安をかき立てる。また、異様なまでの息苦しさも、ひしひしと伝わってくる。
突然の死から数日後、サッセンは父親に別れを告げることとなった。書斎に安置された遺体の損傷は激しかったが、同時に美しかったという。「私は部屋に入り、父の隣に座ると、冷たくなったその額に手を置いて、語りかけました。それからタイマーでセルフポートレイトを撮りました。そこにはほとんど何も写っていません。ただ、棺と花の横に私が立っているだけです。最後にもう一度、父と一緒に写りたかった。その後は、気持ちが落ち着きました。あれは、私なりのさよならでした」と書かれたサッセンの過去のインタヴューを読み、筆者はサリー・マンが撮った安置所の遺体や、病院で亡くなったばかりのピーター・ヒュージャーを撮ったデイビット・ウォジナロビッチの写真を思い出した。冷たくなった足、開いた口、死者に対する揺るぎない愛。亡きがらを手放し、亡くなった人を思い出に変えるのは、たまらなくつらいことだろう。
このような行為には、潜在的なフェティシズムの要素がある。私たちは愛しているけれどいつまでもとっておけないものや、かつて所有していたけれど二度と再び手に入れることができないものを写真に収める。サッセンは遺体を撮った写真に魅了されてきた。彼女の作品もまた、この相いれない思いによって作られている。「死や未知のものに対する恐怖、それと同時に感じる、ある種の抱擁によって他者と完全に一体化したいという願望は、私の作品に繰り返し登場するテーマ」というサッセンは、最後に「自分がひとりぼっちにならないように」といい足していた。
詩人のアンネ・カールソンは、『The Glass Essay』で、長い間彼女を苦しめてきた深い喪失感と切望について書いている。何かを失ったときに一番つらいのは、「来る日も来る日も、その日が繰り返されるのを見る」ことではないかと。その感覚について彼女は、「今日という日の底に、あの日が流れているのを感じます。まるで古いビデオテープのように」と記している。同様に、サッセンが過ごした日々の底には、父親の亡くなった日が流れ続けている。そして身を切るような喪失感が、長い月日の中で彼女の美的感覚を形成し、彼女の写真には決して消えることのない影が静かに映り込んでいる。2015年に『Umbra』で父親の死が残した影を分析しようと思い立つまで、サッセンはこの影を穏やかに解きほぐそうとする作品を作り続けた。
母となったサッセンの変化
サッセンは、美術史家ヴィクトル・ストイキツァの『A Short History of the Shadow』をはじめとする影について書かれた本や、カール・ユングの影と無意識についての理論を読んだが、それらはあまりにも抽象的な内容であった。サッセンは、自分でも認めているように、直情的で美を大切にするアーティストである。彼女は参考書を捨て、自分の内面への旅に出かけた。「私は『UMBRA』で、父の死を消化することができました」と、当時の彼女は述べている。『UMBRA』は、長い間彼女の心を占めてきた悲嘆のプロセスの最終段階であった。
2〜3年前、サッセンに、自身のキャリアにおいてどのような段階にいると感じるか、尋ねたことがあった。「半分くらいまでは来たと思います。私にとって『UMBRA』は、前半の締めくくりを象徴していました。当時は何を目指しているのか理解していませんでしたが、あの作品は、ある種の自己分析の旅になりました。ひとりの人間として、少し落ち着いた気がしますし、以前よりずっと幸せです。自分らしくいることに慣れてきたと思います」。
そして今回もまたサッセンに、同じ質問を投げかけた。「ええと……」と話し始め、「『UMBRA』が完成したときは、いいたいことはすべていい尽くしたように感じて、心がすっきりしました。いつ死んでもいい、二度と作品を作らなくてもいいというふうに」と話すサッセン。そして「もちろん、本当はそうではないけれど」と続けたが、アーティストとして、象徴的な意味で転換期となったのだろう。『UMBRA』によって思いもしなかった場所につながる新しい扉が開き、彼女の人生がもう一度花開き、作品も進化していくことを、当時の彼女はまだ知らなかった。2008年にサッセンは息子のルシウス(ラテン語で“光”という意味)を出産する。これは、彼女の最初の写真集が出版された年でもあった。彼女の作品と人生は常に交差し合い、どちらかがもう一方に影響を与えたり、鏡のように映したりしているようだ。母親になったことで、世界のとらえ方がどんなふうに変わったのか尋ねた。
「複雑すぎて、うまく答えられないかも」といいながらも、ルシウスが生まれてから「生きることに対する恐怖の大部分が消えました。ついに自分の運命を見つけたような気持ち、帰属意識を感じることができました」と話した。『UMBRA』以降サッセンは、母親としての体験を基にした作品を多く生み出す。「写真に色を塗ったり、コラージュを作ったりし始めました。心から楽しみながら、実験的なやり方でやっています。多分、私はようやく父親の死に代わるものを見つけたのだと思います。そして、作品制作の中で生まれ変わることができたのかもしれません」。
濃密で目がくらむようなサッセンのコラージュは、女性らしさと何かを産み出す力、子どもを宿す意味を探っている。そして、そこから生まれた作品のひとつが「Of Mud and Lotus」である。「心理学的な観点から理解しやすい作品だと思います。平凡で人間的なテーマから作品を作り出し、ありふれた、型通りの表現を超えた、意味のある何かに変える作業は難しいことですし、アーティストであっても常に成功するとは限りません」。
しかしサッセンは、そこに到達するまで努力し続ける。『UMBRA』の中に、ビーチでサッセンの隣を走るルシウスの写真がある。彼の小さな体を包み込む彼女の影は、私たち自身の影もまた、愛する人たちの体験によって影響をおよぼされることを教えてくれる。
このエッセイを締めくくるにあたって、ヴェルサイユ宮殿について私が学んだ、もうひとつの事実に触れておきたい。17世紀当時の庭園には、気分が悪くなるほど強い臭気が漂っていたという。楽園のように美しい場所に漂う、息が詰まるような強烈な臭いは、サッセンの作品に通じるものがあるといえるのではないだろうか。この話は、彼女の作品を見ているときに感じる、共感覚的な喜びについて考えさせられる。それは彼女が自分の思い通りに、巧みに表現している感覚や感情の激しさによってもたらされると同時に、イメージの表面に波紋のように広がる彼女の個人史の暗い部分によって、もたらされるものでもあるのだ。
「私は底流にあるものを隠したり、それを探しに行くのが好きです。見る人は、それが何か、自分で想像するしかありません。私は抑制された、控えめなやり方で、多くのことを表現しています。私の作品は確かにドラマティックかもしれませんが、私自身は唯美主義者であり続けたいと思います」と彼女は数年前にいっていた。あまりにもまぶしい光に満ちたシーンにおいては、あらゆる類いの影を隠すことができる。サッセンは、そのことをよくわかっているのだ。
ヴィヴィアン・サッセン|Viviane Sassen
1972年、アムステルダム生まれ。幼少期をアフリカで過ごし、ユトレヒト芸術大学、アーネム芸術アカデミーでファッションデザインと写真を学ぶ。その後、ファッション写真家として『Purple』『VOGUE』『Dazed & Confused』などの雑誌で活躍するほか、Miu Miu、ルイ・ヴィトンほか数々のファッションブランドのキャンペーンビジュアルを撮影。2011年にニューヨーク近代美術館の「New Photography」展に参加。同年、ニューヨーク国際写真センターの「Infinity Award」ファッションフォトグラファー部門を受賞した。2013年に第55回ヴェネチア・ビエンナーレ「The Encyclopedic Palace」に出展し、2015年にはドイツ証券取引所写真財団賞にノミネートされた。主な作品集に、『Flamboya』(contrasto、2008年)、『Parasomnia』(Prestel、2011年)、『Umbra』(oodee、2014年)、『Pikin Slee』(Prestel、2014年)、『Of Mud and Lotus』(アートビートパブリッシャーズ、2017年)など。
ジョアナ・クレスウェル|Joanna Cresswell
ロンドンを拠点とするライター、編集者、キュレーター。写真とカルチャーを専門とし、多数の媒体に寄稿するほか、これまでに『Unseen Magazine』『Self Publish, Be Happy: A DIY PhotoBookManual and Manifesto』、Apertureが刊行する『PhotoBook Review』など、多数の出版物を編集。The Photographers’ GalleryやThe Whitechapel Galleryなどでのプロジェクトのキュレーションも手がける。