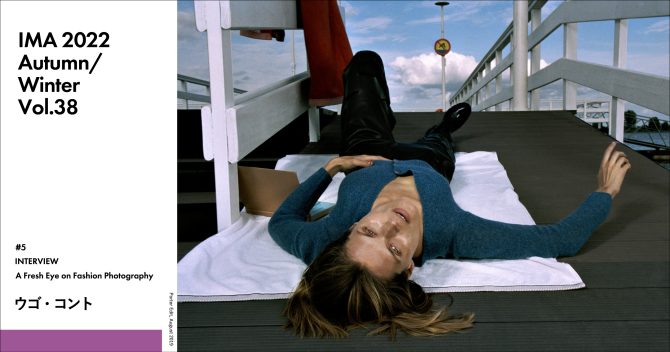東京・南青山にあった「SKWAT/twelvebooks」が東京・葛飾区亀有に移転し、2024年11月2日「SKAC(SKWAT KAMEARI ART CENTRE)」として新たなスタートを切った。位置するのは、JR常磐線亀有駅と綾瀬駅間の高架下、ジェイアール東日本都市開発が運営する高架下スペース「ぽちかめ」だ。SKWATを手掛ける設計事務所「DAIKEI MILLS」とアートブックディストリビューター「twelvebooks」の他、レコードショップ「Vinyl Delivery Service」、カフェ「TAWKS」が入居し、エキシビションスペースも持つ。お店であるように見えるが、実は扱う本やレコードの“倉庫”という。業態もさることながら、立地も珍しい地域。亀有駅から徒歩10数分と決してアクセスしやすい場所ではない同所になぜ移転したのか、SKACを仕掛けた、設計事務所「DAIKEI MILLS」率いる設計者・中村圭佑と「twelvebooks」代表の濱中敦史に概要を聞いた。
取材・文=IMA
―まず、なぜ亀有に引っ越したのでしょうか。
中村:遊休施設や、見過ごしていて本来もっと価値があるものをVOID(ヴォイド)と呼んでいます。南青山では一定の成果を残せたと思ったので、次をどうするか考えた時に、フィジカル的に最も東京のヴォイドに異動したいと考えたのです。
―南青山の施設は、ジェントルモンスターやアクネ ストゥディオズの旗艦店がオープンし、話題のスポットになりました。
中村:価値の転換が起きた時に、そのコントラストが強烈に生まれて、 たぶん街自体が 変わるだろうと思っていました。なのでアートのコンテクストが無く、距離もかなり離れた、アンタッチャブルな地域を可能性として考えていました。
亀有を見つける前年のミラノサローネのサテライト企画「ドロップシティ」にSKWATが招待されたんですが、それは、ミラノ中央駅の高架下での一時的な活用方法を問う、実験的なエキシビションでした。ドロップシティの経験で高架下の面白さ、可能性を感じていて、調べているうちに「ぽちかめ」を発見し、ジェイアール東日本都市開発に正面からコンタクトを取りました。
濱中:当初は数カ月の短期契約の募集でしたが、リーシングが難航していたようでした。そのほころびもある意味ヴォイドと言えます。そこに私たちの提案が通り、今に至りました。SKACは複数年契約で借りることになっています。

積み重なる書籍の山がクールなインテリアとなる。
―本当によく亀有にしましたね。漫画『こち亀』のイメージしかありませんでした。
濱中:恵比寿、渋谷、清澄白河、天王洲、日本橋などいろいろな候補がありました。でもどれも無難な印象でした。でも亀有は周りの誰に聞いても、「何で?」という意見しかなかった。これは考えようによってはものすごいポテンシャルがあるということです。ここからどうすれば人に来てもらえる、また来た人に楽しんでもらえる場所にするかを徹底的に考えていきましたね。
―都心から離れており高架下とはいえ、東京です。それなりの売り上げが必要になるのではないでしょうか?
濱中:それは、twelvebooksもVinyl Delivery Serviceもここをお店とは捉えていません。もちろん店頭で購入できますが、我々にとって用途は倉庫なんです。倉庫としての経費で捉えており、卸やECでの売り上げで十分賄えるようにしています。
中村:売り上げを上げないと維持できないというスタイルは厳しくなってきます。そこの捉え方はかなりジェイアール東日本都市開発と交渉しました。この冬には倍くらいの広さに拡張します。SKACがあることで、この場で協業したいという引き合いもあります。そういったところで「ぽちかめ」に貢献していきます。
濱中:場所の運営は原宿のvacantでの経験が大きいですね。最初は面白いことをできていても月日が経つほどクオリティーとインパクトが下がって来ます。イベントがある日とない日の集客が全く違いました。つまり、何もしない状態でも面白い、そこに行く価値というのを追求しないといけないと思ったんです。
そうすればイベントは本当にやりたいことだけにしぼれる。集客、売り上げのためのイベントはお客さんにも伝わってしまうんですね。twelvebooksは在庫の量だけで圧倒的な空間性があって、十分コンテンツとして成立します。いかにそういった価値を作れるかが大切だと思います。
中村:コンテンツは持続性のレイヤーととらえていて、外側から、倉庫&オフィス、その次が小売り、そして展示(イベント)です。一番外側は無理をしないで日々のルーティンとしてやっていけるもの。これがコンテンツとして成立すれば楽ですから。設計事務所の我々としては素材や什器のモックアップを施設内に据えればコンテンツになりますし、本やレコードは立派なインテリアになります。

レコードを扱うVinyl Delivery Service。
―実際、お客さんの反応はどうですか。
濱中:3分の1から半分くらいは海外ツーリストの方ですね。グローバル単位で比較しても、なかなか他にないスペースだと自負しています。もちろんアート系の方、またSNSを見た若い方、地元の方と様々なお客さんがいらっしゃいます。
中村:東京観光の目的地になるようなスケールと滞在時間がある施設ということは意識していました。
―レファレンスした施設はあったのでしょうか。
中村:概念としてロンドンのバービカンセンターは念頭にありました。ローカルの人も、アートに興味がある人も、目的はそれぞれ違いながら居心地が良いから時間を費やしてくれる場所を目指しました。あと、やっぱり買えることって、日本人の気質からすると安心 材料かと思っていて、先述のレイヤーでいうと、小売りがあって、その中に展示があるという状態にした方が、自然とアートにタッチできます。その方向を作りたかったというのもありました。
濱中:まあ買う、を強調し過ぎると、買わなくても入っていいのかなと不安に思われたりするんで、バランスですね。この場所を倉庫でありながらも開かれた場所としたい思いがありました。なので開業のときは単なるオープンという言葉ではなく、“一般開放”という方がしっくりくると思ってあえて後者の表現としました。
ただ尖った場所にしたいわけではなく、街に愛される場所になりたいじゃないですか。場所柄、普段そんなにアートに興味が無い人でも面白いね、楽しいね、と図書館や公園のように捉えて興味を持ってきてくれるようにしたいと思っています。こういったバランスが、アートのプロから地域の住民、海外観光客といろんな人が来てくださることに繋がっていると思います。

カフェTAWKS。
―そのための本、音楽、カフェのラインアップですね。
濱中:カフェは街の人との最初のコミュニケーションの窓口になります。いきなりアートブックを手に取らなくても、コーヒーを飲みに来ることは手軽ですから。そこから中に入ってくれるかもしれないですし。
中村:自分が興味あるということもありますが、カルチャーを感じるもので構成したかったんです。どれも長期滞在につながるというのも良いですね。
―今冬には拡張するとのことですが。
濱中:まだ始まって半年なんですが、もう場所が足らないという感覚がしています。物理的な場所の意味だけではなく、自分たちがやりたいことのスペースが足りないので、拡張することにしました。嬉しいことに色んな引き合いやご提案を頂くのですが、ただここがブランド街になることは避けなければいけません。
中村:拡張ではもっと現代美術のコンテンツを強化する予定です。美術のファーストステップは初めにつくれたと思っているので、拡張では少しディープなところまで美術を掘り下げたいと思っています。

JR常磐線高架下にあるSKAC。
SKAC
住所:東京都葛飾区西亀有3-26-4
時間:11:00~19:00 ※TAWKS 8:30~18:00(土日祝11:00から)
休業日:月・火曜日
記事内全ての写真 ©2025 Daisuke Shima Photography