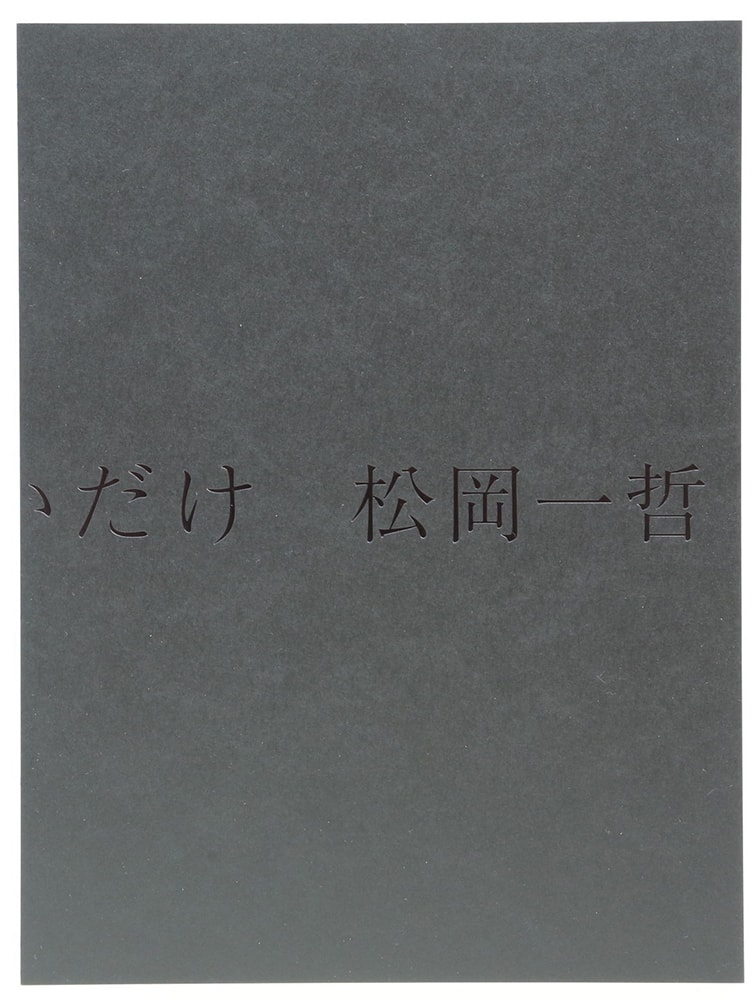タカ・イシイギャラリー フォトグラフィー/フィルムで、ファッションやグラビア、コマーシャルなど幅広い分野で活躍する写真家・松岡一哲の個展「やさしいだけ」が開催された。本展では、子どもを中心に据えながらも滲んだ色彩や錯綜する線、不明瞭な輪郭線などによって写真のなかに広がる奥行きにわずかな錯覚を起こし、平面性を強調する写真表現に取り組んでいる。妻・マリイを中心としたパーソナルな日常の光景をとらえた「マリイ」、そして、松岡の活動全体を象徴する言葉「やさしいだけ」に込めた思いを聞いた。
文=村上由鶴
写真=大竹ひかる
―まず、現在の写真のスタイルに至るまでの変遷について聞かせてください。
自分は、目に見えるものを綿密にとらえるよりも、漂っているなにかみたいなものに真実があるのではないかと思って、それを探し続けて来ました。
―今回の展覧会タイトル「やさしいだけ」はそこから来ているんですね。
自分はやさしいことで損してきている部分もあるし、失敗もしてきているけど、無理矢理強くなったところで強い人には叶わないし、誰かになろうとしてもなれない。結局のところ、自己肯定していく方法だったんですよね。だから、自己肯定という意味においての「やさしいだけ」でもあるし、いまの世の中を見ていて、「やさしいだけ」になって許容することがもっと大事にされてもいいと思って、このタイトルにしました。
―では、「やさしいだけ」になる方法は、写真を始めた頃から?
僕は元々比較や競争があまり好きではありませんでした。どこの社会でも何かを比較して競い合いますよね。自分のほうがものを知っているとか、なにかをより理解できているとか。自分は小学生のときから、自分の意思で徒競走に参加していませんでした。走るのが速いことの意味ってなんだろうって思いませんでしたか(笑)? もちろん写真も、この一枚の四角形のなかでなにかを表現して良いか悪いか判断される世界だから、同じように競い合いはあるように感じます。けど、表現の世界には競争ではない部分が少なからず存在していると、いまでも信じています。
―一方で、一哲さんの写真のなかの被写体の眼差しは、
写真は見返されるものをどう見返すかという行為だと思っています。写真集『purple matter』では、正面から被写体がこちらを見返してくる眼差しばかり撮っていました。そういう強い眼差しを見返していくときに、自分の場合は、にこにこしてただ受け入れるようにしています。例えば、女優さんの圧倒的な美しさを前にしてどう見返すかというときに、自分はただただ”やさしいだけ”のおじさんみたいな感じで受け入れる。そうすると、相手が笑ってくれるんですよね。「なにこの人?」みたいな感じで。その後に、良い写真が撮れることは多い気がします。仕事のときはゆっくり話す時間がないことが多いですが、そのなかでもすっと受け入れてもらえるのは、自分たちだけのコミュニケーションが成立しているからだと思います。
―これまでと、今回の展覧会「やさしいだけ」までで、変わったことはありますか。
今回の展覧会では、自分の感覚を信じてもらって、かなり自由にやらせてもらいました。気づけば子どもの写真が多いですね。さっき、「目に見えないなにかを撮りたい」と話してきましたが、子どもって「目に見えないなにか」ではなくて確実にそこにある物質なので、自分が写真に対して持っている哲学には当てはまらない存在ではあるんです。でも、子どもって動きが自由で、予測できない動きをするのでつい目がいってしまいます。まだ死を意識したことがないからなのか、すごく無垢な強い眼差しでこっちを見てくる。そういうときには眼をそらしたくもなるんだけど、自分はカメラを通すことで見返すことができる。自分の哲学をこえて吸い込まれるものがあるんですよね。

―マリイさんの写真も眼差しが印象的でした。写真集『マリイ』のときには、帯に「ここに写っているすべてがマリイです」とあるように、日常の全てがマリイさんに繋がっていくようなイメージで制作していたんですよね。
自分のずっとやりたかったことが、「マリイ」を作ったことでより見えるようになって、今回の展覧会があります。写真集『マリイ』のほうが先に出ているけど、自分にとっては順番が逆で、今回の展覧会のような表現をずっと構想していました。「マリイ」が自分の表現の“取っ手”のようなものになったんです。例えば、この現実は希望を見いだせるような社会ではないけど、芸術家はものを作るときには、そういう現実に蔓延っている善悪や正誤から離れたい気持ちがあると思うんですけど、写真集『マリイ』はそういう芸術や善悪どうこうも、マリイを前にしたら、なんの意味もないことを表現しています。マリイがぐっとにらんできて、「は?そんなんいいから、早く洗濯してよ」みたいな(笑)。でも、そういう存在が自分のすべてであるし、誰にとってもそういう存在がいれば大丈夫だよ、ということを表現したかった。
―“取っ手”は、具体的にどのようなことですか?
“ひっかかり”ともいうのかな。写真集『マリイ』を作ってくれたデザイナーの佐々木さんが、僕の写真を好きだといってくれていたので、大量の写真を見てもらって、「本作りましょうよ!」と話していたんです。でも、彼に、「一哲くんの写真は、漂っている真実の無限の可能性を、ゆらぎながらとらえているから、まとめて発表した時点でそのなにかが消えていってしまう。純粋で重要な行為だからこそ、本の形態にまとめることがプラスにならないと思う」といわれました。まとめることが写真に失礼だと。僕としては「いや、本作りたいです…!」と思っていたんですが(笑)。でも、マリイを撮り始めて、彼が「一哲くんの写真のなかにマリイという取っ手ができた」といってくれて、写真集を作ることになりました。その話が自分のなかでもひっかかりになっていますね。

『マリイ』松岡一哲(mm books、2018年)
―では、一哲さんの制作のベースのなかに「やさしいだけ」の世界のなかのマリイさんの存在が、作品として写真をまとめるための「取っ手」になったのでしょうか。
写真集『マリイ』には現実の私生活の部分と、そこから離れたいと思う自分の気持ちのどちらも入っています。宙に浮いた世界のなかで無限の可能性を求めても、地上の現実で生きている人たちからしたら何の関係もない。アートはそういうことが常に起こっていますよね。でも、現実から離れたところでいくら芸術とか創作とかいっても、そんなものはその日食べた餃子一個のうまさには叶わないなと思います。
―餃子!(笑)というと、今回の展覧会「やさしいだけ」は、一個の餃子の美味しさに挑むことでしょうか。餃子に勝てないかもしれないけど、餃子に挑んでいく、と。
そうですね。餃子に挑むのが、僕が『マリイ』を作る前からやりたかったことかもしれません。すぐ餃子に挑んで勝った気になるっていうのが僕の昔からの自然な感覚です。芸術としての写真表現が好きだし、そういうものに救われて生きてきた。今回の「やさしいだけ」は、コロナで延期になったりもしたんですが、色々な状況が整って実現して、ようやく自分の表現のスタートに立てた気持ちです。自分がやりたいと思ってきたコミュニケーションができている感じがします。
―確かに、展覧会に合わせて刊行された写真集『やさしいだけ』では、『マリイ』と比べて大幅に写真の枚数も絞られているし、平面性へのこだわりも見えて、改めて「アートとして写真をやろう」という気概を感じます。
今回は、絵のように線と色をどう配置するかにこだわっています。でも、写真のおもしろさはそこに被写体がある以上、永遠の自由が許されるわけではないところ。僕の場合は、仕事でモデルさんや女優さんを撮ることが多いので、被写体となってくれた「彼女の気持ち」が入ってきます。僕は、彼女が嫌だと思うようなものはやっぱり嫌なんです。そこが、写真のいいところであるような気がしています。表現する側が突っ走らないように歯止めがかかる。その中間に生まれる何かが、希望そのものであるように思います。
―「妻を撮る」行為は、日本だと私写真の系譜上に位置づけられますが、一哲さんが撮ったマリイさんの「で、皿洗ったの?」という視線は、かつての私写真にはなかったことかもしれませんね。
昔の写真家って、「やさしいだけじゃだめ」みたいな世界観が強かったと思うんです。男性の撮影者が征服するような感じで世の中をとらえていくような写真表現が多かった。もちろん尊敬もしているんですが、時代は変わってきていますよね。例えば、僕が大学に入った頃は「決定的瞬間」をとらえるのが良いとされていたんですが、そういう写真を撮るためには運動神経が要る。でも僕は運動神経が悪くて、「ここだ!」という一番いい瞬間にシャッターを切れなくて、写真が下手くそだといわれていました。だからか、決定的な瞬間があったとしても、その前後だって美しい瞬間のでは? と思うようになりました。決定的瞬間が撮れないようなカメラ[オリンパス ミュー]を、好むのもそのせいかもしれません。「決定的瞬間」だけがよいとされていた時代から、その前後の瞬間だっていいし、全部の時間もいいでしょ? と、時代とともに「良い」の範囲が広がって来ている。それって他のことにもいえると思うので、そういう意味では、まだ世界にも希望はあるなと感じます。
―運動神経の悪さを受け入れて、他の人は撮らないような決定的瞬間から少しずれた瞬間を撮ることが、一哲さんの個性につながっているんですね。
それも、もちろん運動神経がいい人がいるからこそ、なんですよね。

―「やさしいだけ」の写真は、「良いとされるもの」がピンポイントに定められていた時代から、その範囲が引き伸ばされてきている時代の変化を反映しているのかもしれませんね。
「やさしいだけ」の展示はずっと前から準備していたことでもあったので合わせたつもりはないけど、たまたま自分の感覚がリンクしたのかなという気はします。昔は完全にこれが正しい、絶対的に美しいと思われていたものがひっくり返ることが、この5年や10年の間に起こっている。そうすると自分の感覚や感性なんて信用できるものではないと思っています。でも、やさしいっていう感覚は、100年後も否定的にとらえられることはないと思うんです。
| タイトル | |
|---|---|
| 会期 | 2020年10月3日(土)~10月31日(土) |
| 会場 | |
| 時間 | 12:00~18:00 |
| 休館日 | 日月曜、祝日 |
| URL |
松岡一哲|Ittetsu Matsuoka
1978年生まれ。日本大学芸術学部写真学科卒業後、スタジオフォボスに勤務し、独立。フリーランスの写真家として活動するかたわら、2008年6月よりテルメギャラリーを立ち上げ、運営。主にファッション、広告などコマーシャルフィルムを中心に活躍する一方、日常の身辺を写真に収めながらも、等価な眼差しで世界を捉え撮影を続ける。主な個展に「マリイ」Bookmarc(東京、2018年)、「マリイ」森岡書店(東京、2018年)、「Purple Matter」ダイトカイ(東京、2014年)、「やさしいだけ」流浪堂(東京、2014年)「東京 μ粒子」テルメギャラリー(東京、2011年)など。現在は東京を拠点に活動。
2021年3月以前の価格表記は税抜き表示のものがあります。予めご了承ください。